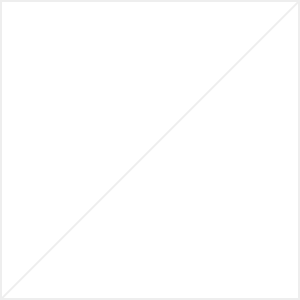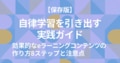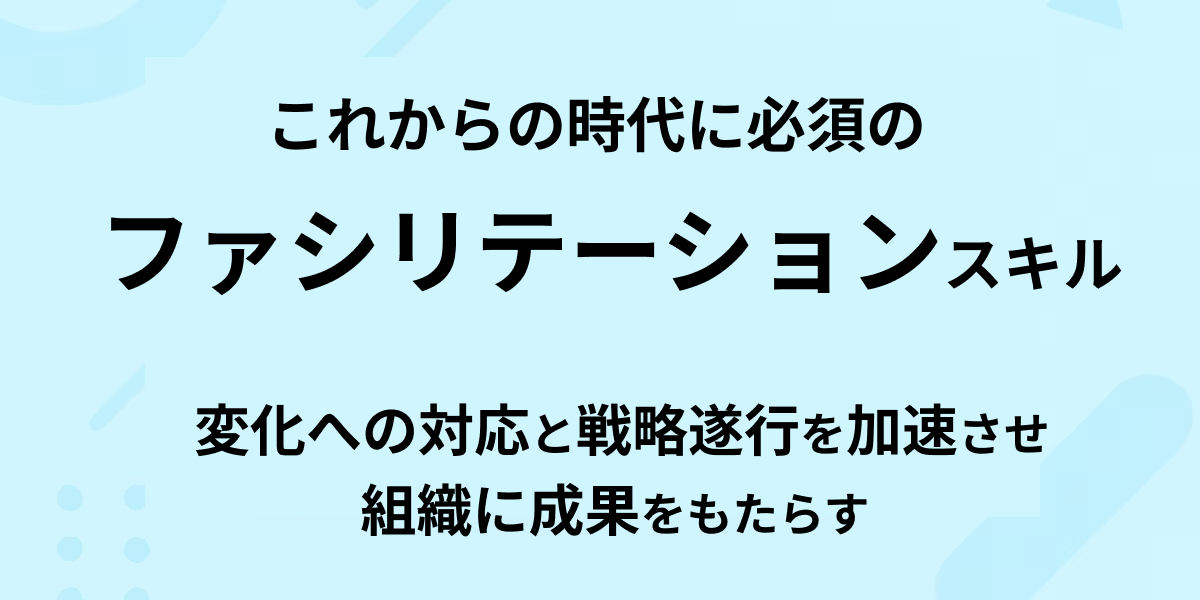
これからの時代に必須のファシリテーションスキル|変化への対応と戦略遂行を加速させ、組織に成果をもたらす
「最近の会議、発言する人がいつも同じだな…」
「リーダー候補者たちの“巻き込み力”が弱い気がする…」
こんな悩みを抱える人事・育成担当者や現場マネジャーの方は多いのではないでしょうか。
今、変化の激しいビジネス環境の中で、組織やチームが成果を上げるために、リーダーに求められる重要なスキルのひとつが「ファシリテーション」です。
本記事では、「なぜ、現代のリーダーにファシリテーションスキルが求められているのか」を中心に解説しながら、ファシリテーションスキル教育の重要性について、改めてお伝えできればと思います。また、ファシリテーション力を高めるために必要な「4つのスキルセット」についても解説します。企業の人事・育成ご担当者様が、社員に学習機会の提供を検討される際の、教育設計の参考にもなれば幸いです。
目次[非表示]
- 1.ファシリテーションとは何か|定義とファシリテーターの役割
- 2.ファシリテーションが注目される背景
- 2.1.統率型から巻き込み型へ
- 2.2.正解のない時代における意思決定のあり方の変化
- 2.3.組織の「フラット化」による、リーダーに求められる役割の変化
- 2.4.多様化する人材と働き方による関係性のあり方の変化
- 2.5.戦略遂行とイノベーションに不可欠な「ダイバーシティ」と「心理的安全性」
- 3.正解のない時代だからこそ必要とされているファシリテーションスキルを持ったリーダーの存在
- 3.1.組織を動かし、成果をもたらすリーダーに求められる、“ファシリテーター的”な3つの役割
- 3.1.1.1)“考える場”を設計し、意見の対話を通じて、より良い意思決定に導く“支援者”
- 3.1.2.2)戦略を現場に接続し、チームが動き出す“対話の設計者”
- 3.1.3.3)合意形成と巻き込みによって、“戦略の実行力を高める”中心的役割
- 3.2.ファシリテーションは“戦略と現場”を“つなぐ”
- 4.組織が強くなる――ファシリテーションによる3つの効果
- 4.1.①会議・ミーティングの生産性と意思決定の質の向上
- 4.2.②メンバーの能力開発| 対話による巻き込みがメンバーの“考える力”と“発言力”を育てる
- 4.3.③チーム力とエンゲージメントの向上
- 4.4.ファシリテーションで組織が強くなる
- 5.現代のリーダーがファシリテーションを学ぶ意義
- 5.1.新任管理職・リーダー候補者に“最初に学ばせたい”スキル
- 5.2.職場や業種を問わずに活用できる“汎用性の高い”スキル
- 5.3.「個人の力」を「組織の力」に変換する“橋渡し”役
- 5.4.ファシリテーションは「学べる」スキル
- 6.ファシリテーションスキルを高めるために必要な4つのスキルセットとは?
- 6.1.①議論の構造をつくる――論理的思考力
- 6.2.②アンコンシャス・バイアスの緩和――「問い」を立てる力
- 6.3.③心理的安全性の確保――「意見を安心して言える」場をつくる力
- 6.4.④対人コミュニケーションスキルの向上――“聴く”力と“質問”力
- 6.5.ファシリテーションは4つのスキルセットで構成された複合的なスキル
- 7.戦略的人材育成を強化する4種類の学習形態
- 8.まとめ|社内の“共通言語化”を視野に入れた教育設計が組織を強くする
ファシリテーションとは何か|定義とファシリテーターの役割
ファシリテーションとは
「ファシリテーション(Facilitation)」とは、会議やミーティングの場で参加者の意見を引き出し、議論を活性化させ、合意形成や意思決定を円滑に進めるためのスキルやプロセスのことを指します。
語源は「容易にする」「促進する」という意味のラテン語 facilis に由来し、ファシリテーターはその名の通り、「進行役」や「場を整える人」という役割を担います。
そして近年、ビジネス用語としても定着しつつある「ファシリテーション」は、メンバー一人ひとりが納得し、行動に移せるような意思決定を導くために、場の空気や心理的安全性に配慮しつつ、全体の流れをデザインする高度なコミュニケーション技術として、特に、次世代リーダーやマネジャーが備えるべきスキルとして、注目されています。(「なぜ注目されているのか」については次章で詳しく解説します)
ファシリテーターと「議長」「司会」「コーチ」との違い
「ファシリテーションとは何なのか」をより明確にするために、会議やミーティングの場におけるファシリテーターと、「議長」 「司会」 「コーチ」との役割の違いを比較して見てみましょう。
役割 | 主な目的 | 場の例 | 関与の仕方 |
議長 | 組織的な意思決定と統率 | 委員会、取締役会 | 会議の議事進行を行い、決定権を持つことも多い |
司会 | 時間通りに遂行し、場をまとめる | 講演会、パネルディスカッション | 内容には関与せず、話題の順番や時間を管理する |
コーチ | 個人の成長支援と内省の促進 | 1on1ミーティング、キャリア面談 | 質問を通じて気づきや、行動変容を引き脱 |
ファシリテーター | 対話の促進と合意形成 | 会議、プロジェクトミーティング | 中立的立場で意見を引き出し、方向性を導く |
このように、ファシリテーターは特定の立場に偏らず、あくまで中立的な視点から場の設計や進行を担う存在です。参加者一人ひとりの声に耳を傾け、対話を通じて多様な意見を整理しながら、合意形成と行動へとつなげていきます。
チームの力を最大限に引き出す推進役としての役割を担うファシリテーターは、まさに“戦略実行を支えるキーパーソン”といえる存在です。
ファシリテーションが注目される背景
変化の激しいビジネス環境において、組織のリーダーやマネジャーに求められる能力は大きく変化しています。かつては「明確な指示を出す」「速やかに意思決定する」ことが重視されていましたが、現代では「多様なメンバーを巻き込み、共に考え、共に決める」姿勢が問われるようになりました。
こうした変化の根底には、以下のような5つの背景があります。
統率型から巻き込み型へ
従来のリーダー像は、「チームを統率し、明確なゴールに向けて成果を上げる存在」でした。カリスマ的なリーダーが正解を提示し、メンバーを牽引するというスタイルは、安定した市場や明確な答えが存在する時代には有効でした。
しかし、市場の不確実性が高まり、複数の選択肢の中から最善を選ぶ必要がある場面が増えた今、特に現場のリーダーに必要なのは「チームを巻き込み、共に考え、解を導く姿勢」です。
今、この時代に、特に現場で求められているのが、問いを立て、対話を促進し、心理的安全性を確保しながらメンバーの主体性を引き出す「ファシリテーター的リーダーの存在」なのです。
正解のない時代における意思決定のあり方の変化
近年、テクノロジーの進化や国際情勢の不安定化、環境・サステナビリティ課題など、あらゆる要素が絡み合い、従来のような「唯一の正解」が通用しにくくなっています。判断材料は常に不十分であり、未来は予測困難です。
そのような状況下では、一人のリーダーが「正解」を提示するよりも、多様なメンバーの知見を持ち寄って意思決定を行う「共創型の意思決定」が必要になります。
ファシリテーションはまさにこの共創型の意思決定を支える技術です。論点を整理し、対話を促し、合意を形成するファシリテーションスキルは、戦略的判断や現場での実行力を高めるうえで不可欠なものになっているといえるでしょう。
組織の「フラット化」による、リーダーに求められる役割の変化
かつての企業はピラミッド型の組織が主流で、意思決定はトップダウンで行われていました。しかし現在、多くの企業がプロジェクト型・マトリクス型のようなフラットで機動力のある組織へと変化しています。
この変化により、リーダーはもはや「命令する存在」ではなく、「メンバーを巻き込み、支援する存在」としての役割が期待されるようになっています。
チームを横断的にまとめ、部門や立場を超えて合意を形成し、行動へと導く――こうしたリーダー像の中核を担うのが、ファシリテーションスキルです。
多様化する人材と働き方による関係性のあり方の変化
グローバル化・ジェンダー多様化・価値観の多様性・リモートワークの普及――こうした背景により、現代の組織では、異なる価値観や働き方を持つ人々が協働する機会が増えています。
その結果、かつての「暗黙の了解」や「一体感」に頼ったマネジメント、これまで暗黙のうちに共有されていた「常識」や「阿吽の呼吸」、理解を求めてきた「察する」「背中で語る」が通用しづらくなっています。つまり、意図を言語化し、対話によって相互理解を築く力が不可欠です。
ファシリテーションは、こうした多様性の中で、信頼を築き、違いを力に変えることができる技術でもあるのです。
戦略遂行とイノベーションに不可欠な「ダイバーシティ」と「心理的安全性」
Googleの調査(Project Aristotle)*でも示されたように、チームの生産性や創造性を高めるには、心理的安全性が不可欠です。加えて、戦略の実行やイノベーションを実現するには、多様な人材が自由に意見を出せる土壌=心理的安全性とダイバーシティの両立が必要です。
ファシリテーションは、こうした環境を作る中心的な手法です。
安心して話せる場を設計する
多様な意見を引き出す
異なる意見を対立させず統合する
これらを通じて、ファシリテーションスキルを備えるリーダーは、チームの力を最大化し、戦略実行と価値創出を加速させる存在になれるのです。
*参考:GoogleのProject Aristotle
Googleのリサーチチームは、何が真にチームの効果性に影響を与えるかを突き止めるために、収集したデータを分析しました。その結果によると、真に重要なのは「誰がチームのメンバーであるか」より「チームがどのように協力しているか」であるとしています。またチームの効果性に影響する因子は以下の5つであった、としています。
①心理的安全性
②相互信頼
③構造と明確さ
④仕事の意義
⑤インパクト
詳細はGoogleによるこちらのレポートページをご覧ください。
次章では、こうした背景を踏まえ、「どのようなリーダー像が今求められているのか」「ファシリテーションはどのように役立つのか」を解説します。
正解のない時代だからこそ必要とされているファシリテーションスキルを持ったリーダーの存在
現代のビジネス環境は、もはや「正解のある問題を、素早く、正確に解く力」だけでは対応できません。市場の急速な変化、デジタル化の進展、サステナビリティの重視といった要素が複雑に絡み合い、「これが正解」と言い切れる道筋が存在しない中で意思決定を下すことが日常的になっています。
こうした中で注目されているのが、“ファシリテーター的なリーダー”です。ここでは、現代の組織に求められるこの新しいリーダー像と、ファシリテーションが果たす役割について具体的に見ていきましょう。
組織を動かし、成果をもたらすリーダーに求められる、“ファシリテーター的”な3つの役割
リーダーはもはや「指示を出す人」ではなく、「共に考え、共に動く人」であることが求められています。その中でも、ファシリテーションスキルを備えたリーダーは、以下の3つの役割を担うことで、戦略の実行力を高め、組織に成果をもたらします。
1)“考える場”を設計し、意見の対話を通じて、より良い意思決定に導く“支援者”
正解の見えない状況において、誰もが安心して意見を出し合い、対話を通じて意思決定を行う「場」の設計が、リーダーの重要な役割となっています。
問いの立て方、議論の構造、論点の提示、意見の引き出し方――こうした一連の設計が、思考の質と結論の納得感を左右するのです。
ファシリテーター的リーダーは、メンバーに答えを与えるのではなく、メンバーの思考を支援しながら“最適解”にたどり着くための環境を整えます。
2)戦略を現場に接続し、チームが動き出す“対話の設計者”
いかに優れた戦略を描いても、それが現場に浸透せず、アクションにつながらなければ意味がありません。
経営戦略と現場の実行をつなぐ「橋渡し役」として、リーダーが果たすべきは「対話を通じて現場の納得感を高める」という行動です。
ファシリテーションスキルがあれば、戦略の背景や意義を言語化し、メンバーの意見を引き出し、現場レベルで「自分ごと化」させることが可能になります。これは、単なる伝達ではなく、“共に戦略を体得するプロセス”を意味します。
3)合意形成と巻き込みによって、“戦略の実行力を高める”中心的役割
組織の意思決定は、トップダウンの号令だけでは動きません。メンバーが納得し、自らの意志で動くことが、戦略の実行力を高める鍵です。
ファシリテーター的リーダーは、チームの合意形成を支援し、意見の違いを統合して、組織全体を一つの方向へと導くことができます。特に、「自分たちで決めた」「参加した」という感覚(当事者意識)は、実行へのコミットメントを格段に高めます。
このように、ファシリテーションは「戦略の実行力」を高めるための中核スキルなのです。
ファシリテーションは“戦略と現場”を“つなぐ”
多くの企業で、戦略と現場の乖離が課題となっています。戦略は経営層で描かれていても、現場にはその意義が伝わらず、単なる作業になってしまっている――こうした断絶は、多くの企業に共通する“見えにくい停滞”の一因です。
この断絶を埋めるのが、まさにファシリテーター的リーダーの役割です。戦略の意図をかみ砕いて伝え、現場の声をすくい上げ、「双方向の対話」を通じて戦略の意味を再構築する――ファシリテーションは、そうした機能を持った「実行支援のスキル」でもあるのです。
次章では、ファシリテーションによって組織にもたらされる3つの主要な効果について解説していきます。これにより、ファシリテーションが単なる「会議技法」ではなく、戦略遂行・人材開発・チーム強化を支える基盤的スキルであることが、より具体的に見えてくるはずです。
組織が強くなる――ファシリテーションによる3つの効果
ファシリテーションは、単なる“会議の進行技術”ではありません。戦略の実行力を高め、メンバーの能力を引き出し、チームの一体感と信頼を醸成する――つまり、組織そのものの力を底上げする「仕組み」として機能するスキルです。
ここでは、ファシリテーションによって組織にもたらされる3つの主要な効果について解説します。なお、これらはいずれも、人的資本経営の視点からも極めて重要な意味を持つものであり、リーダー候補者に早期に習得してもらうべき理由を裏付けるものです。「ファシリテーションスキル教育を導入したいが、必要性を説明する必要があって困っている」といったご状況でしたら、ぜひ本コラムを参考にしていただければと思います。
①会議・ミーティングの生産性と意思決定の質の向上
会議やミーティングは、単なる情報共有の場ではなく、組織にとって重要な意思決定を行ったり、前進の方向を決めたり、アイデアを創出したりする“インフラ”です。もしも実際の現場に次のような課題が多く見受けられるようであれば、リーダーのファシリテーション能力開発の検討が必要なのかもしれません。
<会議・ミーティングの場で見られる課題の例>
アジェンダが曖昧で、目的が分からない
一部の人しか発言しない、発言するメンバーが限られている
話が発散し、結論が出ない
議論はできていても、「誰が何をやるか」が曖昧
ファシリテーションスキルを備えたリーダーであれば、次のような会議を設計・運営できます。
会議前に、目的・論点・時間配分を整理しアジェンダとして共有する
会議中は、問いを通じて発言を促し、構造的に意見を整理する
会議後は、合意事項とアクションを明確に共有する
このような会議運営により、会議の生産性は飛躍的に高まり、意思決定のスピードと質も向上します。ファシリテーションには、戦略実行を強力に後押しする力があるのです。
②メンバーの能力開発| 対話による巻き込みがメンバーの“考える力”と“発言力”を育てる
ファシリテーションは、メンバーの成長を促進する役割を果たすことができます。
リーダーが一方的に話すのではメンバーは受け身にとどまります。しかし、リーダーがファシリテーターとして、場をつくり、問いを投げかけ、発言を引き出し、対話を通じて意思決定を進めていくことで、メンバーには次のような変化が生まれます。
自分の考えを言語化する力が育つ
他者の意見を聴き、自らの視点を広げられる
なぜそう考えるのかを掘り下げる中で、論理的思考力が強化される
意見を交わす中で、問題の本質をつかむ力が養われる
つまり、日常的な会議やミーティングが、適切かつ効果的なファシリテーションによって、“人材育成の場”になります。
リーダーは、組織にとって「成果を上げる人」であると同時に、「人を育てる人」でもあるべきです。だからこそ、リーダー候補者によるファシリテーションスキルの早期習得が、組織力の向上にも直結するのです。
③チーム力とエンゲージメントの向上
最後に挙げたいのが、チームの一体感や信頼関係の醸成におけるファシリテーションの効果です。
良質なファシリテーションによって、以下のようなメリットを享受することができます。
自分の意見が尊重されることによる承認欲求の充足
対話の中でのフィードバックによる納得感と学習機会の増強
互いの意見を聴き合う中で醸成される信頼関係の構築
「自分たちで決めたこと」という当事者意識の高まり
こうしたプロセスは、単なる「和気あいあい」ではなく、組織の心理的安全性の土台となり、自律的なチームへの進化、チーム力とエンゲージメントの向上を後押しします。結果として、チームのパフォーマンスは確実に高まるでしょう。
ファシリテーションで組織が強くなる
ここまでに解説したように、ファシリテーションがもたらす以下の3つの効果
会議・ミーティングの質向上
メンバーの能力開発
チーム力とエンゲージメントの向上
はいずれも、「人的資本経営」や「戦略遂行力強化」といった、組織の中長期的課題を解決するための基盤的スキルであり、書籍や現場実践、属人的な指導のみではなかなか習得が難しく、育成施策としての投資対象として価値のあるものです。
だからこそ、組織の未来をつくるファシリテーション教育が、今あらためて注目されているのです。
現代のリーダーがファシリテーションを学ぶ意義
現代のリーダーにとって、ファシリテーションスキルは、戦略遂行・人材育成・組織成果の最大化を担う中核スキルです。
ここまでに解説したように、ファシリテーションには以下のような効果があります。
会議・ミーティングの生産性向上と、質の高い意思決定
対話を通じたメンバーの能力開発
心理的安全性を高め、チームの一体感と信頼を醸成する
これらは、いずれも「人的資本経営」に直結する成果であり、企業の持続的成長を支える“見えにくい資産”を築く要素です。
そのため、企業の研修や教育設計においては、ファシリテーションスキルの習得を一過性の研修で終わらせず、戦略的に組み込むべき投資領域と捉えることが重要です。
新任管理職・リーダー候補者に“最初に学ばせたい”スキル
ファシリテーションスキルは、現場の課題解決や人材マネジメントといった日々の業務の中で頻繁に必要とされるスキルであり、育成の初期段階で学んでおくことが極めて効果的です。
特に、新任管理職やリーダー候補者には、以下の観点から早期教育が推奨されます。
自らのマネジメントスタイルを形づくる初期段階で“対話型・巻き込み型”の視点を持たせる
指示型・評価型マネジメントに偏ることを防ぐ
周囲との信頼関係構築を促進し、リーダーシップ発揮の土台を築く
また、若手~中堅社員のうちから「問いを立てる」「対話を設計する」経験を積むことで、次世代の経営幹部候補の思考力と対人力を高いレベルで育成することが可能になります。
職場や業種を問わずに活用できる“汎用性の高い”スキル
ファシリテーションスキルのもう一つの重要性は、職場や業種を問わずに活用できる“汎用性の高さ”にあります。
プロジェクト型組織、フラット型組織、自律分散型組織など
正社員・派遣・業務委託など多様な雇用形態
対面・リモート・ハイブリッドな働き方
こうした複雑化する組織環境の中であればこそ、よりファシリテーションの力が不可欠なのです。
「何を話すか」よりも「どう話し合うか」が成果を分けることもある時代において、ファシリテーションはまさに“組織運営のインフラ”的なスキルなのです。
「個人の力」を「組織の力」に変換する“橋渡し”役
企業が今、本当に育てたいのは「成果を上げられる個人」ではなく、周囲を巻き込み、成果を共に生み出す人材=共創型リーダーです。
リーダーがファシリテーターとしての力を持つことで、以下のような組織的な効果とメリットを期待できます。
組織の知恵が表出しやすくなる
議論が深まり、方向性が明確になる
合意形成が進み、行動変容につながる
個々のメンバーの力を引き出し、それらを構造的に束ね、戦略実行につなげる「接続スキル=ファシリテーション」が不可欠なのです。
ファシリテーションは「学べる」スキル
最後に強調したいのは、ファシリテーションは「才能」ではなく「誰でも学べるスキル」であるということです。
問いを立てる力
論点を構造化する思考力
発言を引き出す問いかけと傾聴
合意形成に向けた対話の設計
これらは、適切なカリキュラムと実践機会があれば、確実に伸ばせるスキルです。
とりわけ、サイコム・ブレインズのeラーニング教材「コースウェア」や、双方向の対話を重視した「まなラン」のような実践型プログラムは、ファシリテーションスキルの習得に最適な設計がなされており、多忙なリーダー候補者にも、“質の高い学びの場”を無理なく提供できるソリューションです。
リーダーがファシリテーションを学ぶことは、個人のスキルアップにとどまりません。
そのスキルが社内に浸透することで、組織の風土改革・共通言語の形成へとつながっていきます。
「経営と現場をつなぐ」 「多様性を活かす」 「戦略を実行に移す」――こうした未来をつくるのは、ファシリテーションを武器としたリーダーに他ならないのです。
ファシリテーションスキルを高めるために必要な4つのスキルセットとは?
ファシリテーションとは、ここまでに繰り返しお伝えしてきたように、単に「話し合いをうまく仕切る」技術ではありません。多様な人の意見を引き出し、構造的に整理し、納得と合意を生み出すことで、戦略実行を加速させるリーダーの基盤スキルです。
そのファシリテーションを習得するには、以下の4つの能力=スキルセットを段階的かつ総合的に高めていく必要があります。
論理的思考力
アンコンシャス・バイアスをなくす視点
心理的安全性の確保
対人コミュニケーションスキルの向上
以下に、それぞれの能力について解説します。
①議論の構造をつくる――論理的思考力
ファシリテーションは、場の進行役であると同時に「議論の設計者」としての役割も担います。
その際に求められるのが、「論点を整理し、順序立てて構造化する力」です。
例えば、以下のような問いを立てながら、話し合いの土台を設計することが求められます。
会議の目的とゴールが何か
現状とあるべき姿のギャップ(=問題)は何か
どんな論点を押さえて、どんな順番で話し合うべきか
抜け漏れなく、論点が網羅されているか
このような論理的思考による構造設計があることで、議論が発散せず、合意形成がスムーズに進むようになります。
ホワイトボードやフレームワークを活用して「見える化」する力も含めて、論理的思考力はファシリテーションにおける最初の土台です。「見える化」することで、参加者の思考もクリアになり、合意形成が進みやすくなります。
②アンコンシャス・バイアスの緩和――「問い」を立てる力
アンコンシャス・バイアスとは、無意識の偏見や思い込みのことです。ファシリテーションの場では、「誰の意見も置き去りにしない」設計が不可欠です。しかし現実的には、リーダー自身や参加者の中に無意識の思い込み(=アンコンシャス・バイアス)が存在し、多様な意見の出現を妨げてしまうことがあります。例えば「若手にはまだ難しいだろう」「あの人はこういう考え方に違いない」といった固定観念は、発言の機会や対話の可能性を狭めてしまう危険があります。
そのため、リーダーは、ファシリテーターとして、意識的に以下のような多様性を促す「問い」を持ち続ける必要があります。
「それは誰の視点だろう?」
「他にどんな見方があるだろう?」
「本当にそう言い切ってよいのか?」
といった問いを立てながら、偏見を緩和し、場に多様な意見を引き出す、多様な視点を受け入れる、安心安全な土壌を整える力は、組織の中にイノベーションとダイバーシティを加速させる源泉にもなるのです。
③心理的安全性の確保――「意見を安心して言える」場をつくる力
どれほど論点が明確で、構造化された議題が用意されていても、「本音を言えない空気」の中では、意味のある議論は生まれません。
Googleの調査研究「Project Aristotle」でも、高い成果を出すチームの共通項の1つは“心理的安全性”であると明らかにされています。
心理的安全性を確保するために、ファシリテーターは以下のような場の運営スキルと能力が求められます。
発言に対して評価せず、丁寧に受け止める
否定する代わりに、問を重ねて深堀する
発言が少ない人にも「話して良いよ」と促す
こうした行動の積み重ねが、「ここでは安心して話せる」「話しても大丈夫」と感じられる場をつくり、対話の深まり・合意の質の向上・学習の活性化へとつながっていきます。
④対人コミュニケーションスキルの向上――“聴く”力と“質問”力
リーダーがファシリテーターとして「信頼」されるには、実は「うまく仕切る」ことよりも、「よく聞いてくれる」「引き出してくれる」存在であることが非常に重要です。
ファシリテーターが「よく聴いてくれる人」「的確な問いを投げかけてくれる人」であればあるほど、場は活性化し、参加者が主体的に考えるようになります。
具体的には、以下のような行動が重要です。
話を遮らず、最後まで聴く
内容だけでなく、感情や背景に共感する
話がまとまらない場合に、要点を整理して言語化を支援する
問題の本質に気づかせる“深い問い”を投げかける
また、表情やうなずきといった非言語のリアクションも含めて、安心感・信頼感を育むファシリテーションが必要です。
ファシリテーションは4つのスキルセットで構成された複合的なスキル
ここまで紹介した4つの能力は、それぞれが独立したスキルでありながら、ファシリテーションの場面においては相互に補完し合い、統合的に機能する必要があります。
論理的思考で「議論の構造と進行」を設計し、
バイアスへの気づきによって「多様な視点と意見」を引き出し、
心理的安全性の確保によって「安心して発言できる場」をつくり、
対人コミュニケーションスキルによって「信頼関係と対話の質」を高める
こうしたスキル群が相乗的に機能することで、組織における意思決定の質を高め、戦略実行と人材開発の両輪を支えることができるのです。
ファシリテーションは、単なるテクニックではなく、「人と組織を動かすために必須のスキルセット」として、これからのリーダーが必ず身につけておくべ基礎力だと言えるでしょう。
次章では、本コラムのまとめとして、こうしたスキルをどのように学習設計として落とし込み、社内に浸透させるのかについて、実際の研修・教材の紹介も交えながら解説します。
戦略的人材育成を強化する4種類の学習形態
ファシリテーションスキルは、「研修で一度学べば終わり」という類の知識ではありません。現場での実践や経験と結びつけながら、繰り返し学び・試し・振り返ることでようやく定着していくスキルです。 そのため、学習目的や対象者に応じて、効果的な学びの形態を組み合わせて設計することが重要です。 ここでは、サイコム・ブレインズが提供する4つの学習形態と、それぞれの特徴をご紹介します。
オンライン集合研修:効率的かつ低コストで知識習得
オンライン上で講師や他の受講者とリアルタイムにやり取りしながら学ぶ形式。移動・会場コストを抑えつつ、双方向性のある学びを実現できる対面集合研修:交流・体験型学習に強み
その場の空気や相互作用を活かしたロールプレイやディスカッションを実施しやすい。実践力・対人スキルの習得に効果的ハイブリッド研修:オンラインと対面の集合研修の利点を活かす戦略的選択肢
事前のeラーニングで知識を習得し、集合研修で実践・応用を行うなど、学習効果と運用効率を両立できる設計が可能eラーニング/映像教材:自主性を重んじた柔軟な学習スタイル
テキストや動画などを活用し、自分に合ったタイミングと方法で学べる。一方で、学習の継続と定着に工夫が必要
あるいは「独学」と「グループ学習」という切り口から検討することもできます。
独学:自分に合ったタイミングと方法で学べる。自律的に学びたい層に有効。継続支援の仕組みがカギ
グループ学習:仲間と共に学ぶことで、気づきや内省が深まり、学習モチベーションも高まる。仲間との対話や意見交換を通じて、理解を深めると同時に、自身の考えを言語化する力や多様な視点を得る機会にもなる
「誰に」「何を」「どのように」届けるかを一貫して設計することが、人材育成と教育・研修設計の成功のカギとなるのです。
まとめ|社内の“共通言語化”を視野に入れた教育設計が組織を強くする
ファシリテーションは、属人的な才能ではなく、意図的に育成可能なスキルです。
しかも、単なる会議運営テクニックにとどまらず、戦略の実行、人材の成長、組織力の強化に直結するリーダーの基本能力として、多くの企業で注目が高まっています。
人的資本経営が求められる現在、企業には「どのような人材を育て、どのように活かしているのか」を、戦略との連動性を持って示すことが求められています。だからこそ、ファシリテーションのような“組織のベース力”となるスキルを、研修・教育施策の軸に据えることは、非常に理にかなったアプローチです。
ファシリテーションを“共通言語”として育てる意義
社員一人ひとりが、異なるバックグラウンド、価値観、職務経験を持つ中で、組織がまとまり力を発揮していくには、「対話」「問い」「傾聴」「合意形成」といった、共通の行動様式やスキルセットが必要です。これらを“共通言語化”することによって、チームや部署を超えた横のつながりや、リーダー間の連携がスムーズになり、組織の一体感が生まれます。
教育施策は「一気通貫」で考える
リーダー人材にファシリテーションスキルを身につけてもらうには、以下のような一気通貫の教育設計が効果的です。
階層ごとに同じ考え方・スキルを段階的に学べる仕組みを整えること
共通の教材を用いて“言葉の定義”と“行動の基準”を社内でそろえること
研修だけで終わらず、現場での実践やフィードバックの仕組みと接続させること
また、対面・オンライン・eラーニングなどの学習手法の掛け合わせによって、多忙な現場にもフィットした育成が可能になります。特に、集合研修が難しい環境でも、良質な教材を通じて自律的に学ぶ文化を根づかせることが、今後ますます重要になるでしょう。
お役立ち資料
関連サービス
関連記事
■本記事の監修者■