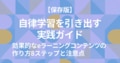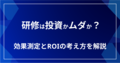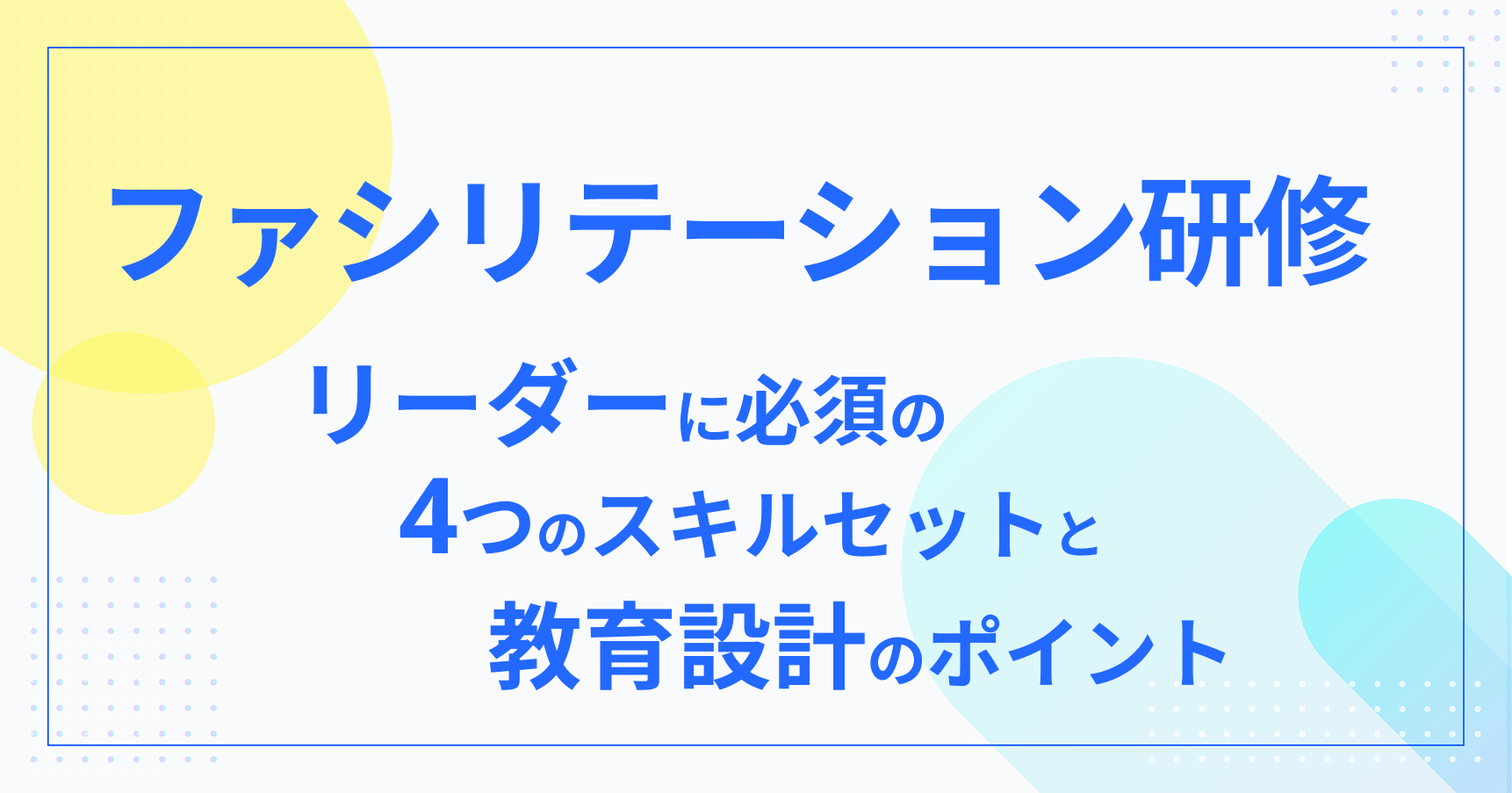
【ファシリテーション研修】リーダーに必須の4つのスキルセットと教育設計のポイント
「最近の会議、発言する人がいつも同じだな…」
「毎日会議ばかり…」
「会議の時間が長くなりがち・・・」
「議論の中身が薄い」
こんな悩みを抱える人事・育成担当者や現場マネジャーの方は多いのではないでしょうか。
今、変化の激しいビジネス環境の中で、組織やチームが成果を上げるために、リーダーに求められる重要なスキルのひとつが「ファシリテーション」です。
本記事では、そもそも現代のリーダーがなぜファシリテーションスキルを身につける必要があるのか、ファシリテーション力を高めるために必要な「4つのスキルセット」について解説します。
企業の人事・育成ご担当者様が、社員に学習機会の提供を検討される際の、教育設計の参考になれば幸いです。
【無料ダウンロード資料】
▼サービス概要資料 『ファシリテーショントレーニング』
▼お役立ち資料
目次[非表示]
- 1.ファシリテーションとは何か|定義とファシリテーター的リーダーの役割
- 2.ファシリテーションスキルが組織にもたらす5つの効果
- 2.1.①会議・ミーティングの生産性と意思決定の質が向上する
- 2.2.②メンバーの能力開発と育成| メンバーの“考える力”と“発言力”を育てる
- 2.3.③チーム力とエンゲージメントが向上する
- 2.4.④集団による知的相互作用を促進する
- 2.5.⑤戦略と現場をつなぐ
- 3.ファシリテーションを構成する「4つのスキルセット」
- 3.1.①議論の構造をつくる――論理的思考力
- 3.2.②アンコンシャス・バイアスの緩和――「問い」を立てる力
- 3.3.③心理的安全性の確保――「意見を安心して言える」場をつくる力
- 3.4.④対人コミュニケーションスキルの向上――“聴く”力と“質問”力
- 3.5.ファシリテーションは4つのスキルセットで構成された複合的なスキル
- 4.ファシリテーション研修を設計する
- 4.1.3つの学習形態の各メリット: 効果的に組み合わせて設計する
- 4.1.1.組み合わせの例:
- 4.2.独学とグループ学習の各メリット: 使い分けて設計する
- 4.3.「誰に・いつ・どのように学ばせるか」を設計する
- 4.4.どのように学んでもらうか|おすすめしたい研修動画・eラーニング・パッケージプログラムの活用
- 5.まとめ
ファシリテーションとは何か|定義とファシリテーター的リーダーの役割
ファシリテーションとは
「ファシリテーション(Facilitation)」とは、会議やミーティングの場で参加者の意見を引き出し、議論を活性化させ、合意形成や意思決定を円滑に進めるためのスキルやプロセスのことを指します。
語源は「容易にする」「促進する」という意味のラテン語 facilis に由来し、ファシリテーターはその名の通り、「進行役」や「場を整える人」という役割を担います。
そして近年、ビジネス用語としても定着しつつある「ファシリテーション」は、メンバー一人ひとりが納得し、行動に移せるような意思決定を導くために、場の空気や心理的安全性に配慮しつつ、全体の流れをデザインする高度なコミュニケーション技術として、特に、次世代リーダーやマネジャーが備えるべきスキルとして、注目されています。(「なぜ注目されているのか」については次章で詳しく解説します)
正解のない時代だからこそ必要とされているファシリテーションスキルを持ったリーダーの存在
現代のビジネス環境は、もはや「正解のある問題を、素早く、正確に解く力」だけでは対応できません。市場の急速な変化、デジタル化の進展、サステナビリティの重視といった要素が複雑に絡み合い、「これが正解」と言い切れる道筋が存在しない中で意思決定を下すことが日常的になっています。
こうした中で注目されているのが、“ファシリテーションスキルを持ったリーダーの存在”です。
ファシリテーターと「議長」「司会」「コーチ」との違い
「ファシリテーションとは何なのか」をより明確にするために、会議やミーティングの場におけるファシリテーターと、「議長」 「司会」 「コーチ」との役割の違いを比較して見てみましょう。
▶図表1:ファシリテーターと「議長」「司会」「コーチ」との違い
役割 | 主な目的 | 場の例 | 関与の仕方 |
議長 | 組織的な意思決定と統率 | 委員会、取締役会 | 会議の議事進行を行い、決定権を持つことも多い |
司会 | 時間通りに遂行し、場をまとめる | 講演会、パネルディスカッション | 内容には関与せず、話題の順番や時間を管理する |
コーチ | 個人の成長支援と内省の促進 | 1on1ミーティング、キャリア面談 | 質問を通じて気づきや、行動変容を引き脱 |
ファシリテーター | 対話の促進と合意形成 | 会議、プロジェクトミーティング | 中立的立場で意見を引き出し、方向性を導く |
このように、ファシリテーターは特定の立場に偏らず、あくまで中立的な視点から場の設計や進行を担う存在です。参加者一人ひとりの声に耳を傾け、対話を通じて多様な意見を整理しながら、合意形成と行動へとつなげていきます。
チームの力を最大限に引き出す推進役としての役割を担うファシリテーターは、まさに“戦略実行を支えるキーパーソン”といえる存在です。
ファシリテーションスキルが組織にもたらす5つの効果
ファシリテーションは、単なる“会議の進行技術”ではありません。
戦略の実行力を高め、メンバーの能力を引き出し、チームの一体感と信頼を醸成する――つまり、組織そのものの力を底上げする力として機能するスキルです。
ここでは、ファシリテーションによって組織にもたらされる4つの主要な効果について解説します。これらはいずれも、人的資本経営や戦略遂行力強化の視点からも極めて重要な意味を持つものであり、リーダー候補者に早期に習得してもらうべき理由を裏付けるものです。
「ファシリテーションスキル教育を導入したいが、必要性を説明する必要があって困っている」といったご状況でしたら、ぜひ本記事を参考にしていただきつつ、お気軽にご相談いただければと思います。
【お役立ち資料】
①会議・ミーティングの生産性と意思決定の質が向上する
会議やミーティングは、単なる情報共有の場ではなく、組織にとって重要な意思決定や方向性の確認、アイデア創出を行う“インフラ”です。
現場に以下のような課題が多く見られるようであれば、リーダーのファシリテーション能力開発の検討が必要なのかもしれません。
<会議・ミーティングの場で見られる課題の例>
アジェンダが曖昧で、目的が分からない
一部の人しか発言しない(発言するメンバーが限られている)
話が発散し、結論が出ない
議論はできていても、「誰が何をやるか」「いつまでに」が曖昧
ファシリテーションスキルを備えたリーダーであれば、次のような会議を設計・運営できます。
会議前に、目的・論点・時間配分を整理しアジェンダとして共有する
会議中は、問いを通じて発言を促し、構造的に意見を整理する
会議後は、合意事項とアクションを明確に共有する
このような進行ができることで、会議の生産性は飛躍的に高まり、意思決定のスピードと質の向上が期待できます。
②メンバーの能力開発と育成| メンバーの“考える力”と“発言力”を育てる
ファシリテーションには、メンバーの思考力や発言力を高める効果があります。
リーダーがファシリテーションスキルを使って、場をつくり、問いを立て、発言を引き出し、対話を通じて意思決定を進めていくことで、メンバーは受け身から脱却し、以下のような力を育むことができます。
自分の考えを言語化する力
他者の意見を聴き、自らの視点を広げる力
論理的に思考し、掘り下げて考える力
問題の本質をとらえる分析力
このような効果的なファシリテーションができれば、日常の会議やミーティングが“人材育成の場”として機能し始め、メンバーの早期戦力化にもつながり、組織力強化に貢献します。
③チーム力とエンゲージメントが向上する
ファシリテーションには、以下のように、チーム内の信頼や一体感を醸成し、心理的安全性のある職場づくりに寄与します。
意見を尊重される経験が、自己肯定感や当事者意識を高める
フィードバックが学びと成長の機会になる
共感と理解の積み重ねが、信頼関係の土台を築く
このように、ファシリテーションには、エンゲージメントの高いチームへと進化させる力があります。
④集団による知的相互作用を促進する
ファシリテーションによって、次のような変化や効果が期待できます。
多様な視点の統合
異なるバックグラウンドや知見を持つメンバーによる互いの思考が掛け合わされ、創発的なアイデアが生まれる議論の深まりと本質化
丁寧に問いを立てることで、表層的な意見交換から、議論が深化し、本質的な問いや解に接近できる学習サイクルの促進
議論を通じて仮説→検証→修正という学習プロセスが自然と回るようになるチームの知恵の蓄積
対話を重ねながら、暗黙知までも言語化され、組織に知見として蓄積されていく
ファシリテーションは「会議を回す」「合意を取る」だけでなく、集団の思考を触発し、知恵を引き出し、そこから新しい知が生まれるような、“集団で知を創る場をデザインする”スキルでもあるのです。
⑤戦略と現場をつなぐ
多くの企業で、戦略と現場の乖離が課題となっています。
経営層で戦略が描かれていても、現場にはその意義が伝わらず、単なる作業になってしまっている――「戦略はあるが伝わらない」、「現場の声は拾われない」――このような停滞を打破することができるのが、ファシリテーター的リーダーの存在です。
戦略の意図をかみ砕き、現場が理解できる形に変換する
現場の声や知見をすくい上げ、双方向の対話を通じて戦略を再構築する
共通理解のもとで、組織全体が一枚岩となって行動できる状態をつくる
人と組織を動かし、戦略実行につなげるファシリテーターとしての役割が、今、リーダーに期待されているのです。
ファシリテーションを構成する「4つのスキルセット」
ファシリテーションとは、ここまでに繰り返しお伝えしてきたように、単に「話し合いをうまく仕切る」技術ではありません。多様な人の意見を引き出し、構造的に整理し、納得と合意を生み出すことで、戦略実行を加速させるリーダーの基盤スキルです。
そのファシリテーションを習得するには、以下の4つの能力=スキルセットを段階的かつ総合的に高めていく必要があります。
論理的思考力
アンコンシャス・バイアスをなくす視点
心理的安全性の確保
対人コミュニケーションスキルの向上
以下に、それぞれの能力について解説します。
①議論の構造をつくる――論理的思考力
ファシリテーションは、場の進行役であると同時に「議論の設計者」としての役割も担います。
その際に求められるのが、「論点を整理し、順序立てて構造化する力」です。
例えば、以下のような問いを立てながら、話し合いの土台を設計することが求められます。
会議の目的とゴールが何か
現状とあるべき姿のギャップ(=問題)は何か
どんな論点を押さえて、どんな順番で話し合うべきか
抜け漏れなく、論点が網羅されているか
このような論理的思考による構造設計があることで、議論が発散せず、合意形成がスムーズに進むようになります。
ホワイトボードやフレームワークを活用して「見える化」する力も含めて、論理的思考力はファシリテーションにおける最初の土台です。「見える化」することで、参加者の思考もクリアになり、合意形成が進みやすくなります。
②アンコンシャス・バイアスの緩和――「問い」を立てる力
アンコンシャス・バイアスとは、無意識の偏見や思い込みのことです。ファシリテーションの場では、「誰の意見も置き去りにしない」設計が不可欠です。しかし現実的には、リーダー自身や参加者の中に無意識の思い込み(=アンコンシャス・バイアス)が存在し、多様な意見の出現を妨げてしまうことがあります。例えば「若手にはまだ難しいだろう」「あの人はこういう考え方に違いない」といった固定観念は、発言の機会や対話の可能性を狭めてしまう危険があります。
そのため、リーダーは、ファシリテーターとして、意識的に以下のような多様性を促す「問い」を持ち続ける必要があります。
「それは誰の視点だろう?」
「他にどんな見方があるだろう?」
「本当にそう言い切ってよいのか?」
といった問いを立てながら、偏見を緩和し、場に多様な意見を引き出す、多様な視点を受け入れる、安心安全な土壌を整える力は、組織の中にイノベーションとダイバーシティを加速させる源泉にもなるのです。
③心理的安全性の確保――「意見を安心して言える」場をつくる力
どれほど論点が明確で、構造化された議題が用意されていても、「本音を言えない空気」の中では、意味のある議論は生まれません。
Googleの調査研究「Project Aristotle」でも、高い成果を出すチームの共通項の1つは“心理的安全性”であると明らかにされています。
心理的安全性を確保するために、ファシリテーターは以下のような場の運営スキルと能力が求められます。
発言に対して評価せず、丁寧に受け止める
否定する代わりに、問を重ねて深堀する
発言が少ない人にも「話して良いよ」と促す
こうした行動の積み重ねが、「ここでは安心して話せる」「話しても大丈夫」と感じられる場をつくり、対話の深まり・合意の質の向上・学習の活性化へとつながっていきます。
④対人コミュニケーションスキルの向上――“聴く”力と“質問”力
リーダーがファシリテーターとして「信頼」されるには、実は「うまく仕切る」ことよりも、「よく聞いてくれる」「引き出してくれる」存在であることが非常に重要です。
ファシリテーターが「よく聴いてくれる人」「的確な問いを投げかけてくれる人」であればあるほど、場は活性化し、参加者が主体的に考えるようになります。
具体的には、以下のような行動が重要です。
話を遮らず、最後まで聴く
内容だけでなく、感情や背景に共感する
話がまとまらない場合に、要点を整理して言語化を支援する
問題の本質に気づかせる“深い問い”を投げかける
また、表情やうなずきといった非言語のリアクションも含めて、安心感・信頼感を育むファシリテーションが必要です。
ファシリテーションは4つのスキルセットで構成された複合的なスキル
ここまで紹介した4つの能力は、それぞれが独立したスキルでありながら、ファシリテーションの場面においては相互に補完し合い、統合的に機能する必要があります。
論理的思考で「議論の構造と進行」を設計し、
バイアスへの気づきによって「多様な視点と意見」を引き出し、
心理的安全性の確保によって「安心して発言できる場」をつくり、
対人コミュニケーションスキルによって「信頼関係と対話の質」を高める
こうしたスキル群が相乗的に機能することで、組織における意思決定の質を高め、戦略実行と人材開発の両輪を支えることができるのです。
ファシリテーションは、単なるテクニックではなく、「人と組織を動かすために必須のスキルセット」として、これからのリーダーが必ず身につけておくべ基礎力だと言えるでしょう。
次章では、こうしたスキルをどのように学習設計として落とし込み、社内に浸透させるのかについて、実際の研修・教材の紹介も交えながら解説します。
スキル | 行動の例 |
|---|---|
論理的思考力 |
|
アンコンシャス・バイアスをなくす視点 |
|
心理的安全性の確保 |
|
対人コミュニケーションスキルの向上 |
|
ファシリテーション研修を設計する
ファシリテーションスキルは、「映像教材を見るだけで身につく」「集合研修で一度学べば終わり」という類の知識ではありません。
現場での実践や経験と結びつけながら、繰り返し学び・試し・振り返ることでようやく定着していくスキルです。
そのため、効果的な学びの形態を組み合わせて設計することが重要です。
ここでは、サイコム・ブレインズが提供する3つの学習形態と、それぞれのメリットをご紹介します。
3つの学習形態の各メリット: 効果的に組み合わせて設計する
▶図表3:3つの学習形態とメリット
提供スタイル | メリット |
|---|---|
オンライン集合研修 | 効率的かつ低コストで知識習得 |
対面集合研修 | 交流・体験型学習に強み |
eラーニング/映像教材 | 自主性を重んじた柔軟な学習スタイル |
組み合わせの例:
映像教材で知識の事前インプット→事前課題に取り組む→半日のオンライン集合研修で課題の共有と演習→映像教材で復習→現場実践に向けた準備→対面もしくはオンラインの集合研修で演習やロールプレイ→現場実践→振り返りのワーク→対面もしくはオンラインの集合研修で総括
あるいは「独学」と「グループ学習」という切り口から検討することもできます。それぞれにメリットがあり、研修を設計する際には何を独学で、何をグループ学習で学んでもらうことが効果的か、という視点での検討も必要です。
独学とグループ学習の各メリット: 使い分けて設計する
▶図表4:学びのスタイルとメリット
学びのスタイル | メリット |
独学 |
|
グループ学習 |
|
「誰に・いつ・どのように学ばせるか」を設計する
ファシリテーションスキルを育成プログラムに組み込む際に重要なのは、「誰に・いつ・どのように」学ばせるかという教育設計の視点です。
ファシリテーションスキルは、部署・職種・業種・年次を問わず、あらゆる業務場面に通用する汎用性の高いスキルでもあります。「リーダーになったら急にファシリテーションができる」というものではありません。リーダーや新任管理職といった特定のポジションに昇進してから学ばせるのではなく、段階的に習得できるように設計されていることが理想です。
▶図表5:育成対象者とスキルの習得レベル
育成対象者 | ファシリテーションを構成する4つのスキルセットを段階的に習得していく |
|---|---|
若手・中堅社員 |
|
プロジェクト参画者やクロスファンクションの担当者 / 新任管理職やリーダー候補者 |
|
マネジメント層 | ファシリテーション自体は部下に任せつつ、
|
より多くの社員がファシリテーションスキルを段階的に学ぶことで、組織全体の力が高まり、持続的な成果創出につながります。また、これからの時代は、良質な教材の活用を通じて“自律的に学ぶ文化を根づかせる”こと=「ラーニングカルチャーを作る」ことが、今後ますます重要になります。
どのように学んでもらうか|おすすめしたい研修動画・eラーニング・パッケージプログラムの活用
ご参考として、サイコム・ブレインズがご提供できるサービス、ソリューションを使ってご紹介します。
①ファシリテーションを含む周辺の、必須のビジネススキル基礎について、信頼と実績ある研修動画で、まずは知識をインプットしたい:
300講座以上の動画でビジネススキルや知識を学習できる見放題サービスの動画ライブラリで学ぶことができます。
1ID単位で利用・購入可能です。法人のお客様には、動画単体のレンタルも可能。貴社のLMSに搭載してご利用もいただけます。詳細はお問い合わせください。
②ファシリテーションの知識インプットと実践力強化ができるeラーニング教材を探している:
目標達成型の進化系eラーニング『コースウエア』は新任管理職向けに開発されたeラーニング教材です。
効果的な学習を実現するために、成人学習学理論と学習の動機付け理論に基づいたインストラクショナルデザインを採用。
①動画、②テキスト+個人ワーク、③理解度テストの3点から構成されており、学習者は、実務で役立つ知識とスキルを、自律的に身につけ、自身の成長を実感することができます。1ID単位で利用・購入可能です。
③会社として、集合研修の要素を取り入れながら、自律的に学習してもらいたい:
『まなラン』は受講者同士で学び合いながら学習を進め、実践力を鍛えるパッケージ・プログラムです。 学習設計された完全オンライン完結型のプログラムですので、集合研修を企画・実施することに伴うスケジュール調整や会場手配といった手間や工数がかからずに、すぐに利用いただけます。
まとめ
ファシリテーションスキルは、誰でも「学び、習得できる」
実は、ファシリテーションは、属人的な才能ではなく、意図的に育成可能なスキルです。
人的資本経営が求められる現在、企業には「どのような人材を育て、どのように活かしているのか」を、戦略との連動性を持って示すことが求められています。だからこそ、ファシリテーションのような“組織力の要”となるスキルを、リーダー研修・教育施策の軸に据えることは、非常に理にかなったアプローチです。
ファシリテーションスキルは「個人の力」を「組織の力」に変換する“橋渡し”役
“ファシリテーションスキル”が全社的に、その重要性が認知され、活用が進むことで、組織の推進力になる
変化の激しい、先の見えない今、企業が本当に育てたい、必要な人材は、周囲を巻き込み、成果を共に生み出すことができる人材=ファシリテーター的リーダーです。
リーダーがファシリテーターとしての力を持つことで、以下のような組織的な効果とメリットを期待できます。
組織の知恵が表出しやすくなる
議論が深まり、方向性が明確になる
合意形成が進み、行動変容につながる
個々のメンバーの力を引き出し、それらを構造的に束ね、戦略実行につなげる「接続スキル=ファシリテーション」が不可欠なのです。
もしも学習教材や研修プログラムを選ぶ際には、学習効果と実践力を考慮して学習設計された、成人学習理論と学習動機付け理論に基づいて開発されたものであることを確認してください。学習の目的とゴールに合わせてしっかりと学習設計されていない教材では、現場実践力まで強化することができません。
【ご参考】サイコム・ブレインズが提供する映像教材や研修プログラムは、確かな学習理論と研修実績約30年の知見を基に設計されています。以下のプログラムは多忙な新任管理職やリーダーおよびその候補者がファシリテーションスキルを習得できるように設計されています。企業の人材育成ご担当者様であれば、実際の教材や受講画面のご紹介なども可能です。
教育のプロも認める、30年の研修実績を持ったサイコム・ブレインズが開発した動画コンテンツ、『コースウエア』、『まなラン』は、確かな学習理論を基に学習設計・開発されているデジタルラーニングサービスです。会社からの指定教材や研修としてのご利用はもちろん、手上げ・自己啓発・自律学習支援の教材・研修としても、安心してご利用いただきやすいように開発・設計されています。
「誰に」「何を」「どのように」届けるか、まで一貫して設計することが、人材育成と教育・研修設計の成功のカギとります。教育・研修設計のご相談含め、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お役立ち資料
関連サービス
▼パッケージプログラム
▼映像教材(動画コンテンツ)
関連記事
■本記事の監修者■