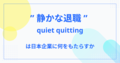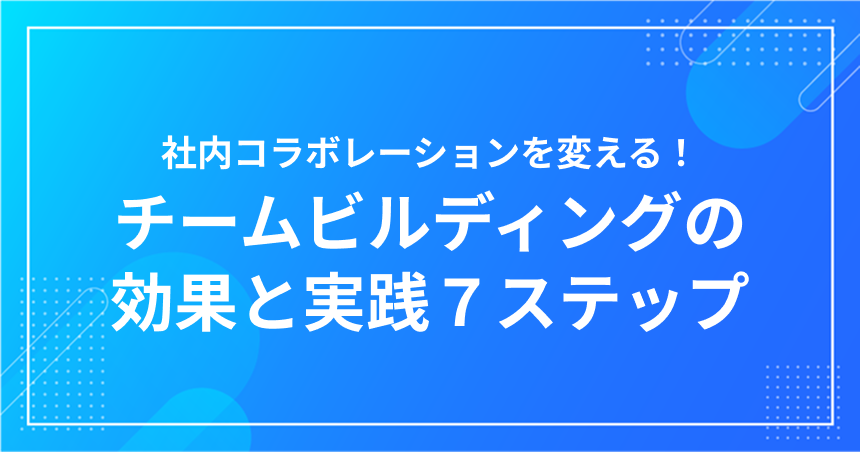
社内コラボレーションを変える!チームビルディングの効果と実践7ステップ
リモートワークの浸透や中途入社メンバーの増加により、「チームとして仕事をする」ことの難しさを感じていませんか?部門間の連携が希薄になり、会議は増えたがコミュニケーションの質は下がったと感じる企業も少なくありません。そこで本コラムでは、チームビルディングを“ただの楽しいイベント”で終わらせず、組織的な成果につなげるためのポイントを整理します。さらに、リモートやハイブリッド環境でも実践可能な具体的な7ステップをご紹介。読了後には、「社内で実施すべきチームビルディングワークショップ」が自信をもって設計できるようになります。
目次[非表示]
なぜ今、チームビルディングが必要なのか
リモート化、部門の細分化、価値観の多様化――こうした変化が「チームで働く」という当たり前を揺るがしています。そこで、改めてチームビルディングの意義を整理します。
リモート/ハイブリッド環境で生まれた“隠れ壁”
当社の組織開発支援の現場でも、近年このテーマに関する相談が急増しています。
「リモート環境でチームの温度差が広がってきた」「オンライン会議では本音が出づらい」「中途入社者がなかなか馴染めない」――こうした声を多くいただきます。
背景としてよく挙げられるのは、次の3点です。
偶発的なコミュニケーションの減少:オフィスでの雑談や立ち話がなくなり、関係構築のきっかけが減った。
情報共有の個別化:メールやチャットが中心となり、部門や職種を越えた交流や情報共有が生まれにくい。
文化の断絶:中途入社者やリモート/ハイブリッド勤務者が、非公式なネットワークやチーム文化を体感しにくい。
このような“隠れ壁”が放置されると、メンバー同士の心理的距離が広がり、表面上は業務が回っていても「関係の質」や「協働のスピード」が低下するケースが少なくありません。だからこそ、チームビルディングを通じて信頼・共通理解を再構築する重要性が高まっています。
現場の声を聞き取り、「関係性」「情報共有」「文化浸透」のどこに壁があるか診断しましょう。
研究が示すチームビルディングの効果とは
複数の研究により、チームビルディングが“チーム機能の土台”を強化することが確認されています。
たとえば、ある研究では、意図的なチームビルディング介入によってチーム内のコミュニケーションネットワークが拡大し、信頼と相互理解が深まる傾向が見られました。
また、メタ分析では「信頼関係」「役割の明確化」「協働プロセスの改善」が、チーム成果の向上に一貫して寄与していることが示されています。
さらに別の研究では、共同体験型の活動がチームの一体感を高め、協働の質を向上させることが確認されています。
これらの結果は、チームビルディングが「単なるイベント」ではなく、信頼・目的・連携プロセスを強化する体系的なアプローチであることを示しています。
▶図1:チームビルディングがもたらす主要な効果要素
設計上、このような成果を目指すことで、施策をただの「楽しい場」から「成果創出の起点」に変えられます。
「なぜやるのか」を明確化し、信頼・役割明確・プロセス改善の3視点を設計初期に確認しましょう。
チームビルディングで狙うべき3つの効果
研究で確認された効果を踏まえ、実務ではどこを狙って設計すべきか――
ここでは、MBK Wellnessが多数の支援現場で有効性を確認してきた3つの焦点を紹介します。
関係性/信頼の強化
対話や共同ワークを通じて、メンバー間の壁を下げ、心理的安全性を育てます。
ある研究では、チームビルディング介入後にチーム内の関係性ネットワークが広がり、メンバー間の信頼が高まったことが確認されています。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786318307609
信頼が高まることで、率直な意見交換やリスク共有が促進され、チーム内の問題解決スピードが上がります。当社の研修では、これを体験的に理解できるよう、心理的安全性に関するワークを取り入れることが多くあります。
役割・目標の明確化と共有
チームが方向性を合わせて動くには、「誰が何を担うか」を明確にする必要があります。
メタ分析でも、信頼や心理的安全性が成果への主要因とされる一方で、役割分担や目標共有の明確化もチームの協働を支える要素の一つとされています。
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169604
このため、当社のチームビルディング研修では、プロジェクト目標や役割分担の必要性と重要性を体感的に理解し、実務における役割の明確化につなげるワークを組み込む場合もあります。
プロセス・コミュニケーション改善
多様な働き方が混在する今、連携の仕方そのものを見直すことが重要です。
別の研究では、協働活動を通じてチームの一体感が高まり、コミュニケーションの質と安定性が改善されたことが確認されています。
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1353944/full
当社の支援でも、実際の業務テーマを題材に「理想的な連携プロセス」を議論することで、チーム内の意思疎通を最適化する事例が多くあります。
▶表1:狙うべき効果と現場の問い(例)
効果 | 現場の問い | ワーク設計のポイント |
|---|---|---|
信頼強化 | 「お互いについて知っているか?」 | 自己紹介+非業務ディスカッション |
役割明確化 | 「私は何を担っていると感じているか?」 | ロールマッピング+目標確認 |
プロセス改善 | 「連携にムダ・抜けはないか?」 | ワークショップで理想プロセス共有 |
目的に応じて「信頼」「役割」「プロセス」のいずれに焦点を置くかを決め、ワークを設計すると効果的です。
一度きりのイベントで終わらせないためのポイント
「イベントは盛り上がったけれど、翌日には元に戻った」──これは多くの企業が経験する課題です。私たちMBK Wellnessも、多くの研修・ワークショップを設計・運営する中で、“楽しかった”を“行動変化”へつなげる設計が何よりも重要だと実感しています。
“楽しかった”から“変化した”へつなげる設計
当社のチームビルディング研修では、単なるアクティビティで終わらせず、リーダーシップやコミュニケーションの理論と実践を組み合わせる設計を重視しています。
例えば以下のような工夫を加えます:
- リーダーシップへの気づき:グループ課題やゲームを通して、自然に「意思決定」「巻き込み」「支援」などの行動特性を振り返り、リーダーシップスタイルへの理解を深める。
- 心理的安全性の理解と浸透:メンバー同士が失敗や意見を共有するワークを通じて、心理的安全性の重要性を体感的に学ぶ。
- 共通言語としての理論導入:DiSC®やソーシャルスタイルなどのコミュニケーションスタイル理論を活用し、ワークショップ後も日常業務で使える“共通言語”をチーム内に残す。
参考:DiSC® - グローバルに通用する研修・アセスメント・映像教材|MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部
こうした構成により、参加者は「ただ楽しかった」で終わらず、日常のコミュニケーション行動やチーム運営に活かせる学びとして持ち帰ることができます。
実際、研修後のアンケートでは「普段の1on1で意識するようになった」「メンバーへの関わり方が変わった」といった声が多数寄せられています。
研究でも、チームビルディングは“感情・プロセス”への影響が特に強く、
「設計された内省・理論との接続」がある場合、行動変容・パフォーマンス向上への波及が確認されています。
効果測定とフォローアップの仕組み
当社の支援では、事後の“フォローアップ設計”を最初から組み込むことを重視しています。
具体的には:
- 行動宣言と振り返り会:ワークショップの最後に、各自が「明日から実践すること」を言語化し、約2週間後に短時間のオンライン振り返り会を実施。
- アンケート+フィードバックレポート:実施前後の「信頼感」「心理的安全性」「協働意識」を可視化して、チームの変化を共有。
- 上司・リーダー向けガイドの提供:リーダーが日常で“学びを支える”仕組みを整え、定着を促進。
このように、ワークショップを“起点”として行動変容を支援する仕組みを持たせることで、チームビルディングは一過性のエンタメから“組織開発プログラム”へと昇華します。
▶図2:チームビルディングを行動変化につなげる設計の流れ
設計時点で「理論×体験×行動宣言×フォローアップ」を一体で構想しましょう。
実践!チームビルディング7ステップ設計フレーム
実務で使える「7ステップ設計フレーム」を提示します。研修事務局や人事企画部でもすぐに活用できるように、具体手順と注意点を整理しました。
現状分析・目的定義
まず、現状のチーム状況を診断します。例として:
- 社内アンケートで「部門間連携」「心理的安全性」「知識共有頻度」を可視化
- リモート環境下での交流頻度・雑談機会の減少をヒアリング
目的定義では、「部門A・B間のナレッジ共有を月1回に増やす」「中途入社者の半年内離職率を10%減に」など、明確かつ測定可能な目標を設定します。こうした現状と目的を設計の起点にすることで、ワークショップの意味づけが高まります。
ワークショップ設計~振り返り計画
ワークショップ設計では以下を含めます:
- ロールプレイ・グループワーク・自己/他者理解ワークの組み合わせ
- オンサイト・オンライン両対応を想定
- 行動宣言を含む振り返りセッション(ワーク終了直後)
振り返り計画では、終了後「30日・90日・半年」のチェックポイントを設け、進捗と定着状況を確認します。設計時点でこのフォローを予定に入れておくことで、実施後の“放置”を防げます。
▶表2:チームビルディング設計7ステップ概要
ステップ | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
1. 現状把握 | アンケート・ヒアリングによる診断 | 定量+定性両方向で実施 |
2. 目的設定 | 測定可能な目標を設定 | SMART原則に則る |
3. 設計 | ワーク・場所・形式を決定 | オン/オフハイブリッド対応 |
4. 実施 | ワークショップ本体の運営 | ファシリテーターと記録体制を準備 |
5. 行動宣言 | メンバー自身の次の動きを宣言 | 個人・チーム単位で設計 |
6. フォローアップ | 進捗確認と支援策提供 | 30・90・180日視点で設定 |
7. 効果測定・改善 | 指標と振り返りで改善設計へ | アンケート・成果データを活用 |
限られた時間でも、まずは「現状把握」と「目的設定」を整理するだけで、チームビルディングの方向性がぐっと明確になります。
リモート&ハイブリッド環境での実践注意点
対面とリモートが混在する今、従来の「合宿型+懇親会」だけでは効果が頭打ちになることがあります。特に留意すべき3点を整理します。
非対面ならではの課題と解消策
オンライン・ハイブリッドで特に生まれやすい課題は以下のとおりです:
- オフラインならではの“偶発的な雑談”が欠如し、信頼醸成が遅れる。
- 気軽に発言しづらく、ハイブリッド参加者が疎外感を抱く可能性。
解消策としては、冒頭に「ブレイクアウトルーム+アイスブレイク」を必ず入れ、カメラON+リアルタイム投票・チャット活用などで全員参加を促します。
オンライン/対面ハイブリッド型の工夫
ハイブリッド設計で効果を出すためには、以下のポイントが有効です:
- オンサイト参加・リモート参加どちらでも同じ体験が可能な仕立てにする(例:リモート参加者用ワークキット+ファシリテーション)。
- “ハイブリッド用役割”を設定(進行役・リモートグループ支援役など)。
- フォローアップ時には、チャット・オンライン会議・社内SNSなど、定期的な非対面交流を設置。
こうした工夫により、リモート環境下でも関係性を積み重ねることができます。
▶図3:ハイブリッド方式のポイント
企画の際は必ず「リモート参加用役割」「オンライン専用アイスブレイク」を設計に入れましょう。
中途入社・多様なメンバーを巻き込む方法
中途入社者増加・世代多様化・職務多様化が進む現在、「既存メンバー向け」ではないチームビルディング設計が求められています。ここでは、多様な背景を持つメンバーを巻き込むための設計ポイントを紹介します。
オンボーディングとしてのチームビルディング活用
中途入社者やプロジェクト加入直後のメンバーに対して、早期からチームビルディングを位置づけると効果的です。例えば:
- 入社後1〜2カ月目に「自己紹介+業務背景共有+メンバーからのQ&A」を行う。
- 既存メンバーとの交流やペアワークを介し「チーム文化・価値観」を伝える。これにより、中途入社者が早期に“チームの一員感”を獲得し、離職抑止やオンボーディング加速につながります。
多様性を活かすワークのデザイン
多様な背景を持つメンバーがいるチームでは、「共通点探し」「背景共有」「多様性からの学び」をワークに入れることが有効です。設計のポイントとして:
- 多様な職種・世代・勤務地の混合チームに分ける。
- 「自分のバックグラウンド」「成功失敗体験」「期待するチーム像」を共有する。
- 多様性を前提に「異なる視点からの新しい発想」を促すテーマ(例:新規サービスの構想)を設計。
こうした設計によって、メンバー間の理解が深まり、協力を前提とした関係性が生まれます。
▶表3:多様性対応ワーク設計チェックリスト
設計項目 | 実務的ポイント |
|---|---|
チーム編成 | 職種・勤務地・勤務形態が混在するように工夫 |
ワークテーマ | 出身地・キャリア背景を素材に、共有+共創型テーマを設定 |
フィードバック設計 | 多様な視点からの学びを促すため、混成チームの成果共有を最終セッションに配置 |
中途入社者向け回と既存メンバー混成回を別途設け、「背景共有ワーク」を冒頭に実施しましょう。
まとめ
本コラムでは、現在の働き方・組織構造の変化を背景に、チームビルディングがなぜ重要か、どんな効果があるか、そして“ただ楽しいだけで終わらせず”成果につなげるための設計方法と実践ステップをご紹介しました。
ポイントを整理すると、①関係性・信頼、②役割・目標の明確化、③プロセス・連携改善という3つの効果を意識することが先決です。次に、一度きりのイベントにしないために、「目的設定→ワークショップ設計→行動宣言→フォローアップ→定着」という流れ(図2参照)を設けること、そしてリモート/ハイブリッドや中途入社が多様化する環境に対応したワーク設計が鍵となります。
実務としては、まずは「現状把握・目的設定」から着手し、設計7ステップ(表2参照)に沿って構築してみてください。
最後に、チームビルディングを「遊び」ではなく「組織力強化の戦略施策」として位置づけ、社内に設計・実行・フォロー体制を作ることが最大の鍵です。
MBK Wellnessの研修プログラム
FAQ
Q1:チームビルディングは一回で十分でしょうか?
A1:一回だけでも関係づくりや気づきを促せますが、「感情・プロセス」アウトカムへの効果が最も出やすく、長期的な「パフォーマンス・成果」につなげるには継続的なフォローや振り返りが重要です。
Q2:オンラインだけでチームビルディングは可能ですか?
A2:可能です。ただし、対面型と比べて“偶発的雑談”や非言語コミュニケーションが減るため、リモート特有の設計(ブレイクアウト、雑談時間、ファシリテーター支援)を入れることが効果を高める鍵です。
Q3:どのくらいの規模(人数)で実施すべきでしょうか?
A3:5人程度の1チームから、100名を超える大人数まで広く対応可能です。人数が多い場合には、アクティビティによって中グループ・小グループに分けたり、サブファシリテーターを置く設計がおすすめです。
Q4:費用対効果を示すにはどうしたらよいですか?
A4:目的に応じたKPI(例:部門間連携回数/プロジェクト完了時間/離職率)を設け、実施前後でアンケート・定量データを比較します。ワークショップ終了から30日・90日・180日とフォローして「変化の軌跡」を可視化しましょう。
Q5:中途入社者だけで別セッションを設けるべきでしょうか?
A5:既存メンバー・中途入社者混合で実施することで「異なるバックグラウンドの交流」「多様性からの学び」が生まれやすくなります。一方、入社直後向けにはオンボーディングとしての簡易導入回も検討すると効果的です。
参照・出典
Pollack, J./Matous, P.(2019)
「チームビルディング介入がプロジェクトチーム内コミュニケーションに与える影響の検証 ―社会ネットワーク分析による実証研究―」
『International Journal of Project Management』第37巻3号, pp.473–484.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786318307609
McEwan, D./Beauchamp, M. R./Harvey, S.(2017)
「チームワーク研修がチーム行動および成果に及ぼす効果 ―統制介入を用いたメタ分析―」
『PLoS ONE』, 2017年.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169604
Kwon, S. H.(2024)
「チームビルディング介入がチーム凝集性に与える影響 ―スポーツチームを対象としたメタ分析研究―」
『Frontiers in Psychology』第15巻, 2024年.
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1353944/full
Akinade, M. E./Obiekwe, O.(2023)
「チームビルディングが組織パフォーマンスに与える影響 ―理論的レビュー―」
『International Journal of Economics and Business Management』第9巻2号, 2023年.
https://www.iiardjournals.org/get/IJEBM/VOL.%209%20NO.%202%202023/IMPACT%20OF%20TEAM%20BUILDING.pdf
Google re:Work(n.d.)
「効果的なチームとは何か ―チームの有効性を理解する―」
Google re:Work公式ガイド.
https://rework.withgoogle.com/intl/jp/guides/understanding-team-effectiveness