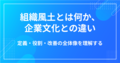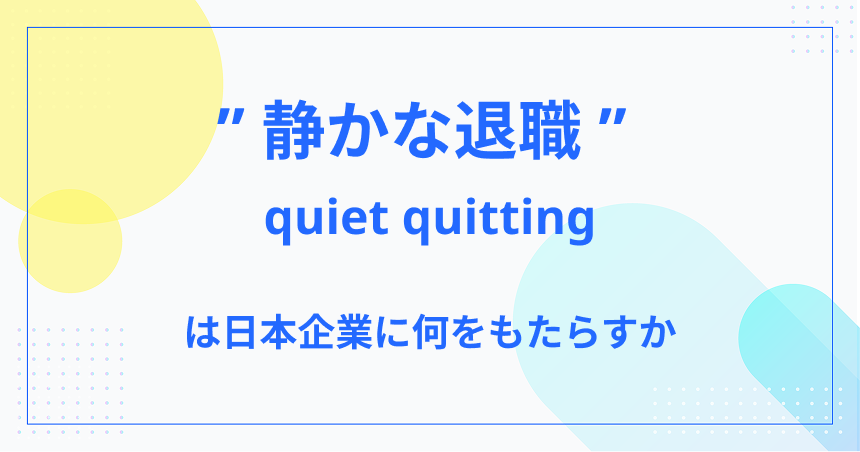
“静かな退職(quiet quitting)”は日本企業に何をもたらすか
近年、従業員が会社を辞めずに“契約上の義務は果たすが、それ以上の関与は控える”態度を取る「静かな退職(quiet quitting)」が、日本でも可視化されています。2024年の国内調査では、正社員の約44.5%が該当する働き方を自認したという結果も示されました(調査主体:マイナビ、記事: nippon.com、2025年5月12日)。
本稿は上場企業の人事・経営企画向けに、①定義と日本的文脈、②経営者視点のリスクと機会、③従業員視点の意味、④育成・評価制度の見直し、⑤人口動態・AI時代の戦略、⑥すぐ使える実務チェックリストの6本立てで、静かな退職を“撲滅対象”から“組織を更新するシグナル”へと捉え直す視座を提供します。
目次[非表示]
- 1.静かな退職とは何か――定義と日本的文脈
- 1.1.用語の定義と学術的な整理
- 1.2.日本での実態と背景
- 1.3.実務への落とし込み
- 2.経営者視点 ――放置コストと見落としがちな機会
- 3.従業員視点 ――防衛と自律、価値観の転換
- 3.1.燃え尽きを避ける “ 線引き ” という合理
- 3.2.自律の回復と “ 余白 ” の戦略的活用
- 3.3.実務への落とし込み
- 4.人材育成・評価制度の再設計ポイント
- 5.人口動態・ AI時代に “静かな退職 ”を活かす人事戦略
- 6.実務チェックリスト ――今すぐやること/やめること
- 6.1.今すぐやること( 8 項目)
- 6.2.すぐやめること( 8 項目)
- 6.3.実務への落とし込み
- 7.まとめ
- 8.FAQ
- 9.参照・出典
静かな退職とは何か――定義と日本的文脈
議論の出発点は「辞職ではない」という正確な理解です。海外起源の言葉であるがゆえに、概念のズレが意思決定を誤らせます。本節では定義と日本的文脈を揃えます。
用語の定義と学術的な整理
静かな退職は、従業員が“上乗せの役割・努力(残業、進んでの追加責務、社外時間の献身)”を抑制し、職務記述書や契約の範囲に仕事を限定する態度を指します。最新の計量研究では、静かな退職は「時間(Time)」「努力(Effort)」の二次元で測定可能とされ、いずれも公式に定められた職務範囲を超えて仕事を引き受けることを回避する点が特徴的とされています。エンゲージメント低下と密接に関わる概念として扱われことも多く、「怠慢だ」と感情論で切り捨てるのではなく、制度設計において向き合うべき課題と言えます。
日本での実態と背景
日本では「在籍しながらも仕事へのコミットメントを最低限にとどめる」態度が、特に20–40代で広がりを見せています。2024年11月調査(マイナビ、n=3,000)では、44.5%が静かな退職に該当する働き方と回答。仕事量と報酬の釣り合い、評価の不透明さ、キャリア上昇の期待値低下などが背景として挙げられました。国際比較の観点でも、日本の「熱意ある従業員」比率は6%と世界最低水準で、構造的なエンゲージメントの弱さが下地にあります(Gallup “State of the Global Workplace 2024”)。これらは、個人の怠慢ではなく“制度・関係性のフィット不全”という見立てを人事や経営に対して問題提起していると捉えられます。
実務への落とし込み
自社の“静かな退職”兆候を明確に定義、可視化し、定期的にモニタリングしていきましょう。
▶図1:静かな退職の典型的なサイン(例)
項目 | 内容 |
|---|---|
自発的改善提案の減少 | プロジェクト発案、改善活動に手を挙げない |
残業・休日出勤の拒否 | 定時帰社を堅持し、サービス残業を避ける |
昇進・異動・キャリア意欲の低下 | 昇格・兼務・転勤などに関心を示さない |
会議・懇親会での発言減少 | 「まあ、いいか」と受動的応対/出席頻度低下 |
経営者視点 ――放置コストと見落としがちな機会
“静かな退職=悪”と断ずるだけでは、真因は見えてこず、改善の機会も逃します。本節は、経営寄りの損益インパクトと戦略機会の両面で問題を捉え直します。
放置のコストは “ 改善余地の蒸発 ”
静かな退職の直接的な損失は“現状維持”ではなく“改善余地の蒸発”です。改善提案・越境協働・暗黙知の共有といった余剰行動(extra-role)が先細れば、新規事業や品質向上の芽は摘まれます。さらに、管理職自身のエンゲージメント低下(2024年、世界で27%に低下との報道)も相まって、チーム内での対話密度が落ち、人事上の様々なリスクの兆候が見過ごされがちになります。エンゲージメントが低いほど離職・引き抜きリスクや人的資本投資の回収遅延が高まる点も、CFO視点では無視できません。
見落としがちな機会 ――“ 持続可能な関与モデル ” 設計
他方で、静かな退職は“過度な滞留期待”すなわち、社員が会社に長く・全面的にコミットし続けるのが当然だと、経営や上司が無意識に期待している状態に対する一種の警告でもあります。静かな退職のシグナルを捉え、評価軸を「時間・儀式」から「価値創出・成果・行動」に移すことで、燃え尽きと不公平感を同時に抑制できます。国際的にも「年功・一律モデルから、成果ベースで柔軟に」という方向性が推奨されており(OECD)、中期ではスキル・職務基準の透明化が採用効率と内部流動性を高めます。静かな退職は“やる気の欠如”というより“制度の矛盾の可視化”。これを機に、業務設計・報酬・昇格・学習機会の整合性を再構築することが、企業価値のレバレッジになります。
実務への落とし込み
「余剰行動の設計」をKPI化。“何に越境行動を求め、どう評価するか”を制度文書に書き起こす。
従業員視点 ――防衛と自律、価値観の転換
静かな退職は、怠慢でも反抗でもなく“自分を守る線引き”と“選択の再配分”という側面があります。従業員のロジックを理解することが介入の第一歩です。
燃え尽きを避ける “ 線引き ” という合理
過大な責務・不透明な評価・時間で測られる献身は、燃え尽きを誘発します。従業員が“最低限の約束”に仕事を戻すのは、健康と生活の維持、キャリアの長期最適化を狙う戦略でもあります。エンゲージメントが世界的に鈍化する中(Gallupレポートの報道)、マネジャーによる定期的で質の高い1on1とフィードバック、この2点の欠如は静かな退職へと転がり落ちる「下り坂」になりがちです。
日本の多くの会社では、“どれだけ頑張っているか”が正しく評価に反映されにくい仕組みがまだ残っています。そのため、社員が“いくら頑張っても報われない”“評価される基準が分からない”と感じると、『ならば、言われたことだけしておこう』と関与を減らす――つまり静かな退職の状態になるのは、むしろ合理的な判断です。
自律の回復と “ 余白 ” の戦略的活用
もう一つの軸は“余白の再配分”です。AIの台頭で定型タスクの価値が圧縮されるほど、個人は創造・学習・副業・家族・地域等へ時間配分を見直します。内閣府の整理でも、生成AIはタスク生産性を10–56%向上させ得るとの知見が紹介され、“人が担うべき仕事の範囲”が再定義されつつあります。
従業員が「会社外の学習・経験」を重ねるのは「忠義に反する裏切り行為」ではなく、「人的資本の拡張行為」とポジティブに解釈したいところです。企業側はこのような余白を“越境学習の供給網”として設計することができれば、企業価値の向上に貢献してくれるはずです。
実務への落とし込み
“余白の活用計画”を人事施策に組み込む。学び・副業・地域活動の承認プロセスと成果還元ルールを設ける。
人材育成・評価制度の再設計ポイント
育成・評価は“静かな退職”を増幅も抑制もします。本節は「主張→根拠→手順→注意点」で、設計の勘所を具体化します。
主張 ――“ 時間 ” から “ 価値 ” へ、評価軸を置き換える
残業や長時間労働が評価に影響する限り、従業員は“見せ方”を最適化し、評価されない余剰行動は萎みます。求めるのは、成果(アウトプット)・再現可能な行動基準・職務スキルの三点セット。ジョブ定義と成果基準を明文化し、越境行動(例:改善提案、横断協働、知識共有)を評価項目として組み込むことで、余剰行動の“設計化”が可能になります。
学術的にも静かな退職は「上乗せ努力の抑制」で測定されるため、そもそも“上乗せ”の範囲を制度で定義し、期待値と報酬の対応関係を透明化することが要です。
手順 ―― 対話と学習の “ 連続体 ” で関与を戻す
まず、四半期ごとにエンゲージメント・パルスサーベイを実施し、部門ごとの“Time/ Effort”偏差を可視化。次に、マネジャー育成(頻度×質の1on1、コーチ型対話)を重点投資し、越境行動の成功事例を社内で流通させます。リスキリング機会は、選べる・短い・仕事に直結、の3条件で設計し、学習と評価を接続(完了ではなく“活用”に点を置く)。最後に、報酬・称賛・昇格のシグナルを揃え、余剰行動に“見返り”があると明確化します。これらは世界的に低下傾向にあるエンゲージメントを押し戻す“地味ではあるが効く”筋道です。
実務への落とし込み
評価票を刷新し「越境行動の定義・例・配点」を明文化。完了時期と運用責任者を指名する。
▶図2:育成・評価制度再設計のチェックポイント
項目 | チェック内容 |
|---|---|
評価軸 | “時間・残業”から“価値創出・アウトプット”へ変える |
キャリアパスの多様性 | 直線昇進だけでなく「専門職/プロフェッショナル職」も設計 |
自己選択機会 | 副業・兼業・学び直しなどを選択肢として提示 |
意味・目的の共有 | 仕事の“社会的価値”・“個人の成長”に関する対話設計 |
人口動態・ AI時代に “静かな退職 ”を活かす人事戦略
労働力減少と技術進展は不可逆な流れです。マクロ環境を踏まえた時、“静かな退職”は脅威だけでなく「持続可能な人と組織の関係」を再設計するチャンスになり得ます。
人口動態 ――“ フル稼働モデル ” の限界
日本の人口は減少トレンドが継続し、老年扶養比率はOECDでも最上位クラスへ上昇する見通しです。若年・生産年齢人口の縮小は、採用難・人件費上昇・熟練喪失の同時進行を意味します。採りにくい時代に“燃え尽き”で手放すコストは増大。だからこそ、人事は“ほどよい関与で長く在籍できる”設計に舵を切る必要があります。
AI の波 ――“ 人が担うべき仕事の範囲 ” の再定義
生成AIの導入は、タスクレベルで10–56%の生産性向上をもたらし得ると整理されています。これは“人の手が必要な範囲”の縮小と、創造・判断・関係調整への人的シフトを意味します。人事は、フル稼働を常時強いるのではなく、余白を学習・共創に振り向ける「適度稼働+高付加価値化」へ。社外学習・副業・越境を“裏切り”と見なす文化から、“資産形成”として制度化する文化へ転地することで、AI時代のレジリエンスが高まります。
実務への落とし込み
労働供給の制約前提で「適度稼働+高付加価値」KPIを導入。学習・越境の“滞在インセンティブ”化を。
実務チェックリスト ――今すぐやること/やめること
最後に、現場で実践できる具体策をまとめます。四半期で回せる粒度に分解し、「やること」「やめること」を明確に示します。
今すぐやること( 8 項目)
- 月次サーベイで Time/Effort の偏差を可視化。
- マネジャーの 1on1 頻度・質の KPI 化。
- 職務記述書・成果基準の明文化。
- 越境行動(改善・横断・知の共有)を評価項目に追加。
- 外部学習・副業の承認と成果還流ルール化。
- 表彰は “ 成果+再現可能な行動 ” に限定。
- 異動・公募・社内副業で内部流動性を上げる。
- 役員・人事・現場の三者で制度の PDCA 会議体を設置。これらは低いエンゲージメントの立て直しに有効です。
すぐやめること( 8 項目)
- 残業や滞在時間を暗黙に評価。
- 一律の “ がんばり ” を要求。
- 「やる気がない」のレッテル貼り。
- イベント型モチベ施策の乱発。
- 評価・報酬・称賛のシグナル不一致。
- マネジャー研修を “ 座学だけ ” で終わらせる。
- 職務・成果基準の曖昧なまま異動・昇格を強行。
- 外部学習・副業の全面禁止。これらは離脱や “ 静かな退職 ” を助長します。人口・ AI の構造変化の中で、旧来の一斉モデルは “ 制度ドリフト ” を起こしやすい点に注意を。
実務への落とし込み
チェックリストを四半期レビューに組み込み、担当・期限・指標を明記して運用を開始する。
まとめ
静かな退職は“退職”ではなく、上乗せ行動の抑制=関与の線引きです。日本では該当者が4割超というデータも出つつ、世界最低水準のエンゲージメントがそれを下支えします。放置すれば、改善余地が蒸発し、人材の滞在価値は逓減。一方で、評価軸を価値創出へ移し、余白を学習・共創に転換すれば、燃え尽きを抑えつつ“持続的な関与”が設計できます。人口減少とAIの波が確実な今こそ、「適度稼働+高付加価値」の人事設計へ。静かな退職を“異常値”として罰するのではなく、“制度アップデートの合図”として受け止め、今日からチェックリストを回し始めましょう。
FAQ
Q1 :静かな退職は “ 怠け ” と何が違いますか?
A:辞職や職務放棄ではなく、契約・職務記述書の範囲に仕事を限定し、上乗せの時間・努力を抑える態度です。計量研究では「時間」「努力」の二因子で測定され、組織市民行動の縮小として表れます。
Q2 :日本での広がりは本当に大きいのですか?
A:2024年11月の国内調査(マイナビ、n=3,000)を報じた記事では、44.5%が静かな退職に該当する働き方を自認。世代横断で確認されています。絶対値は調査枠に依存しますが、傾向把握には有効です。
Q3 :企業にとって最大のリスクは?
A:新規事業や改善を生む“余剰行動”の縮小です。また管理職の関与低下は、対話・ケアの希薄化を通じて離職・品質低下を誘発します。定期的で質の高い1on1が対策の要になります。
Q4 :マクロ環境と関係がありますか?
A:あります。人口減少・高齢化で労働供給は細り、フル稼働前提は非現実的に。OECDの分析でも年功・一律から成果ベース(柔軟・多様)への転換が有効と示唆されます。
Q5 : AI 普及で静かな退職は増えますか?
A:AIは定型タスクの生産性を押し上げ、人が担う範囲を“創造・判断・関係”へ押し上げます。余白を学習・共創に振り向ける設計をすれば、静かな退職の“線引き”はむしろ組織力の土台になります。
参照・出典
- nippon.com / Japan Data 「 Quiet Quitting on the Rise in Japan 」( 2025 )
https://www.nippon.com/en/japan-data/h02392/ - Gallup 「 State of the Global Workplace 2024 (プレス発表・日本のエンゲージメント 6 %)」共同通信 PR ワイヤー掲載( 2024 年 6 月 12 日)
https://kyodonewsprwire.jp/release/202406122054 - PLOS ONE ( Wiley ) “A multidimensional quiet quitting scale: Development and test.” ( 2025 )
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0317624 - Auburn University“Quiet Quitting: A Conceptualization, Scale Development and Validation” (修士論文、 2024 )
https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/9497/JRB%20MS%20Thesis%202024.pdf - OECD“Working Better with Age: Japan” (老年扶養比率の見通し、 2024 更新ページ)
https://www.oecd.org/en/publications/working-better-with-age-japan_9789264201996-en.html - 内閣府『世界経済の潮流 2024Ⅰ :第 1 章 AI で変わる労働市場』( 2024 )
https://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sh24-01/s1_24_1_0.html - 総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024 年平均結果の概要」( 2025 年公表 PDF )
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/gaiyou.pdf