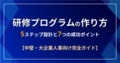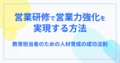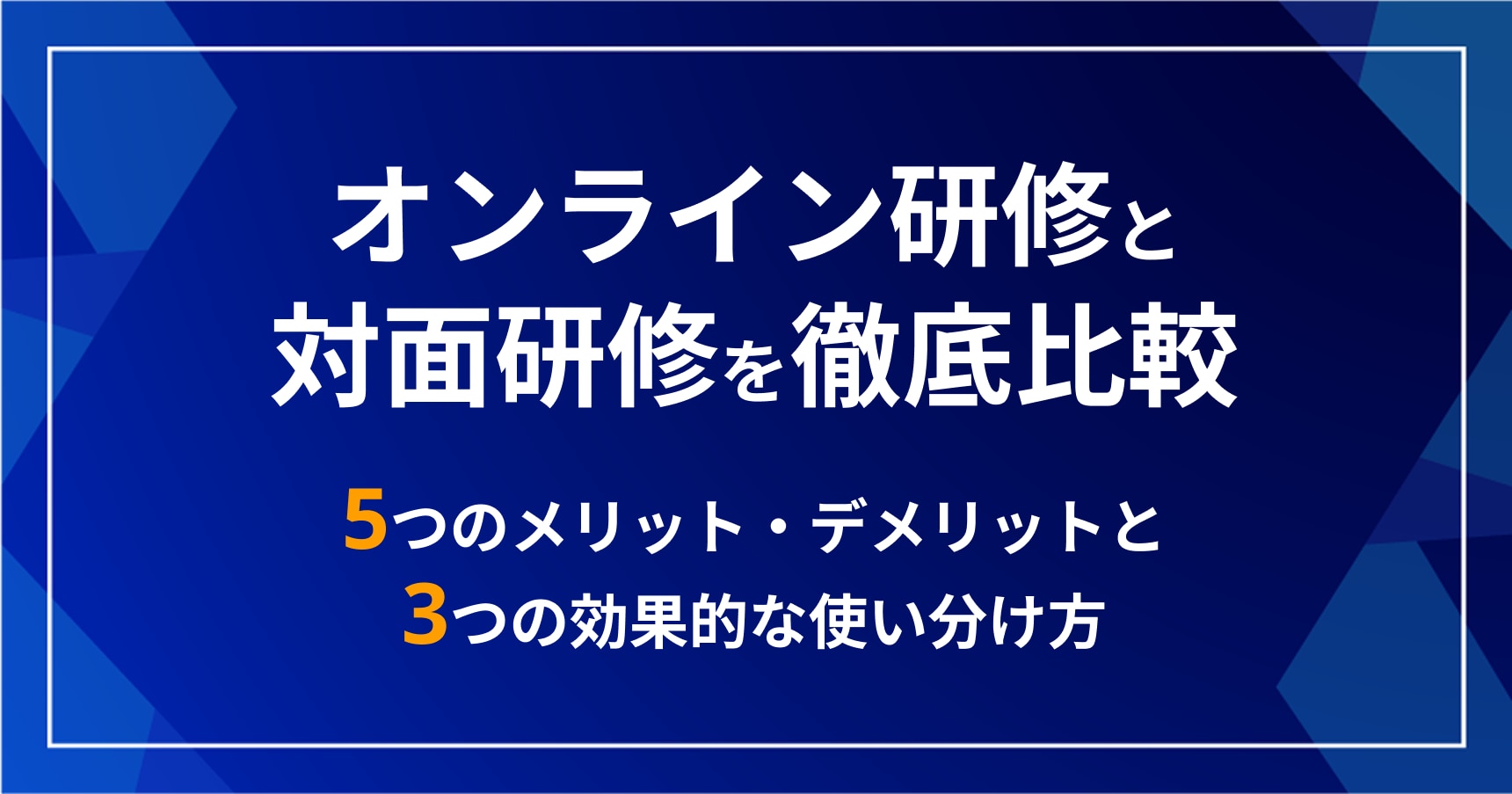
オンライン研修と対面研修を徹底比較|5つのメリット・デメリットと3つの効果的な使い分け方
はじめに|社員研修の方法論を選ぶ前に知っておきたいこと
社員研修は、企業の人材育成や組織力向上に欠かせない取り組みです。研修の目的は多岐にわたりますが、大きく分けると①知識習得型、②スキル習得型、③マインド醸成型の3つに分類できます。そして、その目的や対象者に応じて、研修方法論を選定することが重要です。
サイコム・ブレインズは30年に亘って大手企業を中心に社員教育、研修設計をサポートしておりますが弊社の経験では、人事部員や社員教育担当者、研修事務局の方は、研修方法選びにおいて次のような課題を抱えることが多いようです。
- 限られた予算で最大の効果を出したい
- 全国・海外拠点の社員をどう効率よく研修に参加させるか
- 現場の業務負担を軽減しながら研修を実施したい
- 研修の効果をどのように測定・報告するか
研修方法の選定は、単なる運営手段の違いではなく、企業の人材育成戦略そのものに影響を与える重要な判断であると、弊社では考えます。
本記事では、オンライン研修と対面集合研修のメリット・デメリットを5項目で整理し、効果的な使い分け・組み合わせの3つのアプローチをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.はじめに|社員研修の方法論を選ぶ前に知っておきたいこと
- 2.オンライン研修の3つのメリットと5つのデメリット
- 2.1.オンライン研修の概要と主な実施方法
- 2.2.3つのメリット
- 2.3.5つのデメリット *対面集合研修との比較において
- 3.効果を高めるオンライン研修の5つの工夫
- 4.対面集合研修の3つのメリットと7つのデメリット
- 4.1.集合研修の概要と実施形式
- 4.2.3つのメリット
- 4.3.7つのデメリット
- 5.効果を最大化する対面集合研修の6つの工夫
- 5.1.利点(3点)
- 5.2.課題と解決策(3点)
- 6.ハイブリッド研修という選択肢
- 6.1.ハイブリッド研修の定義と実施形態
- 6.2.3つのメリット
- 6.3.3つの課題と解決策
- 7.目的別・対象者別の効果的な使い分け3パターン
- 7.1.目的別の適切な研修手法
- 7.2.対象者別の使い分け、組み合わせ例
- 8.研修効果を測定する3つの方法
- 9.まとめ|社員教育を強化する4種類の学習形態
オンライン研修の3つのメリットと5つのデメリット
オンライン研修の概要と主な実施方法
オンライン研修は、インターネットを介して行う研修形態です。ライブ配信型(ZoomやTeamsなどのツールを使用)、録画配信型、eラーニング形式などがあり、学習管理システム(LMS)と連携させて実施するケースも増えています。
3つのメリット
- 時間・場所の柔軟性
社員は自宅や職場など、どこからでも参加可能。移動時間や交通費が不要です。さらにe-ラーニングであれば、自身の理解度に合わせてマイペースで学べます。 - コスト削減
会場費・宿泊費・交通費がかからず、大規模な全国研修でも低コストで実施可能。 - 参加ハードルの低さ
短時間での研修設定や録画視聴による学習が可能。
5つのデメリット *対面集合研修との比較において
- 集中力が続きにくい
- 通信環境の良し悪しに、学習効果が左右されることがある
- 研修へのコミットメントを強制できない(カメラオフで内職することも可能)
- 講師や受講者同士の交流機会が持ちにくい(たまたま隣に座った人と雑談することがない)
- 実技や体験型研修の場合、期待する効果に限界がある(ノンバーバルな情報量が少ないので、“場”の雰囲気やメンバーの熱量、それらが織り成す相乗効果が得られにくい)
効果を高めるオンライン研修の5つの工夫
- 双方向コミュニケーション(チャット、投票、ブレイクアウトルーム)を組み込む
- 堅牢な通信環境、集中できる学習空間を確保する(確保させる)、カメラオンでの研修参加を義務付ける
- ブレイクアウトルームを活用しながら、アイスブレイクや「雑談タイム」を休憩時間などに組み込む
- 事前課題・インターバル課題・事後課題を設定し、学びを定着させる
- 研修後のアンケートで理解度や満足度を測定し改善に活かす
対面集合研修の3つのメリットと7つのデメリット
集合研修の概要と実施形式
対面集合研修は、参加者が一つの会場に集まり、講師の指導のもとで行われます。会議室、研修施設、ホテル会議室などが一般的な会場です。
3つのメリット
- 交流促進
休憩時間やグループワークを通じて自然な人間関係構築が促進されやすい。 - 臨場感と集中度
講師の熱量や空気感が伝わりやすく、学びへの没入感が高まる。 - 実技・ロールプレイに向いている
接客、営業ロールプレイ、プレゼン練習など体験型研修に最適。
7つのデメリット
- 会場費・交通費・宿泊費がかかる
- 全国からの参加には時間的・経済的負担が大きい
- 日程調整が難しく、参加できない社員が出やすい。また、働き方に制約がある社員(育児や介護に携わる)は参加できないことが多い。
- 比較的拘束時間が長いので、「日常業務に支障が出る」との不満が上がりやすい
- 時間的・経済的負担を回収するために、「詰め込み型」の研修になりがち。結果として、学習効果が限定的になる
- 社員各人の個別の課題感や理解度に対応しにくい(一律的な学習になりがち)
- 非日常的な学習なため、日常業務とのつながりがイメージされにくい。学習内容が日常業務に活かされにくい(意識改革や行動変容につながらない)
効果を最大化する対面集合研修の6つの工夫
- 事前に目的とゴールを共有しておく
- 業務の一環であること、戦略遂行の方法論としての研修であることを説く
- 受講者参加型のアクティビティを多く取り入れる
- 研修内のワークと日常業務との関連性を強化する(実践型ワークにする)
- 知識やスキルのインプットを他の手段(e-ラーニングやオンライン研修)に置き換え、対面集合研修ならではの期待効果(アウトプットの反復練習)を最大化させる
- 研修後のフォローアップ研修やオンライン補足学習を実施
利点(3点)
- オンラインの柔軟性と対面の交流効果を両立
- コスト削減と効果の最大化を両立
- 多様な働き方(リモート・オフィス)に対応
課題と解決策(3点)
- 技術的トラブル防止:事前リハーサルを徹底
- 体験格差をなくす:同一教材・同一講師を活用
- 学びの定着:オンライン・対面の両方でフォローアップ実施
ハイブリッド研修という選択肢
ハイブリッド研修の定義と実施形態
ハイブリッド研修は、オンラインと対面研修を組み合わせて両者の「おいしいとこどり」を狙う形態です。例えば、基礎知識はe-ラーニングやオンライン研修で事前学習し、応用や実技は対面で行う方式などがあります。
ハイブリッド研修は合理的であり、今後ますます活用されることが期待されます。
3つのメリット
- オンラインの柔軟性と対面の交流効果を両立
- 研修全体のコストを抑えつつ効果を高められる
- 多様な働き方に対応可能
3つの課題と解決策
- 技術的トラブル防止のため事前リハーサルを徹底
- オンライン・対面での受講体験格差をなくす工夫(同じ教材・同じ講師)
- フォローアップをオンライン・対面の両形態で実施し、学びを定着させる
目的別・対象者別の効果的な使い分け3パターン
目的別の適切な研修手法
- 知識習得型:オンライン研修(効率重視)
- スキル習得型:対面研修(実践重視)
- マインド醸成型:対面またはハイブリッド(共感・交流重視)
対象者別の使い分け、組み合わせ例
対象者 | 推奨形態 | 理由 |
新入社員 | 対面+オンライン | 仲間意識醸成と基礎知識習得の両立 |
中堅社員 | 短期対面+オンライン | 実務知識更新と効率化 |
管理職 | ハイブリッド | 戦略思考研修とケーススタディの両立 |
研修効果を測定する3つの方法
- 事後テストで理解度を測定
- 行動変容アンケートで実務適用度を確認
- KPI連動評価で営業成績・顧客満足度との関連を検証
まとめ|社員教育を強化する4種類の学習形態
社員研修は、単一の方法論で完結させるよりも、目的・対象・内容に応じてオンライン研修と対面集合研修を組み合わせることが効果的です。
- オンライン研修:効率的かつ低コストで知識習得
- 対面集合研修:交流・体験型学習に強み
- ハイブリッド研修:双方の利点を活かす戦略的選択肢
研修企画の段階から、目的別の適材適所な使い分けと、研修効果測定の仕組みを設計することで、企業の人材育成の質とスピードは大きく向上します。
サイコム・ブレインズでは大別すると、以下4種類の学習形態を用意しています。顧客企業が抱える育成課題や学習の狙い、目的に応じて、最適な学習方法の使い分け、組み合わせをご提案いたします。
●社員が自身の興味関心、課題感に沿って自己啓発できる「動画ライブラリ」
●内定者から役員まで、各レイヤーの人材要件に基づく能力要件を身に付けるための独学教材「コースウエア」
●顧客企業の個別課題に応えるカスタマイズ研修(オンラインおよび対面集合研修)
●映像学習とオンラインワークショップ、学習プラットフォーム「ビジネスマスターズ」上での学習者同士の学び合いの3要素を組み合わせた「まなラン」