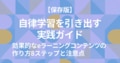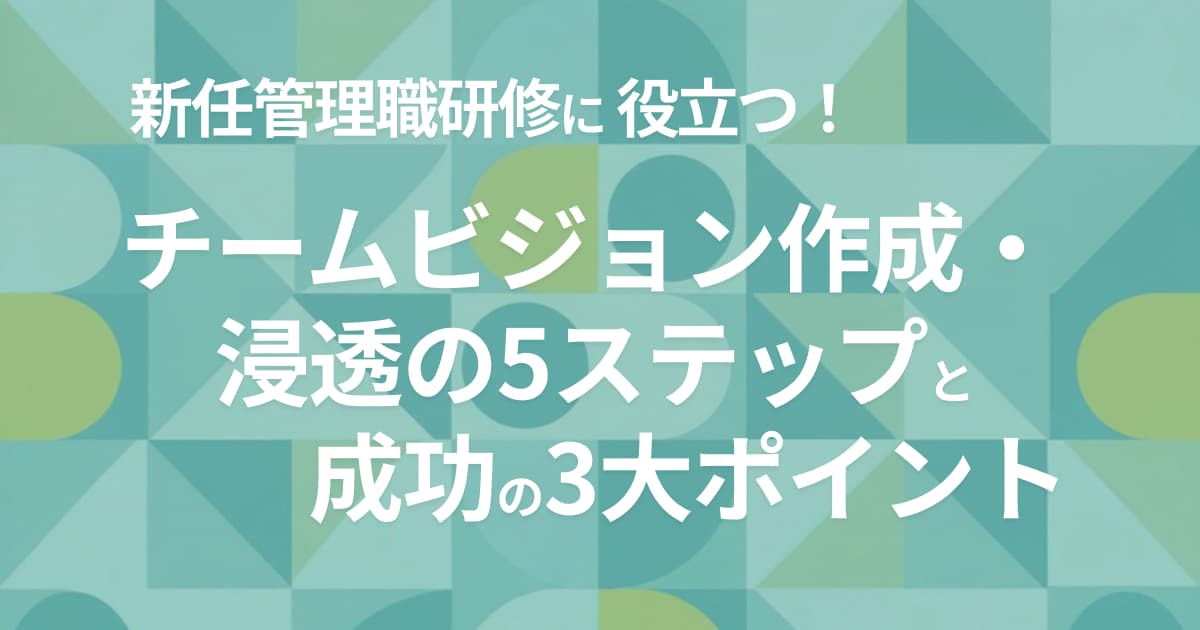
新任管理職研修に役立つ!チームビジョン作成・浸透の5ステップと成功の3大ポイント
なぜ人事部門が新任管理職に「チームビジョン」を学ばせるべきなのか
大企業の人事部門・研修企画担当が新任管理職向けに研修を設計する際、重要なテーマの一つが「チームビジョン」です。
なぜならば、これまでプレイヤーとして成果を上げてきた人材も、管理職になると「チーム全体の方向性を示す」ことが初めての経験になるからです。
ビジョンとは単なるスローガンではなく、未来像や価値観を言語化したものです。 共有されたチームビジョンがあることで、メンバーは日々の業務に意義を見出し、迷いなく行動できます。
特に新任管理職には、最初の100日間でビジョンを言語化・共有する力が求められます。着任から100日の間に一定以上の成果を上げることが、その後のキャリアに好影響を与えるとする向きもあるからです。人事部門が新任管理職研修の中でこのテーマを扱うことは、組織のパフォーマンス向上の観点でも、将来の上級管理職、役員候補者などの「タレントプール」を構築する上でも欠かせません。
目次[非表示]
- 1.チームビジョンの定義と役割(3つの効果)
- 2.ビジョン不在による、チームマネジメントへの3つのリスク
- 3.チームビジョン作成の5ステップ
- 3.1.組織目標とチーム目標の整合性を取る
- 3.2.チームの強み・課題を洗い出す
- 3.3.メンバーの声を反映する
- 3.4.新任管理職が陥りやすい注意点を回避
- 3.5.数値目標と結びつける
- 4.ビジョンを浸透させる3つの方法
- 4.1.初期共有のタイミングと場の設定
- 4.2.エンゲージメントを高めるコミュニケーション術
- 4.3.浸透度を測る方法
- 5.成功するチームビジョン浸透のための3大管理職スキル
- 5.1.チームビルディング
- 5.2.モチベーションマネジメント
- 5.3.メンバーの主体性を引き出すコーチングスキル
- 6.まとめ – ビジョンで組織の一体感を高める
チームビジョンの定義と役割(3つの効果)
チームビジョンは以下の3つの役割を持ちます。
役割 | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
コンパス | チームの進むべき方向を示す | 優先順位が明確になる |
意思決定基準 | 判断や行動の拠り所 | 無駄な迷いを減らす |
一体感形成 | 共通の価値観を共有 | チームの結束が強まる |
人事部門が研修でこの枠組みを提示することで、新任管理職は「ビジョン=抽象的なお題目」ではなく「実務を支える仕組み」と理解できます。
ビジョン不在による、チームマネジメントへの3つのリスク
ビジョンが浸透しているチームは、自律的に動けます。現場で生じる様々な意思決定事案について、ビジョンに照らして即断できるからです。そのため、管理職は戦略判断に時間を割けます。
逆にビジョンが不在だと以下のリスクがあります。
- 「我々は何を重視するか」という尺度が統一されていないため、メンバー間で優先順位がバラバラになる
- 「我々は何者か、何を成すための存在か」というアイデンティティが確立されないため、モチベーションが短期的成果に依存する(安定しない)
- 「ビジョンに基づく意思決定」が権限移譲されていないため、都度上司にお伺いを立てる必要があり、意思決定スピードが遅れる
研修企画の観点では、これらリスクを「ケース教材」として提示すると、受講者に腹落ちしやすくなります。
チームビジョン作成の5ステップ
- 組織目標とチーム目標の整合性を取る
- チームの強み・課題を洗い出す
- メンバーの声を反映する
- 新任管理職が陥りやすい注意点を回避
- 数値目標と結びつける
研修内容を作成する際には、上記5つのステップを研修前の準備ワーク、研修内容そのもの、そして研修後の現場実践に落とし込むことが重要です。
以下、上記5つのステップを簡易的に解説します。
組織目標とチーム目標の整合性を取る
まずは、会社や部門全体のビジョン・戦略を理解することが重要です。チームビジョンは、上位組織の大きな方向性から逸脱してはいけません。
例:
- 組織ビジョン:「顧客の課題を最速で解決するパートナーになる」
- チームビジョン:「顧客の声を即日フィードバックし、最速改善を実現するチームになる」
チームの強み・課題を洗い出す
次に、SWOT分析やメンバーへのヒアリングを通じて、チームの現状を客観的に把握しましょう。強みを活かし、弱みを克服する方向性をビジョンに反映することができれば、メンバーに対する説得力が増します。
メンバーの声を反映する
自チームのビジョン作成にあたっては、当然、新任管理職の想いや価値観が込められるものですし、そうあるべきです。とはいえ、新任管理職が一方的にビジョンを決めると、メンバーは「押し付けられた」と感じがちです。
したがって、ビジョンの作成段階からメンバーに積極的に意見を求め、「自分たちで作った」という当事者意識を持たせることが浸透の第一歩です。
このとき、心理的安全性の高い環境づくりが確保されていると、メンバーは安心して意見を出しやすくなります。
また、メンバーと対話する際は、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見、事実に基づかない思い込み)を排除することも重要です。
新任管理職が陥りやすい注意点を回避
- 抽象的すぎるビジョン(例:「みんなで頑張る」)
- 長すぎて覚えられないビジョン
- 具体性や測定可能性が欠けるビジョン
数値目標と結びつける
ビジョンが実現に向かっているのか、どの程度向かっているのかが不明瞭だと、メンバーのモチベーションは維持できません。したがって、ビジョンと日常業務を紐づけて、実現度や貢献度を評価できる指標を設定することが重要かつ有効です。
その指標をチームやメンバー個々人の数値目標とすることで、望ましい行動を促進することができます。
ビジョンを浸透させる3つの方法
- 初期共有のタイミング設定
- エンゲージメントを高める日常的コミュニケーション
- 浸透度を測る仕組み化
研修を一過性のイベントで終わらせずに、本来の目的を達成するためには、研修後のフォローアップが重要です。
以下、研修事務局がフォローアップしたい、上記4つの方法を簡易的に解説します。
初期共有のタイミングと場の設定
ビジョンは、年度初めや新プロジェクト開始時など「区切りの良いタイミング」や「仕事の(再)出発時点」で発表するとよいでしょう。メンバーの心を統合するのに最も効果的なタイミングだからです。
その際、キックオフミーティングを設定し、背景や作成プロセスも併せて、丁寧に説明しましょう。また、ビジョンに対するメンバーの意見も引き出し、全員で対話することで、納得感や理解度が高まります。
このとき新任管理職に求められるのが、ファシリテーションスキルです。
エンゲージメントを高めるコミュニケーション術
加えて、日常的にビジョンについて、コミュニケートする機会や場を、意図的に設定していくことも重要です。
- 定例会議でビジョン達成状況を共有
- ビジョンに沿った成果を称賛
- 雑談や1on1でビジョンに関連する話題を挟む
浸透度を測る方法
チームビジョンが実現に向けて期限が切られているべきものである以上、その進捗度合いは日々管理されることが重要です。ビジョンに対するメンバーの理解度、実行度、チームへの浸透度を測るための方法として、以下が挙げられます。
例:
- アンケート調査で認知度や共感度を測定
- 会議中の発言や提案がビジョンに沿っているか観察
- KPIの進捗とビジョンの関係性を定期的に確認
成功するチームビジョン浸透のための3大管理職スキル
- チームビルディング
- モチベーションマネジメント
- コーチング
チームビジョンの浸透において、管理職には上記3つのスキルの習得が必要です。研修事務局は、新任管理職がこれらのスキルを体系的に身に付けられるよう、学習設計する必要があります。以下、3つのスキルを簡易的に解説します。
チームビルディング
信頼関係がない状態では、どれだけ立派なビジョンを掲げても浸透しません。かといって、チーム内の意見対立を恐れるがあまり、表面的な信頼関係を築いたところで、ビジョンを達成できる強いチームは作れません。
心理的安全性を確保しつつ、ビジョンとその達成に向けて率直に意見交換することが重要です。また、ビジョン実現に向けたモチベーションを維持、向上させるためには、小さな成功体験を日々共有し、賞賛し合うことが効果的です。
モチベーションマネジメント
メンバーそれぞれの動機付け要因を理解し、適切に刺激することで、ビジョン達成に向けた行動を促します。
メンバーが「何に動機付けられるのか」を理解するために、管理職は、メンバー各人が大切にしている価値観、職業観、キャリア観を深く理解する必要があります。
日々の1on1や定期的なキャリア面談、人事評価面談などを通じて、メンバーと向かい合い、深く対話する機会を設けることが重要です。
メンバーの主体性を引き出すコーチングスキル
「どうしたらビジョンに近づけると思う?」と問いかけ、答えを引き出すスタイルが有効です。答えを押し付けず、考える機会を与えることで主体性が育ちます。
詳しくは、管理職が身につけるべきコーチングスキルをご覧ください。
▶図表:必要な3つのスキル
スキル | 説明 | 期待効果 |
|---|---|---|
チームビルディング | 信頼関係と心理的安全性を構築 | 意見交換が活発になる |
モチベーションマネジメント | 個々の動機付け要因を理解 | 行動意欲が高まる |
コーチング | 質問で主体性を引き出す | 自律的成長を促進 |
まとめ – ビジョンで組織の一体感を高める
人事部門が研修で扱うべき「チームビジョン」は、単なる管理ツールではなく、組織を一つにまとめ、成果を最大化するための戦略的テーマです。
- 組織目標と整合させつつ、メンバーを巻き込みながら作成する
- 初期共有・日常業務への落とし込み・測定を組み合わせる
- 成功には「3大スキル(ビルディング・モチベーション・コーチング)」が不可欠
チームビジョンは「未完成で進化し続けるテーマパーク」のようなものです。
継続的な改善を組織的に楽しめる文化を創ることこそ、人事部門が新任管理職研修を企画する際の最大の狙いといえるでしょう。
サイコム・ブレイズでは新任管理職向けに、ビジョン構築&浸透を実践的に学べるプログラムとして、
「コースウエア」と「まなラン」をラインナップしております。