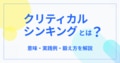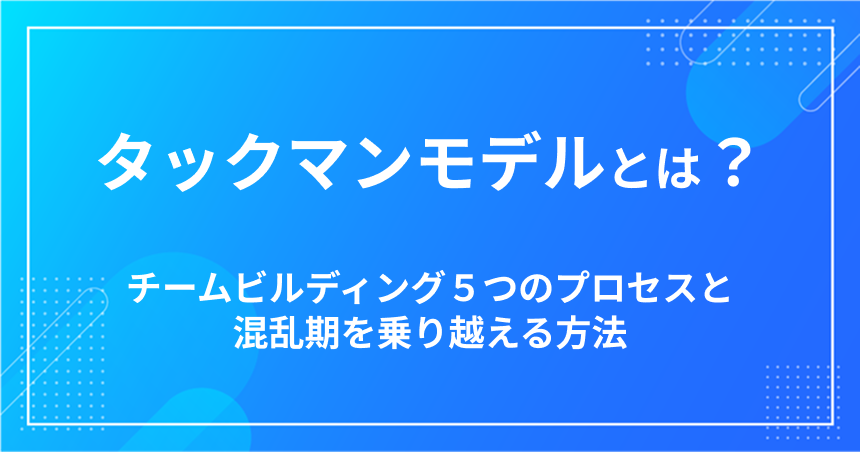
タックマンモデルとは?チームビルディング5つのプロセスと混乱期を乗り越える方法
はじめに
組織の変更や、新プロジェクトの企画などに伴い、新しいチームを作ると、そのチームが機能するようになるまでには、必ずと言ってよいほど「立ち上がりの難しさ」「メンバー間の摩擦」「成果が安定しない時期」を経験します。「タックマンモデル」は、こうしたチームの成長・発達の過程を5つの段階で説明するフレームワークです。チームビルディングを考える上で、タックマンモデルを理解することは、チームの現状を正しく認識し、リーダーとして適切なアクションを検討する上で非常に有用です。
本記事では、チームが成長するプロセスをタックマンモデルに沿って説明し、混乱期を乗り越えるためにリーダーとして行うべきこと、チームビルディング成功のポイントも詳しく紹介します。
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.タックマンモデルとは
- 3.タックマンモデルの5段階:チームビルディングが進むプロセス
- 3.1.段階1:形成期(Forming)
- 3.2.段階2:混乱期(Storming)
- 3.3.段階3:統一期(Norming)
- 3.4.段階4:機能期(Performing)
- 3.5.段階5:散会期(Adjourning)
- 4.タックマンモデルを活用するメリット
- 4.1.チームの現状を客観視できる
- 4.2.メンバー間の相互理解を後押しする
- 4.3.リーダーの成長につながる
- 5.混乱期を乗り越えるためにリーダーがすべき3つのこと
- 6.チームビルディングを成功させるための5つのポイント
- 6.1.1. 実現性のある目標を設定し、着実に前進する
- 6.2.2. 定期的なフォローとフィードバックを行う
- 6.3.3. 適材適所の人選とアサイン
- 6.4.4. 意見の多様性を尊重する風土づくり
- 6.5.5. 管理職・リーダー教育を強化する
- 7.サイコム・ブレインズのチームビルディング研修 | eラーニング
タックマンモデルとは
タックマンモデルとは、1965年に米国の心理学者であるブルース・ウェイン・タックマンが提唱した、チームの成長過程を5つの段階で説明するフレームワークです。チームが形成されたあとに起こる変化を、5つの発達段階にわけて説明しています。
タックマンモデルを理解することで、各段階におけるチームの課題、状況を正しく把握することや、適切な対策を講じることが可能になります。「チームビルディングをどう進めればよいか」「今のチームがなぜうまくいかないのか」といった悩みを客観視するアプローチとして、世界中の企業や教育現場で活用されています。
タックマンモデルの5段階:チームビルディングが進むプロセス
タックマンモデルが提唱された当初は、チームの形成から機能するようになるまでを示す4段階のモデルでしたが、1977年に、チームが任務を終えて解散する第5段階「散会期」が追加され、現在の5段階のモデルとなっています。
段階1:形成期(Forming)
新しいチームが形成された直後の状態です。メンバー同士の理解が浅く、誰もが探り合いの状態です。この時期には、歓迎会や交流会などメンバーが互いの理解を深める場を多く設けることが大切です。
また、各人が示された役割や責任をひとまず受け止めている時期でもあり、不安や期待が入り混じりつつも、まだ大きな衝突は起きにくい段階です。リーダーはこの段階からビジョンや目的を丁寧に共有し、メンバーが安心して活動できる土台を作ることが重要です。
段階2:混乱期(Storming)
チームがやがて本格的に活動を始めると、各人の意見の食い違いや価値観の衝突が表面化してきます。仕事において、誰が意思決定をするのか、どのように役割を分担するのか等を巡って、まさに嵐(Storm)のごとく、摩擦が生じやすいのがこの段階です。
多くのチームがここで停滞し、「なぜうまくいかないのか」と悩むことになりますが、リーダーとメンバーの双方が、「混乱期はチームの成長の通過点である」と理解し、対立を恐れず、根気よく対話をつづける姿勢が求められます。
段階3:統一期(Norming)
議論や衝突を経て、信頼関係が芽生え始める時期です。メンバーは互いの意見、価値観の違いを認識しつつも、共通の目標に向けて、共に協力し、動き出せるようになってきています。
この時期、リーダーはメンバーの努力を承認する、チーム共通のルールや基準を定着させる、誤った方向にメンバーの意識が向かっていないかをモニタリングするなどの役割を担います。
段階4:機能期(Performing)
この段階に入ると、チームは高い自律性を発揮し、目的達成や問題解決に向けた意見交換やアクションができるようになっています。チームのパフォーマンスが最も高くなる段階であり、これまでリーダーによる主導や介入が必要であった役割も、メンバーが自律的におこなえるように変化します。
成果が安定し、「理想的なチーム」と感じられる段階であり、リーダーは、メンバーの自律性を尊重しながら、パフォーマンスを維持できるようフォローに努めます。
段階5:散会期(Adjourning)
目標達成や、プロジェクト終了などに伴い、チームは解散を迎えます。達成感と同時に喪失感やモチベーションへの影響も生じるため、リーダーは、これまでの活動の振り返りの場を設け、ポジティブなフィードバックを送るなど、各人が前向きな気持ちで次のチーム、プロジェクトに移行する支援をおこないます。
タックマンモデルを活用するメリット
チームの現状を客観視できる
タックマンモデルは、チームの現状を客観視するヒントになります。チームが現在どの発達段階にいるかを認知することで、その段階に応じた適切な対応、働きかけ方などが明確になります。
また、チームで起きている衝突や混乱を、解決できないトラブル、障壁と捉える代わりに「今の状態は混乱期だから不安定なのは当然」と客観的に理解することで、無用な焦りを減らし、冷静に自身の役割や業務に集中することができます。
メンバー間の相互理解を後押しする
タックマンモデルは、メンバー間の相互理解を、チームビルディングの前進に欠かせない要素として捉える考え方です。活用により、メンバーは、意見の衝突は失敗ではなく、チームの成長過程の一部であり、互いを理解するきっかけとして前向きにとらえられるようになります。
また、モデルが各段階で必要な行動を示しているため、混乱期の中にあっても、「今は対話を重ねる時期だ」といった行動指針を持つことができます。このことが、対話の機会を増やし、互いの価値観や強みを理解しあう推進力として機能します。
リーダーの成長につながる
タックマンモデルでは、段階ごとに異なるチームの状態、課題が定義され、リーダーに求められる関わり方もそれぞれ提示されています。リーダーは、これらの情報をあらかじめ認識しておくことで、自身のチーム運営の在り方や、行動を振り返り、改善につなげやすくなります。
また、形成期や混乱期において、メンバーが不安や衝突と直面したり、それらを解決するためのコミュニケーションや他者受容などを経験することは、当人の柔軟性、リーダーシップ、マネジメントスキルなどの向上にも繋がります。
混乱期を乗り越えるためにリーダーがすべき3つのこと
チームが機能するようになるまでの各段階のうち、混乱期は、最も困難に直面するステージであり、リーダーの対応次第では、「チームが崩壊するリスク」に見舞われてしまうこともありえます。
混乱期の難しい状況において、チーム内に致命的な亀裂を発生させず、衝突や停滞を乗り越え、次のステージに前進させるために、リーダーとしてどのような役割を担えばよいでしょうか。下記に詳しく紹介します。
1. ビジョン・目的・役割を明確にする
混乱期を突破する最大のカギは、リーダーが明確なビジョンと目的を掲げ、繰り返し共有することです。こうした「共通の指針」があることで、エネルギーが衝突ではなく成果に向かいやすくなります。
混乱期は、メンバー同士の意見の対立が表面化し、エネルギーが衝突に費やされやすい時期です。この状況でリーダーがビジョンや目的を明確に示すことで、衝突の焦点を、個人の価値観から共通の目標へと移す効果が生まれます。
さらに、役割や責任範囲を具体的に提示することで、メンバーは「自分が何を担うべきか」を理解でき、迷いや不安が軽減されます。その結果、エネルギーが成果創出に向かいやすくなり、チームが次の段階(統一期)へと移行する足掛かりとなります。
加えて、リーダーが繰り返しメッセージを発信することは「一貫性と信頼感」を醸成します。何度も示すことで「リーダーはぶれない」「私たちの進む方向は確かだ」という安心感が生まれ、混乱期にありがちな動揺を最小化できます。
2. コミュニケーションの場を積極的に設ける
混乱期こそ、対話がチームを前進させる最大の武器になります。リーダーが積極的にコミュニケーションの場を設けることは、混乱期を乗り越えるために不可欠です。
心理的距離が広がりやすいこの段階で、対話の場を設けることは、誤解や思い込みを解消し、相互理解を促進する効果があります。衝突や不満が水面下にとどまらず、建設的な議論へと転換することで、チームは次の統一期に進む推進力を得るのです。
具体例としては、定期的な1on1やチームミーティング、テーマをしぼったワークショップなどが挙げられます。形式的会議や、カジュアルな雑談の場だけでなく、1つの議題についてじっくりと話し合える時間も設けられるとよりよいでしょう。
重要なのは、場の形式や時間の長さではなく、「本音を言える」「違いを尊重できる」安全な雰囲気を整えることです。リーダーがこうした姿勢を示し続けることで、メンバーも互いの価値観やアプローチの違いを前向きに受け止められるようになります。
3. 混乱は成長のプロセスと認識する
混乱期こそ、チームが次の段階へ進むための成長の通過点です。リーダーがこの姿勢を示すことで、困難に見える状況を前進のエネルギーへと変えることができます。
乱期は一見すると「停滞」や「失敗」のように映るかもしれません。しかし、この段階を「避けるべき状態」ではなく「成長に不可欠なプロセス」と捉えることが非常に重要です。なぜなら、混乱期はメンバーが互いの考えや価値観をぶつけ合い、真の意味で相互理解を深めていくプロセスだからです。
リーダーがこの姿勢を示すことで、メンバーも「これは次の段階に進むための必要な過程だ」と理解し、摩擦が起きても過度に不安にならず、議論を「チームを強くする材料」として建設的に活かせるようになります。
さらに、この認識を持つことは、リーダー自身の冷静さを支えます。感情的に揺さぶられることなく、適切な介入や支援を行えるようになり、結果としてメンバーの安心にもつながるのです。
チームビルディングを成功させるための5つのポイント
チームは形成から解散に至るまで、段階ごとに異なる課題や葛藤に直面しますが、どの段階においても共通して押さえるべきポイントがあります。これらを意識的に実践することで、混乱期を乗り越えるだけでなく、チーム全体が持続的に成長し、高い成果を発揮できるようになります。下記に、各ポイントについて解説します。
1. 実現性のある目標を設定し、着実に前進する
実現性のある目標こそ、チームを成長に導くエンジンです。
チームが安定して前進するためには、達成可能で現実的な目標を設定することが欠かせません。
高すぎる目標は、達成困難さからチームに挫折感や不信感を生みやすく、協働の意欲を削いでしまいます。建設的なコミュニケーションの余裕がなくなり、責任の押し付け合いに発展する危険性もあります。
一方で、現実的に達成可能な目標は、メンバーに「やればできる」という実感をもたらします。その成功体験をチームで共有することで、連帯感が育まれます。また、小さな達成を積み重ねることにより、次の挑戦への意欲が自然と生まれ、チーム全体が持続的に成長していく好循環が形成されるのです。
2. 定期的なフォローとフィードバックを行う
リーダーによるフォローとフィードバックは、チームの自律を支える「安全網」です。
チームを自律的に育てるために「課題を与え、自分たちで考えさせる」という方針は重要ですが、困っているメンバーを放置すると、孤立感や不安が増し、挑戦する意欲を削いでしまいます。リーダーが一人ひとりの特性や力量を理解し、タイミングよくアドバイスや支援を行うことで、メンバーは「見捨てられている」のではなく「見守られている」と感じ、安心して挑戦を続けられます。
また、定期的なフィードバックは、メンバーが自身の成長を実感できる機会となり、モチベーション向上につながります。リーダーにとっても、課題の早期発見や改善への舵取りが可能になり、チーム全体の健全な進化を後押しできます。
3. 適材適所の人選とアサイン
チームの成果を最大化するためは、リーダーがメンバーそれぞれの強みを見極め、最適な役割を割り振ることが欠かせません。
スキルや経験に応じて適材適所に配置することで、メンバーは自分の力を存分に発揮しやすくなり、チーム全体のパフォーマンス向上にも直結します。
また、業務アサインにあたっては、メンバーのライフステージや個別事情にも配慮することが重要です。育児や介護などと仕事を両立するメンバーの状況に応じて柔軟なアサインを行うことで、メンバーは安心して業務に取り組め、結果的にチームの安定と成長を促進します。
さらに、役割を固定化しすぎず、あえて余白や柔軟性を残すことも大切です。余白の存在はメンバーの新たな挑戦や自発的な発想を促し、チームのイノベーションにもつながります。こうした「適材適所×柔軟性」のバランスが、混乱期を乗り越えた後も強くしなやかに機能するチームをつくる基盤になるのです。
4. 意見の多様性を尊重する風土づくり
チームが長期的に進化し続けるためには、多様な意見や価値観を受け入れ合える文化が欠かせません。
これは混乱期を乗り越えるカギであると同時に、統一期や機能期においてチームの創造性や問題解決力を高める基盤にもなります。
特に混乱期には意見の衝突が顕在化します。ここでメンバー同士が発言や対話を避けてしまえば、チームの成長は止まってしまいます。異なる考えを「対立」ではなく「建設的な対話」として扱えるようにするためには、リーダーが本音で語り合える場をつくり、根気強く意見交換を重ねられる環境を整える必要があります。
こうした風土があれば、メンバーは安心して意見を共有でき、互いの強みや弱みを理解し合うことができます。その結果、チームの結束力が増し、困難な状況でも柔軟に対応できるように成長していくのです。
5. 管理職・リーダー教育を強化する
リーダー教育の強化こそ、チームを混乱から成長へ導く最短ルートです。
リーダーには、チームビルディングのプロセスそのものを理解し、状況に応じた関わり方を選択する力が求められます。
具体的には、タックマンモデルに代表されるチーム理論の理解、目標の設計・管理にかかわる知識、メンバーにフォローや指導をおこなうスキルが必要です。さらに、心理的安全性を高める知識や、対話や合意形成をリードするファシリテーション力も欠かせません。
こうした知識やスキルは、属人的な経験ではなく、教育を通じて計画的に育成することが可能です。研修やeラーニングの機会を現場のリーダーや管理職に提供することで、「混乱期を恐れず成長の糧とする視点」を養い、チーム全体の成熟を加速させられます。
サイコム・ブレインズでは、管理職・リーダーがこれらの力を体系的に学び、実践に結びつけられる研修プログラムやeラーニング、映像教材を用意しています。チームの自律性を高め、成果を最大化するために、いまこそリーダー教育を強化してみませんか。
サイコム・ブレインズのチームビルディング研修 | eラーニング
●進化型eラーニングで身につけるチーム構築の進め方「【コースウエア】チームビルディング」
●動画で学ぶチームビルディング理論と成功事例「【動画ライブラリ】自律的なチームをつくる」
●行動特性でメンバーを深く理解し、良好な関係を築く「DiSCコミュニケーション力強化プログラム」