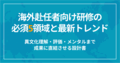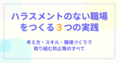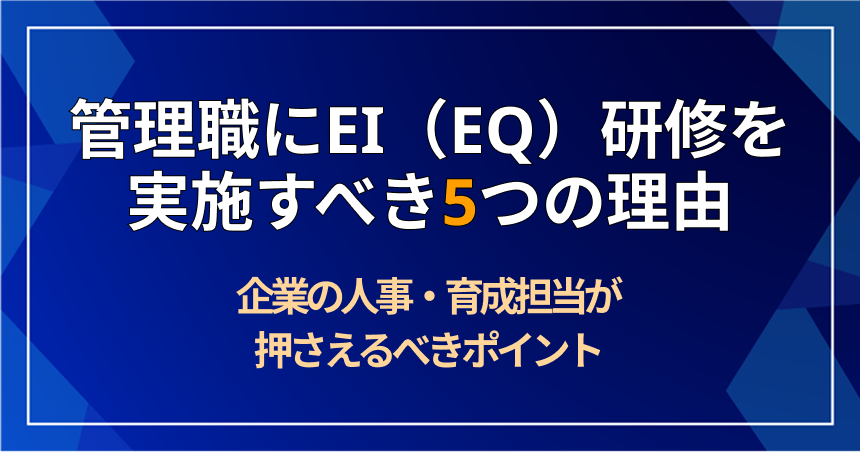
管理職にEI(EQ)研修を実施すべき5つの理由――企業の人事・育成担当が押さえるべきポイント
近年、研修テーマとして「EI(Emotional Intelligence/EQ=Emotional Quotient)」という言葉が頻繁に登場しています。こうした動きの背景には、リモートワークや多様な働き方の浸透、心理的安全性やウェルビーイングへの関心の高まりなど、組織を取り巻く環境変化があります。
とはいえ、「EIやEQとは何を指すのか」「なぜ管理職に必要なのか」「研修で本当に高められるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本稿では、まずEI/EQの定義と社会的背景を整理し、そのうえで管理職に対しEIを高める研修を実施すべき理由を5つの観点から解説します。読了後には、御社の研修企画における判断材料と導入への道筋が見えてくるはずです。
目次[非表示]
- 1.EI/EQとは何か?管理職に関わる定義の整理
- 1.1.EI/EQの構成要素/特徴
- 1.2.管理職の視点で捉えるEIの意味
- 2.なぜ「感情を仕事に持ち込まない」時代から「感情を扱う」時代へ変わったのか
- 2.1.働き方・組織リスクの変化
- 2.2.リーダーシップ観・チーム観の変化
- 3.管理職にこそEIを高めるべき「5つの理由」
- 4.EI研修は「アンガーマネジメント」と何が違うか?
- 5.研修でEI(EQ)を高めることは可能か?最新知見と実践ヒント
- 5.1.実証研究・メタ分析の状況
- 5.2.研修設計・実施・フォローアップのポイント
- 6.実務企画視点:管理職向けEI研修を導入する際のチェックリスト
- 7.まとめ
- 8.FAQ
- 9.参照・出典
EI/EQとは何か?管理職に関わる定義の整理
まず、EI(Emotional Intelligence)/EQ(Emotional Quotient)という言葉が示す意味を明確にし、管理職という立場からどう捉えるべきかを整理します。「何を研修で扱うか」を理解する土台となります。
EI/EQの構成要素/特徴
EI/EQとは、一般に「自分の感情を理解・マネジメントし、他者の感情も認識・適切に関わる能力」と定義されます。たとえば、米ハーバード・ビジネス・スクール・オンラインによれば、「自分自身の感情を理解し、自分と他人の感情に影響を及ぼす能力」がEIの要となるとされています。
代表モデルとしては、以下の4つがよく紹介されます:
- 自己認識(self-awareness)=自分の感情・強み・限界を知る。
- 自己マネジメント(self-management)=感情を適切に制御し、衝動やストレス反応をコントロール。
- 社会的認識(social awareness)=他者の感情を察知し、共感・状況理解を行う。
- 関係管理(relationship management)=他者との関係を築き・維持・影響するスキル。
特に管理職には「自分の感情に気付いて対応できる」「部下・同僚の感情反応を察知し関係を構築できる」ことが、チーム運営・フィードバック・モチベーション維持などで重要になります。
管理職の視点で捉えるEIの意味
管理職という立場から見ると、単に技術的・専門的なスキルを持つだけでは、組織/チーム運営の「人の側面」に十分対応できません。例えば、部下がストレスを抱えているときに気付けなければ、パフォーマンス低下・離職リスクにつながります。実証研究では、EIがリーダー(管理職)の有効性と強く相関することが報告されています(r = 0.771、p = 0.01という値も出ています)。
管理職にとってのEIは、「チームを成果に導くために、論理+人の感情・関係性を統合的に扱える力」と言い換えられます。つまり、部下のリアクション/ムード/心理的安全性など“見えにくい領域”を察知し、適切に介入できることが期待されるわけです。
このように整理すると、EI研修は「感情の整理だけ」ではなく、「管理職が日々のマネジメントや部下育成・組織運営で直面する“人・感情・関係”の難しさ」に対する対応力を高めるためのテーマだと言えます。
▶図1 管理職におけるEI発達のプロセスと成果へのつながり
実務への落とし込み
管理職を対象に研修設計する際は、「自己→他者→関係」という順番でスキル育成を設計すると理解が深まります。
なぜ「感情を仕事に持ち込まない」時代から「感情を扱う」時代へ変わったのか
かつて日本のビジネスシーンでは「感情を仕事に持ち込むな」「合理・論理優先」が美徳とされてきました。それがなぜ変化してきたのか、管理職の役割・組織環境の変化とあわせて整理します。
働き方・組織リスクの変化
近年、組織を取り巻く環境が大きく変化しています。例えば、リモートワーク・多様な働き手の増加・心理的安全性・ウェルビーイングへの関心など。こうした中で「見えない感情/関係性」の影響が成果や離職・モチベーションに直結するという認識が高まっています。また、技術的スキルやマーケット環境の変化スピードが上がる中、管理職にはストレスマネジメント・部下の心理的支援・チームのレジリエンス(回復力)が求められています。こうした背景から、単に「感情を切り離す」だけでは組織運営上のリスク(部下の燃え尽き、離職率上昇、コミュニケーションの断絶)を避けきれなくなりました。
したがって、「感情を無視しておけば成果に集中できる」という時代から、「感情・人・関係を能動的に扱えることが成果創出・組織の持続力につながる」という観点へ転換しています。
リーダーシップ観・チーム観の変化
従来のリーダーシップ観では「指示・管理・成果重視」が中心でしたが、現在は「関係を築き、信頼を高め、チームの力を引き出す」ことが価値になっています。管理職はもはや“命令型”ではなく“支持型/育成型”が期待され、部下の自律性・創発・心理的安全性を如何に生むかが重要です。こうした変化において、感情を理解し、関係のダイナミクスを読み、部下・同僚のモチベーションを引き出せる力(=EI)が、リーダーの重要な資質として浮上してきています。例えば、部下から「この上司には相談できる」と思われるかどうかは、技術論以上に“感情・関係”の側面で決まることも少なくありません。
このようなリーダーシップ観の変化ゆえに、管理職にとってEI/EQを高める必要性が望まれています。
実務への落とし込み
研修企画時には「変化した働き方とリーダー観/管理職の役割変化」を冒頭説明し、EIの必要性を“納得”してもらうモジュールを設けましょう。
管理職にこそEIを高めるべき「5つの理由」
では具体的に、管理職がEIを高めることで“何が変わるか”という観点から、理由を整理します。ここでは代表的に5つを紹介します。
部下との関係・エンゲージメント改善
管理職がEIを高めると、部下との信頼関係が深まり、エンゲージメント(仕事への関心・熱意)や心理的安全性が向上します。例えば、「自分の上司は感情に配慮してくれている」と感じる部下は、意見を言いやすく、アイデアを出しやすくなります。また、誤解や衝突が起きた際も、迅速に状況を察知・対応できるため、トラブルが長期化しにくくなります。実証研究でも、EIとリーダーシップ有効性の強い相関が報告されています。
こうした関係性の改善は、離職率低下・生産性改善・チームの安定運営に寄与します。管理職を対象としたEI研修を実施する意義として、「部下の言動をいち早く察知し、介入できる」ようになるという側面があります。
意思決定・ストレスマネジメント力の強化
管理職は日々、成果責任・複数部門間の調整・人材育成・変化対応など、高ストレスな局面に直面します。EIが高い管理職は、自らの感情やストレス反応を認識・制御できるため、冷静な判断を下しやすく、また部下の感情変化にも敏感です。例えば、プレッシャー下でも焦らず、チームに影響を与えにくくなります。米カル・ルーサー大学の報告では、EQが高いリーダーは「冷静に意思決定できる」「部下や組織の文化に良い影響を与える」とされています。
加えて、ストレス耐性・レジリエンス(回復力)が高まり、変化期においても管理職自身が安定感を持ってチームを導きやすくなります。つまり、EI研修は“感情に振り回されず自らをマネジメントできる管理職”育成に直結します。
▶表1:管理職がEIを高めると得られる主要な効果
理由 | 管理職がEIを高めるとどう変わるか |
|---|---|
信頼関係強化 | 部下と対話・相談しやすくなり、意見収集・協働が促進 |
離職・定着改善 | 心理的安全性が高まり、退職検討の抑制につながる |
意思決定改善 | 感情に流されず冷静判断・部下の反応予測が可能に |
チーム適応性強化 | 変化期においてもチームを安定的に導ける |
組織文化醸成 | 管理職自身の振る舞いが文化に影響し、成果基盤が強化 |
実務への落とし込み
研修企画では、上記5つの理由を「管理職にとっての痛み/期待」に即して掲げ、参加意欲を高める導入コンテンツに活用しましょう。
EI研修は「アンガーマネジメント」と何が違うか?
「感情研修」と聞くと、多くはアンガーマネジメントや“キレない上司”対策イメージが浮かびます。ここでは、EI(EQ)研修とアンガーマネジメントの違いを明確に述べ、EI研修が提供する価値を整理します。
アンガーマネジメントの位置づけと限界
アンガーマネジメントは主に「怒りという感情を認識し、コントロールする」「破壊的な感情表出を防ぐ」という目的で広まってきました。たとえば、上司の怒鳴り・部下への圧力・ハラスメントリスク低減という観点では有効です。しかし、その範囲は比較的限定的であり、「他者の感情を察知して関係構築する」「自らの感情を活かして部下のモチベーションを引き出す」といった“プラスの感情・関係性”にまで踏み込むことは少ない傾向があります。つまり、アンガーマネジメントは“マイナス対応”として有効でも、“プラス創出/日常関係構築/チームダイナミクスの改善”という観点では浅いことがあります。
EI研修がカバーする範囲と価値
一方、EI研修は「自分/他者/関係性」を広くカバーします。例えば、自分の感情に気付き、それをどうマネジメントするか(自己認識・自己マネジメント)、部下・同僚の感情の変化に気付き対応する力(社会的認識)、そしてそれを踏まえて関係を築き・影響を与える力(関係管理)です。前述の通り、管理職の成果との相関も多数報じられています。また、最新の職場研修研究では、EI/共感/感情制御を扱う研修介入が成果を上げており、職場コンテキストでの学び直しが可能というエビデンスがあります。
つまり、EI研修は「怒りを抑える」だけでなく、「日々の関係性を能動的にデザインし、チームを成果に導くための感情/関係性スキルを育てる」ことを目的とします。管理職という立場には、アンガーマネジメント以上の“人・感情・関係を統合的に扱う”スキルが求められており、その意味でEI研修がより上位のテーマと言えます。
▶図2 EI研修がカバーする範囲と価値
実務への落とし込み
研修紹介資料では「アンガーマネジメントだけでは足りない」という言葉も併記し、EI研修の“範囲拡張”を説明しましょう。
研修でEI(EQ)を高めることは可能か?最新知見と実践ヒント
「EIってそもそも生まれつきのもの」「研修で本当に高くなるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、最新の研究を踏まえつつ、研修企画側が押さえておきたいポイントを整理します。
実証研究・メタ分析の状況
実務的な観点からは、EIを育てる研修・介入が効果を出しているという報告が増えています。たとえば、職場におけるEI・共感・感情制御の研修介入を対象としたシステマティック・レビューでは「職場コンテキストでの感情能力トレーニングは成果を期待できる」と報告されています。 また、特定のマネジャーを対象にしたランダム化実験研究でも、研修後にEIスコアが改善したというデータがあります。 ただし、「どのプログラム設計・どのフォローアップが効果的か」についてはまだ研究途上です。メタ分析では「研修後の定着フォロー・現場での実践機会・上司支援」が効果を左右する因子として指摘されています。
つまり、研修でEIを高めることは“可能”というエビデンスが出ており、管理職対象としても十分検討に値するテーマです。
研修設計・実施・フォローアップのポイント
効果を出すためには、以下のポイントが重要です。
- 対象の明確化:役職・役割・課題を整理し、「どんな感情/関係性に課題があるのか」を診断する。
- プログラム構成:前述の「自己認識→他者認識→関係構築」という流れを意図的に設計。ロールプレイ、体験ワーク、振り返りなど実践型を重視。
- フォローアップ:研修後の現場実践機会、振り返りセッション、上司支援・メンタリングを設けること。定着化を支える。
- 評価・指標設定:研修前後・6 〜 12ヶ月後などで、EIスコア(アセスメント)・部下エンゲージメント・チーム離職率などをモニタリング。
- 文化・制度との連動:研修だけで終わらせず、組織文化・制度(1on1、フィードバック施策、心理的安全性)と連動させる。
これらを設計に組み込むことで、研修効果を最大化できます。特に管理職対象では「納得感」と「制度連動」が鍵となります。
▶図3 EI研修の設計から定着までのプロセス
実務への落とし込み
企画段階では、研修設計・フォローアップ・評価・制度連動をワークショップで整理し、ロードマップを明確にしましょう。
実務企画視点:管理職向けEI研修を導入する際のチェックリスト
最後に、研修を実施に移すうえで、人事/育成担当が押さえておくべき“企画・実施・定着”という観点からチェックリスト形式で整理します。
対象選定・評価指標・コスト設計
企画フェーズでは、以下の点を検討します。
- 対象レベルの明確化:例えば「課長~部長クラス」「新任管理職/経験5年以上」等。課題把握から「EIを高めるべき人材」のフォーカスが不可欠。
- 評価指標の設定:研修前後で測定すべき指標(例:EIアセスメントスコア、部下アンケート、離職率、部下生産性、1on1実施率)を設定。目に見えるKPI化が意思決定を助けます。
- コスト・リソース設計:研修時間、講師・ファシリテーター、フォローアップ支援、アセスメント導入、オンライン/集合ハイブリッド形式、予算試算などを起点にROIを検討。「投資対効果(費用対成果)」を明示できると承認を得やすくなります。
- 実施タイミング・頻度:1回限りでは定着しづらいため、ウォームアップ、メイン研修、フォローアップの3段階が望ましい。
運用・定着化・成果定着に向けたステップ
実施後は、以下の運用設計が重要です。
- 上司/部下の合意形成:管理職本人だけでなく、その上司と部下への説明・期待値共有を行い、研修後の実践を支える環境を整える。
- 行動変化支援:研修で学んだ変化を日常業務に結びつけるため、1on1やミーティング時のチェックリスト、振り返りシート、ピアサポートグループ等を設ける。
- 定期モニタリング:3〜6か月ごとに部下アンケート・チームパフォーマンス指標・離職率などを追い、「研修が変化を生んでいるか」を可視化。必要に応じて修正。
- 制度・文化との連動:例えば、フィードバック文化、心理的安全性確保制度、働き方改革の施策と連携し、「EIを高める環境」が研修外でも機能するようにする。
このように運用設計を丁寧に行うことで、単発研修に終わらせず、管理職の行動変化・組織成果までつなげることが可能です。
実務への落とし込み
企画段階でこのチェックリストをワークシート化し、ステークホルダー(経営/人事/対象管理職)で共有すると、承認が取りやすくなります。
まとめ
本稿では、まずEI(EQ)という言葉の定義と、管理職にとって重要となる理由を整理しました。次に、なぜ「感情を仕事に持ち込まない」という前提が変化し、「感情・人・関係を扱えること」が管理職に求められるようになってきたかを探りました。そして、管理職に特化してEIを高めるべき代表的な5つの理由(部下との関係改善、意思決定・ストレス対処力強化など)を挙げ、アンガーマネジメントとの違いも明確にしました。さらに、研修によるEI育成が実証されつつあるという研究エビデンスを紹介し、研修設計/フォローアップのポイント、企業で導入する際のチェックリストを提示しました。結論として、管理職のEIを高める研修は「豪華オプション」ではなく、変化対応力・関係構築・人材定着・チーム成果に直結する「戦略的投資」として位置づけるべきです。企画を検討される際には、本稿のチェックリストを活用し、対象・評価指標・フォローアップ設計を早期に固めることで、実効性の高い研修導入につなげてください。
FAQ
Q:EIとEQは同じ意味ですか?
A:はい。一般にはEI=Emotional Intelligence(感情知能)、EQ=Emotional Quotient(その知能の量を示す指標)という意味合いで使われ、混用されています。学術的な違いよりも、実務上は「感情を扱う能力」という観点で捉えられています。
Q:EI研修をやると、具体的にどんな成果が出るのでしょうか?
A:研究によれば、管理職のEIが高いと部下の満足度・信頼感・チーム効率が向上し、リーダー有効性との強い相関が確認されています。 ただし、成果を出すには設計・フォローアップが重要です。
Q:アンガーマネジメント研修とEI研修、どちらが適していますか?
A:アンガーマネジメントは「怒りを管理する」ことに焦点を当てたもので、EI研修は「自己・他者・関係性を広く扱う」ものです。管理職に“部下育成・チーム運営・変化対応”が求められる現在、EI研修の方がより戦略的と考えられます。
Q:管理職は忙しいですが、EI研修は短期間で効果がありますか?
A:単発研修だけでは定着は難しいという研究があります。職場変化・行動支援・フォローアップを設けた設計が重要です。 研修後6〜12か月の振り返りも効果的です。
Q:なぜ“感情を仕事に持ち込まない”ではなく“感情を扱う”ことが大事なのですか?
A:技術や専門知識だけでは、チームの連携・変化対応・心理的安全性の確保には限界があります。感情・関係を能動的に扱える管理職は、部下を引き出し、危機・変化環境でもチームを牽引できるため、今求められています。
Q:研修実施にあたり、どのような指標を使えば良いですか?
A:EIアセスメントスコア(研修前後)、部下アンケート(信頼・エンゲージメント)、チーム実績・離職率・1on1実施率などをKPIに設定すると、施策のインパクトとROIが明確になります。
Q:自社に合ったEI研修を選ぶ際のポイントは?
A:対象管理職の課題分析、研修内容(自己 → 他者 → 関係)構成、実践ロールプレイ・フィードバック機会、フォローアップ/定着支援設計、組織文化との連動、成果モニタリングといった要素が揃っているかをチェックしましょう。
参照・出典
- Landry, L. “Why Emotional Intelligence Is Important in Leadership.” Harvard Business School Online Blog, 2019.
- Gilar-Corbi, R., Pozo-Rico, T., Sánchez, B., Castejón, J-L. “Can emotional intelligence be improved? A randomized experimental study of a business-oriented EI training programme for senior managers.” PLOS ONE, 2019.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224254
- “Training emotional competencies at the workplace: a systematic review.” BMC Psychology, 2024.
https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-024-02198-3
- Apfelthaler, G. “Why EI is important for effective management.” Cal Lutheran News, 2024.
- “The Role of Emotional Intelligence in Management – Effective Managers”, 2024.
https://effectivemanagers.com/consultants/the-role-of-emotional-intelligence-in-management/
- “The Role of Emotional Intelligence in Modern Management.” e-six-sigma, 2025.
https://e-six-sigma.com/the-role-of-emotional-intelligence-in-modern-management/