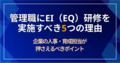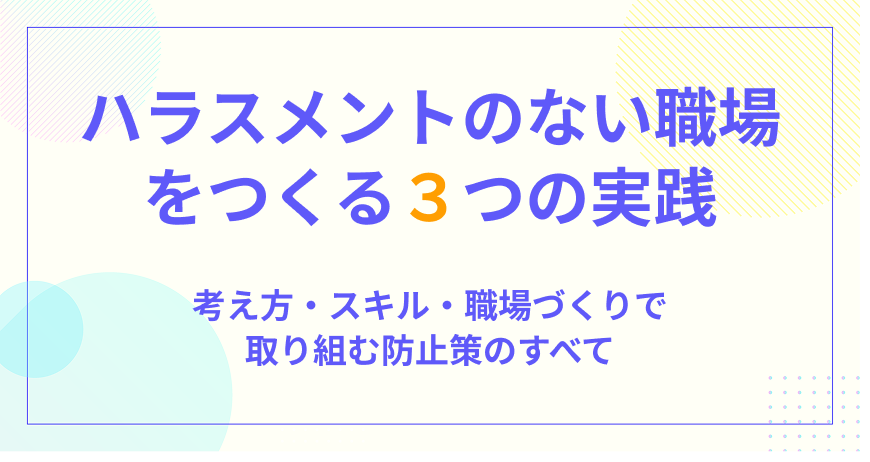
ハラスメントのない職場をつくる3つの実践軸――考え方・スキル・職場づくりで取り組む防止策のすべて
すべての社員が安心して働ける組織へ
ハラスメント研修を行っても、「社員が自分ごととして捉えられていない」「指導とハラスメントの違いが曖昧」「上司・部下・同僚との関わり方に戸惑いを感じている」といった声が後を絶ちません。厚生労働省の調査では、職場でハラスメントを経験した人は3人に1人。しかも半数が「相談できなかった」と回答しています。
本稿では、全社員が安心して働ける職場を実現するために欠かせない「3つの実践軸――①考え方(正しい理解)②スキル(対話力・関係構築力)③職場づくり(制度・文化整備)」をもとに、研修・マネジメント・組織運営に落とし込む具体策を整理します。形だけの“啓発”を超え、行動と文化の変化を生み出すための実践指針です。
目次[非表示]
考え方:ハラスメントを正しく理解し、自分ごと化する
「うちの職場は関係ない」「自分はそんなつもりで言っていない」――この無自覚こそが、ハラスメントを温存させる要因です。誰もが当事者になり得るという認識が、組織を変える第一歩です。
ハラスメントを“自分の職場の課題”として認識する
厚労省の調査によると、過去3年以内にハラスメントを経験した人は32.5%に上ります。規程の整備や相談窓口の設置など、制度面での対策は進んでいるものの、一人ひとりの意識や理解はまだ十分に浸透していないのが現状です。そのため、多くの社員が「自分は被害者でも加害者でもない」と考え、ハラスメントを“自分とは関係のない問題”として捉えてしまう傾向があります。
しかし、実際には悪意のない言葉や態度でも、相手に精神的な負担を与えることがあります。たとえば、部下が上司を無視する、同僚をグループLINEから外す、軽い冗談のつもりで相手の容姿を話題にする――これらもハラスメントに該当する可能性があります。
つまり、防止の鍵は制度ではなく、「自分の言動が相手にどう伝わっているか」を意識できるかどうかにあります。
その第一歩として、社内アンケートや相談件数、心理的安全性スコアなどの数字で現状を見える化し、職場全体で「これは自分たちの課題だ」と認識を共有することが重要です。
▶図1:ハラスメントへの気づきと自覚のプロセス
「指導」と「ハラスメント」を区別する共通基準
ハラスメントを防ぐには、“指導”と“嫌がらせ”の違いを共通言語にすることが欠かせません。厚労省は「業務の適正な範囲を超える行為」をパワハラと定義していますが、これは上司・部下・同僚いずれの関係にも当てはまります。
目的が相手の成長か、感情の発露か。方法が説明と対話か、威圧か。
この判断軸を全員で共有することで、誤解と萎縮を防げます。
▶表1:指導とハラスメントを区別する判断軸(厚労省指針より)
判断軸 | 適切な指導・助言 | ハラスメントの可能性 |
|---|---|---|
目的 | 成長支援・業務改善 | 感情的・支配的 |
方法 | 対話・説明中心 | 威圧・侮辱的言動 |
範囲 | 業務上必要 | 私的・不必要 |
関係性 | 双方向・対等 | 立場を利用・排除 |
実務への落とし込み
研修冒頭では、「自分の発言や対応を相手はどう受け取っているだろうか?」という問いを提示し、立場ごとに自分の行動を振り返る時間を設けましょう。
スキル:対話と関係づくりで防止する
ハラスメント防止の核心は、沈黙ではなく“対話”にあります。互いに尊重しながら意見を交わせる職場は、リスクを減らし、成果も高めます。言葉の選び方や伝え方を少し変えるだけで、関係性と心理的安全性は大きく変わります。
心理的安全性を高める会話スキル
Googleの社内研究「プロジェクト・アリストテレス」では、成果を上げるチームに共通する5つの要素の中で、心理的安全性が最も重要な要素のひとつであることが示されています。厚労省も、相互尊重と信頼関係を前提としたコミュニケーションを重視しています。
心理的安全性とは、「この場で自分の考えや感情を率直に話しても、非難されたり立場を脅かされたりしない」という感覚のこと。これが欠けると、問題が隠され、指摘が減り、ミスやハラスメントの兆候が見過ごされます。
(1)3ステップで建設的に伝える
ハラスメントを恐れず、誤解を防ぎながら率直に伝えるには、次の3ステップが有効です。
- 事実を具体的に伝える:「○○の報告が予定より2日遅れた」と、評価や感情を交えずに事実を述べる。
- 自分の感情を明示する:「その影響でチームの調整が難しかった」と、自分の気持ちを主語にして伝える。
- 相手への期待を共有する:「次回は一報もらえると助かる」と、未来志向の言葉で締める。
この順序を守るだけで、「責めている」ではなく「対話している」と相手に伝わりやすくなります。
(2)“受け止める力”を鍛える
多くの職場では、「話すスキル」に注目が集まりがちですが、ハラスメント防止においては「“聞く力”=受け止める力」こそが重要です。
相手の言葉を途中で遮らず、評価せず、まずは「そう感じたのですね」と受け止める。この一言が、相手の防衛反応を和らげ、信頼の扉を開きます。
また、非言語的要素――うなずき、姿勢、表情、沈黙の使い方――も対話の質を大きく左右します。
心理的安全性の高いチームでは、上司が結論を急がず、「まず聞く」時間を意識的に取っています。
(3)対話スキルを定着させる仕組み
スキルは一度の研修で身につくものではありません。
1on1で「話す:聞く=3:7」の比率を意識する。
チーム会議の終わりに「今日の話し方で気づいたこと」を振り返る。
“注意の伝え方”や“断り方”をペア練習する。
こうした小さな積み重ねが、無意識の攻撃的コミュニケーションを減らしていきます。
全社員で実践するコミュニケーション習慣
(1)日常の“ミニ対話”を増やす
ハラスメント防止を根づかせるには、日常的な対話の量と質を高めることが不可欠です。
会議や面談といった「特別な場」だけでなく、日常の雑談・朝礼・チャットでの声かけも重要です。
たとえば、
- 「最近どう?」と一言かける。
- ちょっとした成功を一緒に喜ぶ。
- 相手の意見を引用して会議で紹介する。
こうした小さな行動が「自分の意見を言っても大丈夫だ」という心理的安全性を育てます。
(2)上司だけでなく、部下・同僚も対話の主体に
ハラスメントを恐れるあまり、上司が部下との関わりを避けるケースもあります。
しかし、対話は上司だけの責任ではなく、チーム全員の役割です。
部下側からも「この言い方で伝わっていますか?」「もう少し説明いただけますか?」と尋ねる勇気が、健全な関係をつくります。
また、同僚間でも「最近、話しかけづらい様子があるけど大丈夫?」と声をかけ合える関係が理想です。
組織全体で「言葉を交わす」ことがリスク防止の最前線になります。
(3)マネジャーに求められる“観察とフィードバック”
マネジャー層には、対話を通じて早期兆候を察知する力が求められます。
部下の表情や反応の変化に気づく。
会議で発言が減った人に声をかける。
チーム内の「沈黙」を放置しない。
この“観察の眼”が、深刻化を防ぎます。
さらに、フィードバックでは「行動+影響+期待」をセットで伝えると、指導が相手に届きやすくなります。
▶表2:信頼関係を崩さない指導のフレーム
フィードバックの型 | 例文 | 目的 |
|---|---|---|
行動 | 「会議での説明が少し早かったね」 | 事実共有 |
影響 | 「他のメンバーが理解しづらかったようだよ」 | 気づき促進 |
期待 | 「次は要点を2つに絞ると伝わりやすいと思う」 | 成長支援 |
(4)感情を扱うチームのルールづくり
感情を抑え込む文化は、ハラスメントの温床になります。
チームで「イラッとしたらどうするか」「疲れている時のサインをどう伝えるか」といったルールを共有すると、トラブルを防ぎやすくなります。
実際、感情の共有を促すなどして心理的安全性が高い職場ほど、離職率が低くなることが、Gallupの研究で明らかになっています。
実務への落とし込み
1on1や定例会議で「話す技術」だけでなく、「聞く・感じ取る技術」を磨く時間を設けましょう。
特に管理職研修では、ケースロールプレイとフィードバックを組み合わせることで、自分の伝え方のクセや表情・声のトーンに気づきやすくなります。
また、アンガーマネジメント研修を導入することも効果的です。
怒りを「抑える」ではなく、「理解し、適切に表現する」スキルを学ぶことで、感情的な衝突や誤解を未然に防止できます。
上司だけでなく、部下・同僚も含め、感情の扱い方を共通言語化することで、より成熟した職場コミュニケーションが実現します。
職場づくり:制度と文化で支える仕組み化
個人の努力だけでは限界があります。仕組みと文化を両輪で整えることで、ハラスメントを“起きにくく・隠れにくく・繰り返さない”職場が実現します。
制度・評価・教育の連動
厚労省が定める3本柱は「相談体制」「迅速な対応」「再発防止」です。
- 匿名相談や外部窓口の設置で声を上げやすくする。
- 初動責任者を明確にして迅速に対応。
- 教育・評価制度と連動させ、学びを定着化。
さらに、評価項目に「育成行動」「心理的安全性の醸成」を加えることで、マネジメント行動が変わります。
▶表3:制度的アプローチの整理
施策領域 | 主な取組 | 期待効果 |
|---|---|---|
相談制度 | 匿名・外部窓口併設 | 声を上げやすい文化 |
教育 | 階層別研修+事例検討 | 学びの定着化 |
評価 | 対話・支援行動の評価化 | 指導品質の向上 |
モニタリング | 相談件数・心理安全性 | 改善状況の可視化 |
文化・風土を変えるリーダーシップ
ある調査では、「トップメッセージを発信している企業」は、防止意識が約1.5倍高いという報告があります。
経営層が「ハラスメントゼロ」を方針として明確にし、現場リーダーがそれを日常の行動で示す。これが文化定着の最短ルートです。
また、称賛文化の導入も効果的です。
良い指導や相談対応を社内表彰する。
“感謝を伝える投稿”を社内SNSで紹介する。
ポジティブな行動を可視化することで、「防止」から「信頼と支援の文化」へと変わります。
▶図2:制度と文化の統合モデル
実務への落とし込み
人事は、年1回の「ハラスメント白書(社内版)」を発行し、相談件数・対応結果・改善策を共有して透明性を高めましょう。
まとめ
ハラスメント防止の本質は、「正しい理解」「信頼に基づく対話」「仕組みと文化」の三位一体です。
まず、全社員が「誰もが当事者になり得る」と理解する。
次に、相手を尊重しながら意見を交わせるスキルを磨く。
そして、制度と文化が行動を支える仕組みを整える。
この3つの実践軸が連動すると、法令対応を超え、“安心して成果を上げられる職場”が実現します。
ハラスメント防止はリスク対応ではなく、信頼と生産性を高める経営戦略です。
今日から「考え方」「スキル」「職場づくり」を点検し、次の一歩を踏み出しましょう。
MBK Wellnessの研修プログラム
MBK Wellnessの動画コンテンツ
FAQ
Q1. ハラスメント防止は企業に義務付けられていますか?
A. はい。改正労働施策総合推進法により、すべての企業に防止措置が義務付けられています。相談体制整備、再発防止、周知・教育の3つが求められ、違反が続けば企業名公表の対象になる場合もあります。
Q2. 同僚間や部下から上司へのハラスメントもありますか?
A. あります。厚労省は「優越的関係に基づかない場合でも、他者に心理的負担を与える行為」をハラスメントと定義しています。上下や同僚関係を問わず、すべての職場行動が対象です。
Q3. 指導をしても“パワハラだ”と言われた場合、どう対応すべき?
A. まず事実を整理し、「目的」「方法」「頻度」で自分の行動を振り返りましょう。相手の受け取りを確認し、必要であれば人事や第三者窓口を交えた対話を行うことが重要です。
Q4. 効果的な防止研修を設計するには?
A. 知識→体験→行動の3段階構成が有効です。eラーニングで基礎を学び、事例討議で気づきを得て1on1で行動定着を図りましょう。
Q5. 経営層の関与をどう高めるか?
A. トップが「ハラスメントゼロ」を経営方針として明示し、日常的にメッセージを発信することが重要です。加えて現場訪問や懇談を通じ、経営層自らが“傾聴する姿勢”を示すことで文化形成が進みます。
参照・出典
・厚生労働省『職場におけるハラスメントの防止のために(総合ページ)』https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
・厚生労働省『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年告示第5号)』
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
・厚生労働省『職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度) 報告書概要・本体』
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001259093.pdf
案内ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html
・人事院『ハラスメント防止(総合ページ)』
https://www.jinji.go.jp/sekuhara/toppage.html
・人事院『人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について』
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/10_nouritu/1032000_R2shokushoku141.html
・内閣府 男女共同参画局『セクシュアル・ハラスメント対策の現状と課題(関連資料ページ)』
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/index_hbo09.html
・Google re:Work『「効果的なチームとは何か」を知る(Project Aristotle 概要)』
日本語:https://rework.withgoogle.com/intl/jp/guides/understanding-team-effectiveness
英語:https://rework.withgoogle.com/intl/en/guides/understanding-team-effectiveness
・厚生労働省『「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書(2018年)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000201268.html