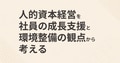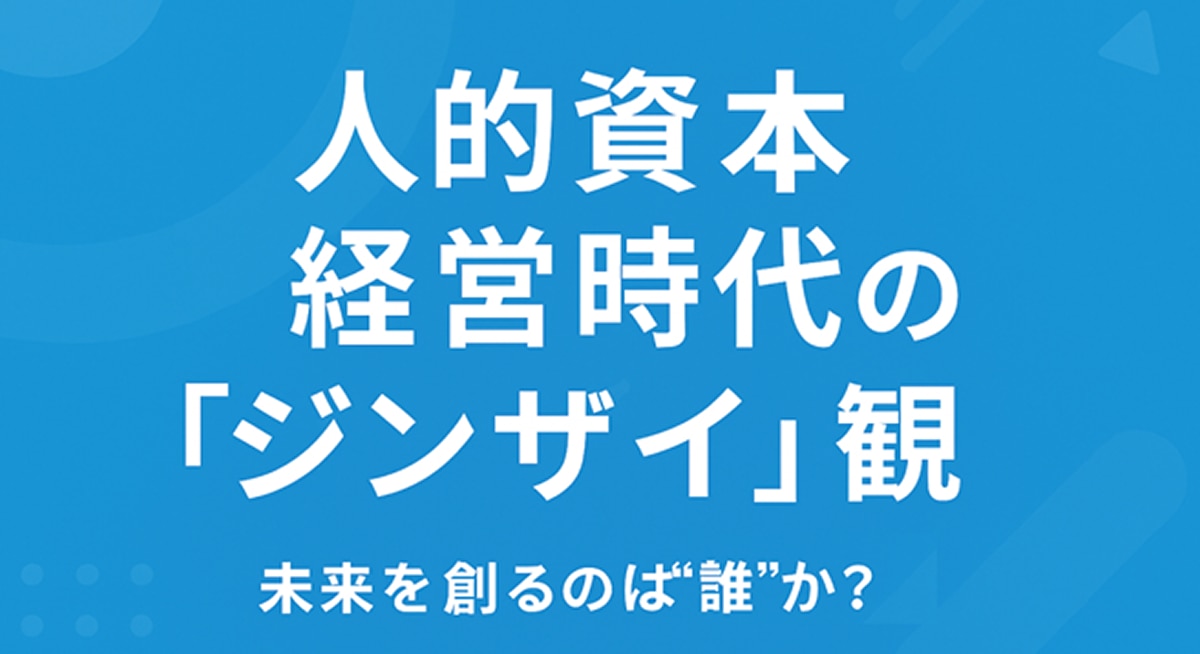
人的資本経営時代の人を見る目「ジンザイ」観 ~組織の未来を創るのは誰か~
「人材」か、「人財」か、「人在」か、「人才」か──。
一見すると読みは同じ「ジンザイ」でも、表記が違えば、その意味合いや企業の人に対する考え方は大きく異なります。皆さまの組織では、どの「ジンザイ」を重視し、どのような視点で人づくりを進めておられますか?
ここでは、政府・官公庁の公開資料をもとに、日本企業における人材観の変遷と、その背景にある社会・経済環境の変化、そして今後求められる人材戦略について考察します。
「人的資本経営に取り組むべきとは聞くが、何から始めればよいかわからない」「自社にとっての“ジンザイ”とは何かを見直したい」──。
そんな人事・人材開発担当者の皆さまをはじめ、人づくりにかかわる方々のお悩み解決につながる“ジンザイ観”について解説します。
目次[非表示]
人材観の歴史と変遷 ~“人は資源”から“資本”へ
かつて日本企業では、「人は最も重要な経営資源である」と語られてきました。この考え方は高度経済成長期における終身雇用制度・年功序列型人事のもと、従業員を長期的に雇用・育成し、企業とともに成長する「人材観」として浸透してきた背景があります。
この頃の「人材」は、どちらかといえば“資源”や“要員”としての側面が強く、「適材適所」に配置し、いかに効率よくパフォーマンスを発揮させるかというマネジメントが中心でした。
しかし1990年代のバブル崩壊以降、経済の長期低迷とともに、企業を取り巻く環境は大きく変化します。終身雇用の見直し、成果主義の導入、グローバル化やデジタル化の進展などにより、これまでの画一的な人材観では対応しきれなくなったのです。
その結果、従来の「人材=労働力」という考え方を超えて、「人財(人は会社の財産である)」という言葉が経営の現場でも語られるようになりました。この“財”という表現には、人的投資の価値やリターンを重視する姿勢が色濃く表れており、経営と人材戦略の接続が意識され始めた時期と重なります。
この動きを明確に後押ししたのが、2020年に経済産業省が公表した『人材版伊藤レポート』です。ここでは、経営戦略と人材戦略の連動や、リーダーシップ開発・人材ポートフォリオ・学び直し(リスキリング)の強化が提言されました。
さらに2022年には、非財務情報可視化研究会による『人的資本可視化指針』が策定され、企業の非財務情報としての「人への投資」や「人的資本の価値」を、開示・可視化する動きが加速しています。これにより近年では、人は単なるコストではなく、価値創造の源泉であり、企業価値を高める「資本」であるという考え方が定着しつつあります。
このような流れの中で、「人材」→「人財」へと価値観はシフトし、加えて昨今では、企業にまだ貢献していない段階の人(人在)や、将来の成長が期待される人(人才)といった視点も浮かび上がってきています。特に若手や多様な働き方をする人々をどう見て、どう育てるかという問いは、これからの人事戦略の根幹に関わる課題です。
「ジンザイ」という言葉に込める意味。それは、企業がどんな未来を描き、どんな価値を人に求め、どう育てたいのかというビジョンそのものに他なりません。
時代背景と人材戦略の変化 〜「働き手」から「価値創出の主役」へ
日本の人材戦略は、時代の変化とともに大きな転換を遂げてきました。かつての高度経済成長期には、企業が長期雇用を前提に人材を確保し、社内教育を通じてゼネラリストとして育成する「内部労働市場モデル」が中心でした。経営における人材戦略の主な目的は、安定した人員の確保と、計画的な配置・昇進による組織運営でした。
しかしバブル崩壊後、経済のグローバル化やテクノロジーの急激な進展により、企業環境は激しく変化し続けています。そうした中で、従来型の人材マネジメントは変化への対応力を欠き、時代に適応した新たな「人材戦略」が求められるようになりました。
この背景のもと、『人材版伊藤レポート』は、人材を経営戦略の中核に据える考え方を強調し、特に以下の3つの視点を重視することが提言されました。これらの視点は、単なる人事施策にとどまらず、経営そのものの質を問うアジェンダでもあります。
■ 視点1:経営戦略と人材戦略の連動
企業が目指す方向性と、人材の育成・配置・活用方針を一体で考えること。戦略実行に必要なスキル・リーダー人材の定義と育成が不可欠。
■ 視点2:AS-IS/TO-BEギャップの把握
現状の人材ポートフォリオと、今後必要とされる人材像との間にあるギャップを見える化し、それを埋める取り組みを行う。
■ 視点3:社員の主体的キャリア形成支援
社員の自律的なキャリア開発を促すことで、企業の変化への対応力も高めていく。
さらに2022年の『人的資本可視化指針』では、「人材=コスト」ではなく、「人材=投資対象」であるという見方が明確化されました。企業の長期的成長を実現するためには、人的資本(Human Capital)への戦略的投資が不可欠であるという考え方が、企業開示の中でも強調されています。
この指針の中では、人的資本に関する開示項目が以下のように例示されています。
指標例 | 説明 |
|---|---|
リスキリング・学び直しへの投資額 | 従業員のスキル向上・専門性強化への取り組み |
エンゲージメントスコア | 従業員の働きがい・会社への信頼度を定量的に測定 |
多様性(D&I)に関する数値 | 女性管理職比率、外国籍社員比率など |
離職率・定着率 | 組織の健全性や働く環境の持続性を表す指標 |
このようなデータが投資家や社会に向けて開示されるようになることで、人材マネジメントは“社内向け施策”から“社会的説明責任を伴う戦略”へと変化してきています。
人材をどう見るかは、企業がどんな価値を社会に提供しようとしているかの現れでもあります。時代の要請に応じて、「人を活かす」視点に基づいた人材戦略が、いま多くの企業に求められているのです。
「人材」「人財」「人在」「人才」、言葉が示す企業の人間観
ここで「人材」という言葉について、改めて考察します。読み方こそ「ジンザイ」で共通していても、さまざまな意味合いを持つ漢字表記が存在しています。近年ではこの言葉の表記に着目し、自社の人材戦略や人間観を見つめ直す企業が増えているようです。特に「人材」「人財」「人在」「人才」といった多義的な表現は、それぞれ企業や社会が人をどう捉えているかを映し出す鏡とも言えるでしょう。
■ 「人材」:人=資源という伝統的な見方
「人材」は最も一般的に使われる表記であり、人を「材」として捉える点にその思想が表れています。これは「人材=資源」としての捉え方であり、ある意味で経営資源の一つ(ヒト・モノ・カネ・情報)の位置づけとして扱われてきました。
この見方では、人は「育成され、配置され、活用される存在」であり、企業にとっての「使う対象」としての意味合いが強くなります。高度経済成長期からの日本企業の成長を支えてきた考え方であると同時に、近年の人的資本経営の流れの中では「一方向的で画一的な活用モデル」として、見直しが進んでいます。
■ 「人財」:人は企業の価値を創る財であるという視点
「人財」という表記は、「人こそが企業の価値を創造する“財(たから)”である」という考え方を強調します。2000年代以降、人的資本への投資や従業員エンゲージメントの重要性が認識されるようになり、この表記が広く浸透していきました。
特に『人材版伊藤レポート』でも「人材=価値創出の主体」として捉えるべきであるとされており、まさにこの「人財」という見方が背景にあると考えられます。
この言葉を積極的に使う企業は、従業員の潜在力に投資し、共に成長しようとする姿勢を社内外に示しているとも言えるでしょう。
■ 「人在」:その場に“いる”ことの意味を問う
一方で「人在」という表記は、「人はいるが、活かされていない」という皮肉を込めた表現として使われることがあります。戦略や制度は整っているが、それが現場で機能していない、あるいは従業員が“受け身”で存在しているだけといったケースを示唆します。
近年の調査でも、多くの企業で「社員が指示待ちになりがち」「自律的な行動が見られない」という課題が挙げられており、人在の状態が一部の組織で常態化している実情を示しているのかもしれません。
■「人才」:個の能力を尊重し、可能性に投資する未来志向
近年注目されつつあるのが「人才(じんさい)」という表記です。これは、中国語圏では「優秀な人材」や「逸材」を意味するポジティブな言葉であり、「人にはそれぞれ違った能力・才能がある」という前提に立った考え方です。
『人的資本可視化指針』においても、画一的な人材マネジメントから脱却し、「多様な人材が力を発揮できる環境づくり」の必要性が強調されています。まさに「人才」という言葉は、多様性と包摂(Diversity & Inclusion)の重要性を反映した、未来志向の人材観と言えるでしょう。
企業がこのような表現を積極的に採用することは、「一人ひとりの違いや個性に価値がある」とする組織文化の醸成につながります。
「人」をどう表記するかは単なる言葉選びではなく、企業がどんな人材を求め、どのような価値観のもとに育てたいのかというメッセージそのものです。「人材」「人財」「人在」「人才」――それぞれの言葉が示す背景には、企業が大切にする“人へのまなざし”が込められています。
企業が取り入れ始めた人材観と取り組みの変遷
昨今では、多くの企業が人材に関する考え方を見直し、単なるリソースや労働力としての「人材」から、価値創造の源泉としての「人財」や「人才」へと視点をシフトさせつつあります。この動きの背景には、政府による人的資本経営の推進や人的資本の「可視化」要請があり、企業にとっても自社の人材観を明確に示すことが重要な経営課題となっています。
■人的資本経営の定着と企業文化の変化
前述したとおり、2022年に経済産業省から発表された「人的資本可視化指針」では、「人材は企業価値の源泉であり、長期的な競争優位の要となる」という考え方が提示されました。この方針に従い、企業は財務情報だけでなく、人材に関する非財務情報を積極的に開示する動きが加速しています。
特に注目されているのが、「人材育成方針」「エンゲージメント」「ダイバーシティ」「リスキリング・アップスキリング」などの観点です。これらの開示は、単なる報告義務ではなく、「どのようなジンザイを求め、どのように育てているか」をステークホルダーに伝える重要な意思表示であり、企業文化そのものを映す鏡でもあります。
■実践に踏み出す企業の例
たとえば、ある先進企業では「人才」の概念を導入し、採用・育成の現場で「学歴や職歴よりもポテンシャルや適応力を重視する」選考を導入しています。これにより、年齢や経歴にとらわれず、多様な人材が活躍できる組織づくりが進められています。
また、人的資本の定量化に取り組む企業では、育成施策の成果をスキルマップや成長指標で「見える化」し、社員一人ひとりの才能や成長段階に応じたキャリア支援を提供しています。このようなアプローチは、「人才」や「人財」を重視する企業の人材観と一致しており、従来のマス型育成から個別最適な支援への転換を象徴しています。
■人事施策そのものがブランディングに
加えて、こうした人材観や育成方針は、単なる人事部門の取り組みにとどまらず、「企業ブランド」にも直結しています。人的資本経営の進展に伴い、就職・転職市場においても「どんな人材をどのように育てているか」が企業選びの重要な基準となっています。
特に若年層やグローバル人材においては、報酬や待遇よりも「自身の成長が支援されるか」「多様性が尊重されているか」といった観点で企業を評価する傾向が強まっており、企業の人材観がそのまま採用力・定着率に影響を与えるようになっています。
こうした背景の中で、企業が「人材」だけではなく「人才」「人財」といった言葉に目を向けることは、単なる表現の工夫ではなく、経営戦略そのものといえるでしょう。ジンザイという言葉が内包する多義性を理解し、組織の価値観と連動させながら、自社に合った育成方針や制度を設計していくことが、これからの人事部門に求められる役割といえます。
これからの“ジンザイ”観と、取り組むべき育成アプローチ
ここまで見てきたように、日本企業の人材観は「人材」から「人財」「人在」、そして「人才」へと広がりを見せ、単なる語感や表現の違いにとどまらず、組織の価値観や育成方針そのものに関わる大きな意味を持つようになっています。
ここでは、こうした変化を踏まえながら、これからの企業がどのように“ジンザイ”を定義し、育成のあり方を設計すべきか、その具体的な方向性について考えていきます。
■“ジンザイ観”を定義する3つの視点
組織としての“ジンザイ”観を明確にするためには、少なくとも以下の3つの視点が必要です。
①事業戦略との連動性
企業の成長ビジョンや中期経営計画と連動し、「自社の未来をつくる人材とは誰か」を明確にすることが第一歩です。人的資本開示の観点からも、採用・育成・配置の方針が戦略とつながっていることが求められます。
②人材の「変化可能性」への注目
“人材”を「持っている能力」だけでなく「これから伸びる力=ポテンシャル」として捉える視点です。固定的なラベルより、可能性への支援が“人才”の育成には不可欠です。
③多様性と包摂性の観点
背景・価値観・ライフステージの異なる人々が活躍できる組織を前提とし、「人的資本の最大化は、個の活用と尊重から始まる」とする発想が重要です。
この3点は、「誰を、なぜ、どう育てるのか」を論理的に整理するフレームにもなります。
■育成アプローチのシフト:画一的から個別最適へ
従来の一斉・年次別・階層別の研修モデルは、いま見直しの時期にあります。画一的なカリキュラムから、個人の役割・経験・課題に応じた「個別最適化」の育成施策へと、シフトが求められています。
たとえば、近年注目されているのが、自律学習支援型ラーニングプラットフォームの活用です。学習履歴に応じたレコメンドや、リスキリングニーズに合わせたコンテンツ提供、オンデマンド型の動画講座などにより、学びの習慣化と主体的なスキル開発が可能になります。
また、タレントマネジメントシステムと連携し、キャリア志向とスキルデータを基に、社員一人ひとりに合った成長ルートを提示する仕組みも広がっています。
■評価制度や配置との連動もカギに
育成だけではなく、その成果をどう「評価」し、「配置」に活かすかも重要です。人的資本経営においては、「人を活かす制度」そのものが企業価値に直結します。
実際、多くの先進企業では、以下のような取り組みが進んでいます。
施策 | 内容 |
スキルベース評価 | 職務内容よりも習得スキルを評価する仕組みの導入 |
オープンポジション制 | 部門を越えて公募で配置を決定し、挑戦意欲を引き出す |
キャリア面談の定期化 | 上司とのキャリア対話を制度化し、育成の方向性を共有 |
こうした制度は、社員のエンゲージメント向上だけでなく、“人才”を活かす組織風土づくりにもつながっています。
今後、企業が求められるのは、「優秀な人材を採る」ことではなく、「社内のあらゆる人材を、価値を創出する存在に育て、活かす」ことです。まさに、“ジンザイ”をどう定義し、育て、活かすか。それが、経営そのものの競争力になる時代に入ったといえるでしょう。
まとめ:企業の“ジンザイ観”が未来をつくる
本コラムでは、「ジンザイ」という言葉の奥にある多様な価値観と、それを支える制度や社会的背景の変遷をたどりながら、これからの人材育成の方向性について考えてきました。
かつては、企業の中で「働く人」は“資源”や“労働力”として捉えられ、どれだけ多くの人員を確保するかが経営課題でした。しかし、経済の成熟化、少子高齢化、グローバル化、そして技術革新の急速な進展により、「誰を、どのように活かすか」という視点が、企業成長の核心となっています。
その中で、「人材」「人財」「人在」「人才」という多様な“ジンザイ観”は、単なる言葉遊びではなく、企業の価値観や育成思想を映し出す鏡となっているのです。
特に政府が掲げる人的資本経営の潮流は、「人はコストではなく、投資対象である」という認識を後押ししており、企業は人への投資を「見える化」し、経営と連動させることが求められるようになっています。
今、企業にとって重要なのは「自社にとっての“ジンザイ”とは何か」という問いを明確にし、その考えを軸に育成と活用の仕組みを再構築していくことです。個人が自律的に成長し、組織の目標と調和したとき、真に価値ある存在として“人財”や“人才”と呼ばれるようになるでしょう。
変化の激しい時代において、人をどう育て、どう活かすか。その姿勢こそが、企業の未来を左右する意思決定といえます。ジンザイを巡る思考の更新が、これからの人材戦略の要になるはずです。
サイコム・ブレインズのソリューション
■本記事の監修者■