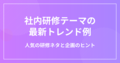DiSC理論とは?特徴・診断・ビジネスでの活用法を解説
はじめに
あなたの職場において、「相手の考えがわからない」「上司や部下との意思疎通がうまくいかない」「なんとなく一緒に仕事をやりづらい同僚がいる」といったコミュニケーションの悩みはありませんか?こうした課題を解決する方法のひとつとして注目されているのが、DiSC理論です。
DiSC理論は、人の行動特性やコミュニケーションスタイルを4つのタイプ(D・i・S・C) に分けて理解するフレームワークで、世界中の企業や組織で活用されています。自己理解を深めるだけでなく、他者理解を通じてチームの協働を促し、マネジメントや営業活動にも応用できる点が特徴です。
本記事では、「DiSCとは何か?」から「診断方法」「ビジネス活用の具体例」「研修での取り組み方」 までを解説します。人材育成や組織開発に携わる方、あるいは職場でのコミュニケーション改善に関心のある方にとって、有益なヒントを得られる内容となっています。
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.DiSC理論とは
- 2.1.DiSC理論の概要と起源
- 2.2.D(Dominance)タイプの特徴と効果的な関わり方
- 2.3. i(Influence)タイプの特徴と効果的な関わり方
- 2.4.S(Steadiness)タイプの特徴と効果的な関わり方
- 3.DiSC診断・分析方法:Everything DiSC® の概要
- 3.1.Everything DiSC® とは(国際的に活用されるアセスメントツール)
- 3.2.診断の仕組みと出力レポートの特徴
- 3.3.活用の流れと概要(導入 → 診断 → レポート提供)
- 3.4.MBTI・エニアグラムとの違い(DiSCがビジネスで選ばれる理由)
- 4.DiSCのビジネス活用法
- 5.DiSCを使ったトレーニング・研修
- 5.1.コミュニケーション研修
- 5.2.マネジメント研修
- 5.3.営業部門向け 商談力強化研修
- 6. DiSC理論を活用する際の注意点
- 7.まとめ
- 8.サイコム・ブレインズのDiSC理論を活用した研修ソリューション
DiSC理論とは
ここからは、DiSC理論の基本を整理します。DiSCとは、人の行動特性を D(Dominance)・i(Influence)・S(Steadiness)・C(Conscientiousness) の4つに分類して理解する考え方です。この章では、理論の起源や背景を押さえつつ、各特性の特徴や、効果的なコミュニケーションの取り方について紹介します。
DiSC理論の概要と起源
DiSC理論とは、人の行動特性を4つのスタイルに分類し、自己理解と他者理解を深めるための心理学モデルです。起源は1920年代、心理学者ウィリアム・M・マーストンの研究にさかのぼります。彼は人間の感情表現や行動パターンを観察し、Dominance(D)、Influence(i)、Steadiness(S)、Conscientiousness(C) という4つの要素で説明できるとしました。現在ではビジネス分野に広く応用され、組織開発やリーダーシップ研修、営業スキル向上など、多岐にわたる場面で活用されています。
D(Dominance)タイプの特徴と効果的な関わり方
Dタイプは、結果志向で行動的、意思決定が早いのが特徴です。目標達成や問題解決を重視し、率直で挑戦的な姿勢を示します。一方で、周囲に威圧的に映る場合もあり、細部への配慮を欠くことがあります。
ビジネス上で効果的に関わるには、結論から伝える、成果やメリットを明確に示す、意思決定のスピードを尊重することが有効です。冗長な説明を避け、要点を押さえて会話することで、Dタイプの強みを引き出せます。
i(Influence)タイプの特徴と効果的な関わり方
iタイプは、社交的で楽観的、人間関係を重視するスタイルです。周囲を巻き込み、明るい雰囲気をつくるのが得意で、チームのモチベーションを高める役割を果たします。ただし、感情に流されやすく、計画性や継続力に課題が出る場合もあります。
効果的な関わり方としては、ポジティブなフィードバックを与える、共感を示す、アイデアや意見を歓迎することが重要です。人とのつながりを大切にするiタイプには、協力的な姿勢を示すことで信頼関係が深まります。
S(Steadiness)タイプの特徴と効果的な関わり方
Sタイプは、協調性が高く、安定を重んじ、忍耐強いのが特徴です。周囲との調和を優先し、サポート役や調整役として力を発揮します。ただし、変化に対して慎重で、意思決定に時間がかかることがあります。
ビジネスで関わる際には、安心感を与える、時間をかけて丁寧に説明する、信頼関係を築くことが効果的です。急な変化や過度なプレッシャーを避け、安定した環境を整えることで、Sタイプは持ち前の協力性を存分に発揮します。
DiSC診断・分析方法:Everything DiSC® の概要
DiSC理論をもとに開発されたアセスメントツールが「Everything DiSC®」です。
1920年代に生まれたDiSC理論は、その後1970年代にアセスメントとして体系化され、最新の心理測定手法や統計学的研究の進歩を取り入れながら進化してきました。現在のEverything DiSC®は、精緻かつ実践的に人々の行動特性を診断・分析できるツールとして日本を含む全世界で利用されています。
Everything DiSC®を受診することにより、4つのタイプ(D・i・S・C)に沿って、自身の行動スタイルを可視化することができます。
本章では、Everything DiSC®による、基本的なDiSC診断の仕組みと出力されるレポートの特徴、導入の流れ、さらにMBTIやエニアグラムといった性格診断ツールとの違いについて解説します。
Everything DiSC® とは(国際的に活用されるアセスメントツール)
Everything DiSC®(エブリシング・ディスク) は、DiSC理論を実務で活かすために開発されたアセスメントツールです。オンライン上で設問に回答することで、行動特性やコミュニケーションスタイルが分析され、詳細なフィードバックレポートとして提示されます。
全世界で6,000万人・10万社以上に利用されており、多言語対応も進んでいるため、グローバル企業や多文化チームでも幅広く導入 されています。
その大きな特長は、単なる性格分類や診断テストにとどまらず、「ビジネス現場での人間関係改善や成果創出」に直結するよう設計されている点です。
自己理解を深めると同時に、異なるスタイルを持つ他者との関係性を築くためのヒントが盛り込まれており、マネジメント、チームビルディング、営業活動など多様なシーンで応用できます。
さらに、個人単位での診断にとどまらず、チーム全体の分析や受診者同士の比較にも活用できるため、組織全体のコミュニケーション改善や人材開発施策に役立つのも特長です。
診断の仕組みと出力レポートの特徴
Everything DiSC®では、複数の設問に回答することで、受診者の行動特性、コミュニケーションスタイルを分析し、結果を詳細なレポートとして提供します。Everything DiSC®には、組織で働くすべての人々を対象とした「Everything DiSC®ワークプレイス」と、組織のマネジャーを対象とした「Everything DiSC®マネジメント」があり、レポートには以下のような内容が含まれています。
- Everything DiSC® ワークプレイス
職場で発揮されるコミュニケーションスタイルを解説。自分の特性だけでなく、異なる特性をもつ他者の言動を理解し、良好な関係を築くためのアドバイスも含まれます。さらに、任意の二人を比較できる「比較レポート」も提供可能です。
- Everything DiSC® マネジメント
マネジャーの強みや課題を分析。部下との関係性を改善し、効果的な育成、マネジメントにつなげるための具体的な指針を提示します。比較レポートを利用すれば、マネジャーと部下の相互理解をさらに深められます。
これらのレポートは、 自己理解を促すだけでなく、上司・部下・同僚との関係改善やチームビルディングの指針を与えてくれる点に特徴があります。単なる診断テストではなく、「行動につなげるためのツール」であることが、Everything DiSC®の強みです。
活用の流れと概要(導入 → 診断 → レポート提供)
次に、Everything DiSC®を導入する際の流れを紹介します。
- 導入準備
企業・組織の目的に応じて、対象者や利用するアセスメントの種類を決定します。 - 診断実施
受検者がオンライン上で設問に回答します。回答時間は約 15 分程度です。 - レポート提供
診断結果は即時に集計され、個別の詳細レポートが出力されます。マネジャーや研修担当者がまとめて確認することも可能です。 - フィードバックと活用
結果をもとにした研修や 1on1 、チームミーティングを通じて、自己理解と他者理解を深めていきます。
上述の流れからもわかる通り、Everything DiSC®は、「診断の実施」だけで終わるものではありません。
診断で得た行動特性に関する情報、アドバイスを活かして、職場での自己・他者理解を深め、ひいてはパフォーマンスを向上させることがゴールとなります。
MBTI・エニアグラムとの違い(DiSCがビジネスで選ばれる理由)
性格や行動を理解するためのツールとしては、他にもMBTI(16タイプ性格診断)やエニアグラム(9つの性格分類)などが広く知られています。これらは自己理解を深める上で有効ですが、多くの場合「個人の性格傾向や心理タイプの診断」に焦点を当てており、職場でのコミュニケーション改善や具体的な行動変容に直結するとは限りません。
Everything DiSC®は、こうした性格診断とは異なり、職場における行動特性を分析し、組織内の実務に結びつけて活用できる点に特徴があります。診断結果は「共通言語」として職場に浸透し、上司・部下・同僚間の相互理解を促進。1on1やチームミーティング、マネジメントなど、日常業務の中で具体的に役立てられます。
また、Everything DiSC®は長年の研究に基づいて開発され、信頼性・妥当性が国際的に認められている点でも安心して導入できるツールです。「診断で終わらず、行動変化につながる」実践性が評価され、ビジネス現場で選ばれる理由となっています。
DiSCのビジネス活用法
DiSC理論は、職場でのコミュニケーションからチームづくり、マネジメント、営業活動まで、さまざまなビジネスシーンで活用できます。
この章では、代表的な活用シーンを取り上げ、具体的にどのように役立つのかを紹介します。
コミュニケーション改善(上司・部下・同僚との関係)
職場での人間関係における課題の多くは、「相手がなぜそのように行動するのか分からない」という誤解や摩擦から生まれます。DiSC理論により、上司・部下・同僚それぞれがもつ行動スタイルへの理解を深めることは、日常的なコミュニケーションを円滑にする効果があります。
たとえば、D(主導型)の傾向が強い人は結論を重視し、スピーディーな意思決定を好みます。一方、S(安定型)の人は人間関係の調和や信頼関係を優先する傾向があります。互いのスタイルを理解していれば、「なぜ相手がそのような反応をするのか」を前向きに捉えることができ、余計な摩擦を防げます。
また、診断結果を共通言語として使うことで、会議や1on1において「自分はCタイプなので細部が気になる」「相手はiタイプだからアイデアを広げるのが得意」といった会話が成立しやすくなります。こうした言語化によって、相手へのリスペクトや配慮が自然に生まれ、組織全体のコミュニケーションの質を底上げできます。
DiSC理論は「性格のラベル付け」が目的ではなく、日常業務の中で「どう関わると成果が出やすいか」を具体的に示すものです。そのため、上司と部下の信頼関係づくりや同僚間の協働促進など、あらゆる人間関係改善に役立ちます。
チームビルディングと組織活性化
組織におけるチームワーク強化や活性化のためには、メンバー同士の相互理解が不可欠です。しかし、価値観や行動スタイルの違いは、ときに摩擦や分断を生み、チーム全体のパフォーマンス低下につながることもあります。
DiSC理論により、メンバー一人ひとりの行動スタイルを理解することは、「自分と相手の違いを前提として認め合う」きっかけとなります。たとえば、目標達成を重視するDタイプ、協調性を大切にするSタイプ、論理的に検証するCタイプなどが一つのチームに混在している場合、スタイルの違いを理解していれば「どの場面で誰の強みを活かすか」が明確になります。
さらに、互いのタイプを共有することで「自分たちのチームはどのタイプが多いか」「足りていない視点はどこか」を把握できます。これにより、役割分担や意思決定のプロセスを見直すことができ、チームのバランスを整えやすくなります。
こうした取り組みは単なる研修にとどまらず、エンゲージメントの向上や心理的安全性の醸成にもつながります。メンバーが「自分の特性を理解され、尊重されている」と感じることで主体性が引き出され、組織全体の活力を高められるのです。
DiSC理論は、チームづくりにおいて「互いの違いを障害ではなく資源として活かす」という視点を提供し、組織活性化を強力に後押しします。
マネジメントやリーダーシップ開発での活用
管理職やリーダーに求められる重要な役割のひとつは、部下やチームメンバーの強みを引き出し、成果につなげることです。しかし、タイプの異なるメンバーに対して一律のマネジメントを行うと、意欲低下やコミュニケーションの行き違いを招くことがあります。
DiSC理論は、リーダーが自分自身の行動スタイルを理解すると同時に、部下のタイプに応じて関わり方を調整するための指針を提供します。たとえば、Dタイプの部下には明確な目標と裁量を与えることが効果的であり、Sタイプの部下には丁寧なサポートや信頼関係の構築が欠かせません。こうしたアプローチの違いを理解することで、リーダーシップの柔軟性が高まり、チームのモチベーションを維持しやすくなります。
また、マネジメント研修やリーダーシップ開発プログラムにDiSC理論を取り入れることで、単なる知識習得にとどまらず、実際の部下との関係構築や意思決定に直結するスキル習得が可能になります。診断結果を活用すれば、自分の強みと課題を客観的に把握でき、自己成長のロードマップを描くことにもつながります。
DiSC理論は「優れたリーダーシップの唯一の型」を示すものではなく、状況や相手に合わせて柔軟に行動を選択する力を養うための実践的なフレームワークです。そのため、マネジメントの質を高め、次世代リーダーを育成する場面で大きな効果を発揮します。
営業・顧客対応での活用
営業活動や顧客対応の場面において、営業担当者と顧客のコミュニケーションが噛み合わず、せっかくの商品やサービスの価値が伝わらない。あるいは、その顧客との関係構築が上手くいかない、といったケースはよくあることです。
DiSC理論は、相手を観察・理解し、攻略するためのシンプルな枠組みを提供します。たとえば、Dタイプの顧客には結論やメリットを端的に伝えることが効果的であり、Sタイプの顧客には信頼関係を重視し、安心感を与える対応が望まれます。相手に合わせてプレゼンテーションや交渉の進め方を調整することで、顧客満足度と商談の成功率を高めることができます。
また、営業チーム全体でDiSC理論を共有することで、「どのタイプのお客様に強いか」「どの場面で弱みが出やすいか」といった分析が可能になります。これにより、営業戦略や役割分担を最適化でき、チーム全体の成果を底上げすることにつながります。
さらに、クレーム対応やカスタマーサポートにおいても、相手のスタイルを理解して対応することで、感情的な対立を防ぎ、信頼関係を再構築しやすくなります。
DiSC理論は、営業や顧客対応の現場で「相手にどう伝えるか」「どう関係を築くか」を考えるための実践的な指針を与え、成果につながる行動を後押しします。
DiSCを使ったトレーニング・研修
DiSC理論を効果的に学び、日常業務で実践していくためには、研修やワークショップの実施が有効です。
DiSC理論と自身のタイプを理解した上で、ビジネスに即した演習やディスカッションをおこなうことで、実際の行動変容につながる、さらなる気づきと実践力を手に入れることができます。
この章では、代表的な研修プログラムとして、コミュニケーション研修、マネジメント研修、営業部門向け研修を紹介します。
コミュニケーション研修
職場の生産性や雰囲気を大きく左右するのが、日々のコミュニケーションです。
しかし「上司の指示がうまく伝わらない」「同僚との連携がぎくしゃくする」といった課題は、多くの組織で見られます。DiSC理論を取り入れたコミュニケーション研修では、受講者が自分自身と相手の行動特性を理解し、実際の会話や協働の場面でどう対応すればよいかを具体的に学ぶことができます。
特に、対人関係のすれ違いを「性格の違い」ではなく「行動スタイルの違い」として捉え直すことで、受講者は前向きな視点を獲得しやすくなります。診断結果を共通言語として活用し、職場全体のコミュニケーションを円滑にするための基盤を築ける点が大きな効果です。
チームビルディングワークショップ
チーム内での相互理解を深め、信頼関係を構築するために有効なのが「チームビルディングワークショップ」です。DiSC理論をベースにしたワークでは、メンバー同士が自分と他者のスタイルを理解しあいます。さらに、自分とは異なる特性をもつメンバー、グループへの効果的な要望の伝え方や、合意の取り付け方などを演習で学びます。
これらのワークを通し、それぞれの違いを強みとして活かす視点を共有し、チームパフォーマンスの向上につなげます。
新入社員向けコミュニケーショントレーニング
新入社員研修においては、社会人として仕事を進める上で必要となる、一定のコミュニケーション力を獲得することが急務となります。DiSC理論を取り入れたトレーニングでは、新入社員が自分のスタイルを理解するとともに、上司、先輩、同期がどのような傾向を持っているかを知ることで、入社直後からの円滑なコミュニケーションと、協働の意欲を後押しします。
たとえば、Dタイプの上司には端的な報告を心がけ、Sタイプの上司には信頼関係を意識した丁寧なやりとりを行う、といった具体的な行動の工夫が身につきます。これにより、新入社員が配属後に適応するスピードが速まり、早期離職の防止にもつながります。
マネジメント研修
管理職やリーダー層に求められるスキルのひとつが、「部下一人ひとりの特性を理解し、最適なマネジメントを行うこと」です。
DiSC理論を取り入れたマネジメント研修では、部下育成における課題、悩みを整理したうえで、自分自身のマネジメントスタイルを行動特性の観点から客観視します。その上で、部下のタイプに応じた効果的な関わり方を検討します。
たとえば、Dタイプの部下には明確な目標設定とスピード感を重視した指示が有効であり、Sタイプの部下には信頼関係の構築や粘り強いサポートが効果的です。
また、プログラム中には、部下マネジメントに影響する要因としての「無意識の偏見」の外し方や、ロールプレイワークを通した、部下への効果的なフィードバックの実践的トレーニング、実践に向けたアクションプラン立案なども含みます。1on1、評価面談などの場面で実践できるスキルが身につくため、組織全体のマネジメント力強化につながります。
営業部門向け 商談力強化研修
営業活動において成果を左右するのは、商品やサービスの魅力そのものだけでなく、「顧客に合わせたコミュニケーションの取り方」です。
DiSC理論を取り入れた営業部門向け研修では、営業担当者が自分自身と顧客の行動特性、コミュニケーションスタイルを見極め、それに応じた戦略的に商談アプローチを設計、調整するスキルを学びます。たとえば、Dタイプの顧客には結論や成果を重視した提案が有効であり、Cタイプの顧客にはデータや根拠を丁寧に示すことで信頼を獲得しやすくなります。
研修中のロールプレイワークでは、「タイプの異なる、苦手なお客様を想定した提案練習」を行い、実践力を養います。顧客の特性に応じた、提案準備、商談のすすめかた、合意形成を身につけることで、商談の成約率向上につながります。
DiSC理論を活用する際の注意点
DiSC理論は、職場での相互理解を深め、コミュニケーションを円滑にするための有効なフレームワークです。しかし、使い方を誤ると、かえって人間関係の分断や相手の可能性を狭めるリスクがあります。ここでは、活用にあたって特に注意すべきポイントを整理します。
1. スタイルに優劣をつけない
D・i・S・Cの4つのスタイルには、それぞれに強みと課題があります。どのスタイルが優れているということはなく、状況によって発揮される力が異なります。優劣をつけてしまうと、偏見や誤解を招きかねません。
2. レッテル貼りをしない
「あなたはSタイプだから必ずこうだ」と決めつけることは、本人の成長や柔軟な行動を妨げます。診断結果はあくまで傾向を示すものであり、状況や相手によって異なるスタイルを取る可能性があることを前提にすることが大切です。
3. 枠組みにとらわれすぎない
人は一つのスタイルに固定されるものではなく、複数の要素を併せ持つ場合もあります。あくまで「理解を助ける枠組み」として活用し、行動を型にはめすぎないことが重要です。
4. 本質は相互理解にある
DiSC理論は人を分類するためのものではなく、相互理解を深め、協働関係を築くためのフレームワークです。相手を理解しようとする姿勢と、自分自身を振り返る謙虚さこそが、本来の価値を引き出します。
まとめ
ここまでご紹介したように、DiSC理論は、個人の行動スタイルを理解するためのシンプルなフレームワークでありながらも、コミュニケーション改善、チームビルディング、マネジメントの質の向上、営業活動の成果強化など、職場のあらゆる場面で活用でき、組織全体の信頼関係や生産性を高める力を持っています。
働く人々の属性や、働き方の多様化が進む現代において、互いの違いを認め合い強みに変えることは、組織づくりの核心と言えます。DiSC理論は、個人と組織の双方に気付きと行動変容を促すアプローチとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。
サイコム・ブレインズのDiSC理論を活用した研修ソリューション
サイコム・ブレインズでは、DiSC理論を活用した様々な研修をご用意しています。
新入社員教育、チームビルディング、マネジメント教育、組織のコミュニケーション活性化など、記事で取り上げた課題解決に直結するプログラムを幅広くカバーしています。
オンライン/オフライン、ブレンディッドラーニング等、貴社の状況に合わせて最適な形態で提供可能です。
●アセスメントツールのご紹介「DiSC®」
●研修プログラム「DiSC®コミュニケーション力強化プログラム」
●研修プログラム「DiSCを活用した顧客タイプ別対応法(営業力強化)」