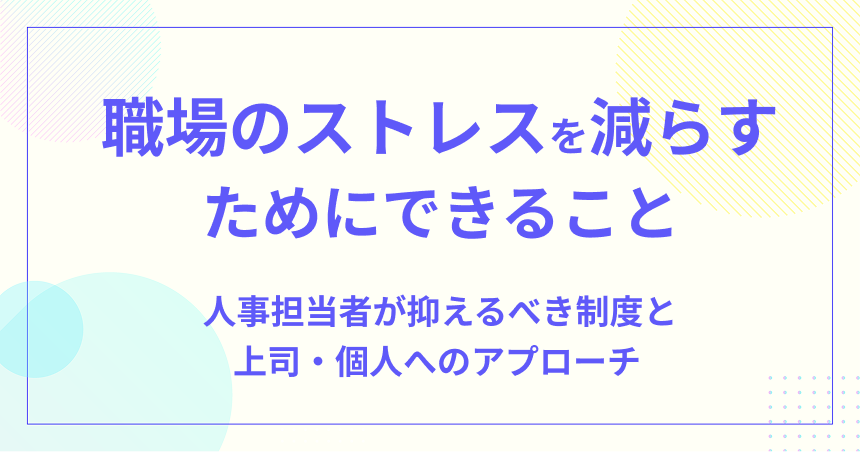
職場のストレスを減らすためにできること ― 人事担当者が押さえるべき制度と、上司・個人へのアプローチ
職場のストレスは、従業員の心身の健康だけでなく、組織の生産性や持続的成長にも大きな影響を与えます。厚生労働省『労働安全衛生調査(令和6年・2024年)』によれば、68.3%の労働者が「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安・悩み・ストレスがある」と回答しています。*1
一方で、制度や仕組みを整備しているにもかかわらず、従業員自身は「改善された」と実感していないというギャップも指摘されています。
産業保健の分野では、ストレス対策は「三段階の予防」として整理されます。
· 一次予防:ストレス要因を未然に減らす(制度・環境整備)
· 二次予防:ストレスサインを早期に発見・対応する(上司・組織の関与)
· 三次予防:不調が発生した際に重症化を防ぎ、復職支援につなげる(医療・産業医の対応)
本記事では、人事・人材開発担当者に向けて、一次・二次予防を中心にした多層的なアプローチを整理し、従業員自身のセルフケアや学習による不調予防の工夫も紹介します。さらに、改善を持続させる仕組みや実際の事例を取り上げ、実践につながるヒントを提供します。
目次[非表示]
- 1.なぜ職場のストレス対策が重要なのか
- 1.1.ストレスがもたらす影響
- 1.2.人的資本経営の観点から
- 2.一次予防としての制度と環境づくり:ストレスを未然に防ぐ
- 2.1.働き方制度の整備
- 2.2.業務量と役割の適正化
- 2.3.現場の声を取り入れる
- 3.二次予防策としての心理的安全性を高める組織文化と上司の役割
- 3.1.心理的安全性が高い職場の特徴
- 3.2.上司ができること
- 3.3.上司向け学習支援
- 4.個人のセルフケアと学習:レジリエンスを高める取り組み
- 5.改善を継続させる仕組み
- 5.1.KPIとモニタリング
- 5.2.PDCAサイクル
- 5.3.成功事例の横展開
- 5.4.公的な外部制度の活用
- 6.まとめ
なぜ職場のストレス対策が重要なのか
ストレスがもたらす影響
ストレスが長期化すると、以下のような組織リスクが顕在化します。
生産性の低下: 集中力の欠如、判断ミス、作業効率の悪化
欠勤・離職の増加: 採用・教育コストの増大につながる
メンタル不調: 抑うつや不安障害など健康リスクを高める
近年では「プレゼンティーズム(出勤はしているが心身不調で生産性が低い状態)」も注目されており、米国の調査では欠勤よりもプレゼンティーズムによる損失コストの方が大きいことが示されています。日本企業も例外ではありません。
人的資本経営の観点から
ストレス対策は福利厚生の一環ではなく、人的資本への投資です。従業員の健康が守られることで、
エンゲージメントの向上
離職率の低下
イノベーション促進
といった成果につながります。
2023年から義務化された「人的資本開示」でも、健康や働きやすさに関する指標の開示ニーズが高まっており、ストレス対策は経営課題としても重視されるようになってきています。
一次予防としての制度と環境づくり:ストレスを未然に防ぐ
厚生労働省の『これからはじめる職場環境改善』では、小さな取り組みから始め、継続して改善を重ねることが推奨されています。*2
例えば以下のような取り組みが挙げられます。
働き方制度の整備
テレワークやリモートワークの導入
フレックスタイム制度
有給休暇の取得促進、リフレッシュ休暇制度
制度だけを整えるのではなく、実際に「取得しやすい雰囲気づくり」のために、実際に上司自身が活用しつつ、部下の取得状況を確認し、利用を促すことも欠かせません。
業務量と役割の適正化
過重・過小負荷を是正する仕組み
責任と裁量のバランスを調整
「やらなくてもよい業務」を整理して業務量を適正化
業務棚卸ワークショップを実施し、不要業務を削減する取り組みは多くの企業で成果を挙げています。
現場の声を取り入れる
ストレスチェックやサーベイ結果を活用
ヒアリングや小規模ワークショップを通じた意見収集
小さな改善を試し、成果を見ながら広げていく
ストレス対策は一度の制度導入では完結しません。「サーベイ→対話→小さな実験→見直し」の短いサイクルを回し、現場が“自分ごと”として動ける状態を作ることが重要です。
二次予防策としての心理的安全性を高める組織文化と上司の役割
制度や環境が整っても、日々の職場運営や人間関係が不健全ではストレスは減りません。そこで重要なのが心理的安全性です。
心理的安全性が高い職場の特徴
発言や質問をしても否定されない
ミスや課題を率直に報告できる
上司や同僚に相談しやすい
新しいアイデアを歓迎する
Googleの研究プロジェクト「Project Aristotle」でも、高業績チームの最大の要因は心理的安全性であるとされています。*3
上司ができること
部下のストレスサイン(欠勤、集中力低下、態度の変化など)を早期に察知
業務量や役割を調整し、負担の偏りを防ぐ
傾聴と建設的なフィードバックを心がける
ハラスメントを行わない・見逃さない
定期的な1on1は、業務の優先順位整理や心理的安全性の向上に有効なアプローチです。
上司向け学習支援
「上司ができること」を上司ができるようになるためには、会社からの支援が必要です。上司向けに提供すると良い学習テーマの例としては
ハラスメント防止
法令遵守
1on1面談スキル
コーチング/フィードバック
などが挙げられます。
各テーマを学習するために、会社が研修プログラムを提供する場合には、①まず映像教材でハラスメントとその対策に関する基礎知識をインプットし、②続いて集合研修で事例を用いながら部下への注意の仕方や対応・予防策についてディスカッションする、といった構成が非常に効果的です。この構成であれば、現場ですぐに使えるスキルを身につけてもらうことができます。
ご参考として、以下に、当社でご提供している、お申し込み後、すぐにご利用いただける、映像教材、パッケージ・プログラムをご紹介します。
上司が学習を通じて行動を改善することは、心理的安全性を高める文化づくりにつながります。 「何から始めたら・・・」というご状況でしたら、職場環境の整備に大きな影響力を持つ上司向けの教育支援から始められると良いでしょう。
【映像教材】
【パッケージ・プログラム】
【映像教材のレンタル・動画ライブラリ(定額見放題)】
個人のセルフケアと学習:レジリエンスを高める取り組み
一次予防・二次予防策を土台にしつつ、従業員個人も、自らストレス対処力を高めることが必要です。
セルフケアの基本
睡眠・休養・運動・食事のバランスを整える
マインドフルネスや呼吸法などでリラックス
自分のストレスサインを知り、早めに対処する
自己理解と振り返り
どんな状況でストレスを感じやすいかを把握
ジャーナリング(日記)で思考や感情を整理
個人向け学習支援
従業員一人ひとりが、職場で感じるストレスを自らコントロールし、健やかに働き続けるためには、個人向けの学習支援が欠かせません。
学習テーマとしては以下のような領域が考えられます。
セルフケアの基本(ストレスの正しい理解、日常での対処法、睡眠・運動・食習慣のセルフマネジメント)
レジリエンス強化(逆境に立ち向かう力、ポジティブ思考の持ち方)
コミュニケーションと人間関係スキル(相手に配慮した伝え方、心理的安全性を高める働きかけ)
ハラスメント防止や緊急時の対応(万一の際に適切に行動できる基礎知識)
こうした内容を、会社が「意図を持って設計」して提供することで、従業員は日常の業務の中でも学んだことを活かしやすくなります。
例えば、自分のペースで取り組める教材を提供すれば「自律学習」となり、さらに学習期間を設定すれば「統制学習」として一定の強制力を持たせられます。加えて、学習の完了率を高め、理解を深めるためには「集団学習」の場を設けるのが効果的です。1〜1.5時間程度の短時間で、学習した内容や疑問を共有・議論するセッションを行えば、受講者同士の刺激によって学びが定着しやすくなります。
また、この「集団学習」の場は、従業員同士が互いの状況を確認し合い、上司が部下の様子を客観的に把握できる機会にもなります。1on1面談とは異なる文脈で部下の姿を見ることで、上司にとっても新しい気づきを得やすいのです。
このように、個人学習と集団学習を組み合わせて設計・提供することは、
一次予防:ストレス要因を未然に減らす(制度・環境整備)
二次予防:ストレスの兆候を早期に発見・対応する(上司・組織の関与)
三次予防:不調の重症化を防ぎ、復職支援につなげる(医療・産業医の対応)
といった段階的なストレス対策の実効性を高めることにつながります。
改善を継続させる仕組み
職場環境改善においては、定量(欠勤・離職・サーベイ)と定性(現場の声)を四半期ごとにPDCAでレビューする運用が推奨されています。*2
定量と定性の両面からレビューを行ったあとは、改善を確実に前進させるための仕組みづくりが不可欠です。以下のようなアプローチを組み合わせると良いでしょう。
KPIとモニタリング
離職率や欠勤率
エンゲージメントサーベイの結果
ストレスチェック集団分析の活用
PDCAサイクル
調査 → 改善策実施 → 再測定 → 見直し
改善の効果を見える化し、従業員にフィードバック
成功事例の横展開
成果を挙げた部署の事例を社内で共有
他部署へも展開し、全社に浸透させる
公的な外部制度の活用
厚生労働省「就業環境整備・改善支援事業(2024年度~)」では、労働条件自主点検や現場訪問支援が行われています。こうした支援制度を取り入れるのも有効です。*4
まとめ
人事担当者が職場ストレス対策を推進する際には、「どのレベルで、何を目指すのか」 を明確にしておくことが欠かせません。
また、具体的な対策を検討する際には、以下の視点が役立ちます。
一次予防: 制度・環境を整え、ストレスの芽を摘む
二次予防: 心理的安全性を高め、上司や組織が早期に対応する
三次予防: セルフケアと学習:従業員自身がレジリエンスを育み、不調を防ぐ
ストレス対策は一過性の施策ではなく、組織全体で継続的に取り組むマネジメント課題です。人事担当者が旗振り役となり、環境・上司・個人をつなぐ仕組みを整えることで、従業員が安心して力を発揮できる職場が実現します。
具体的な取り組み事例のご紹介なども可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
出展
*1.【労働安全衛生調査(令和6年 ページ)】https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r06-46-50b.html
*2.【これからはじめる職場環境改善(2024更新版 PDF)】https://www.mhlw.go.jp/content/000680306.pdf
*3.【Google re:Work(チームの有効性ガイド)】https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/
*4.【就業環境整備・改善支援事業(省公式)】https://www.mhlw.go.jp/stf/shuugyou_10286.html





