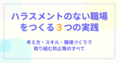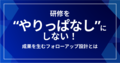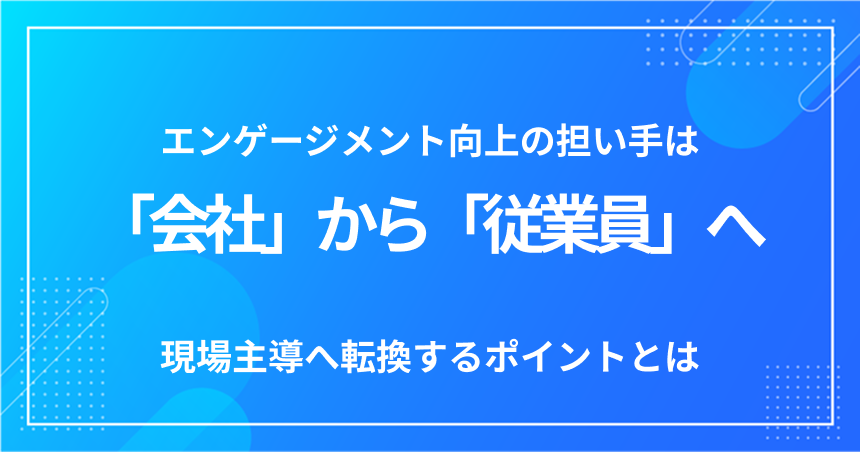
エンゲージメント向上の担い手は「会社」から「従業員」へ―現場主導へ転換するポイントとは
近年、人的資本開示の本格化とともにエンゲージメント・サーベイの実施がますます広がりを見せています。
エンゲージメントとは、仕事や組織への「能動的な関与・熱意」を捉える概念です(UWESやGallupの定義に準拠)。エンゲージメントの向上には本来は会社と従業員が“対等な関係”で互いに役割を担うものですが、長らく「エンゲージメントは会社が従業員のために上げるもの」という受け止めが支配的でした。実際にクライアント企業のサーベイ結果を拝見していると、従業員からの「会社がエンゲージメント向上のために十分な取り組みをしてくれていない」といったコメントをよく見かけます。当然、会社として、経営者として、人事担当者として、エンゲージメント向上のためにできうることはまだまだ残っていることでしょう。
一方で、「エンゲージメントは会社から与えられるものではない」という考え方が広まりつつあることも感じています。それを体現した動きとして、エンゲージメント向上の担い手を「従業員・チーム」にも広げる企業が増えています(例:人材版伊藤レポート2.0の各社事例)。私たちのクライアント企業の中でも、5年以上継続的にエンゲージメント・サーベイを実施し、ある程度トライ&エラーを繰り返してきたであろう企業においては同様の傾向が見られます。エンゲージメントというものが育まれる基盤の整備自体は会社が担うことができても、最終的に“熱意を持てるか・持てないか”は従業員次第である、と考えれば必然の流れかもしれません。
本稿では、日本におけるエンゲージメント・サーベイの実施状況を整理するとともに、サーベイ実施後の改善活動において従業員主体の取り組みを活性化させるメリット・注意点・実装手順をお伝えします。
目次[非表示]
日本の実施状況と10年変化:市場拡大と「測る→活かす」への転換
この10年、日本ではサーベイ実施の広がりとともに、市場・開示の両面で環境が大きく変化しました。まずはサーベイ実施率・市場規模の推移を捉え、課題と転換点を明確にします。
実施率・市場規模の推移
労政時報の特別調査では、エンゲージメント向上に「取り組む企業」は92.3%、サーベイの実施率は約5割と報告されています。上場企業を中心に、もはやサーベイは特別な施策ではなく標準的な経営ツールとなりつつあります。一方、市場面では矢野経済研究所によれば2023年のサーベイクラウド市場は前年比135.8%の91億円、2024年には118億円に拡大。人的資本開示義務化がこの拡大を後押ししています。つまり10年前の「導入期」から「活用・定着期」へと移行し、測定だけではなく“活用の質”が問われる段階に入ったといえます。
サーベイ後の活用課題と打ち手
拡大の一方で、依然として課題となるのが「測って終わり」問題です。矢野経済研究所は、日本企業ではサーベイ結果を施策へと結びつける力が弱いと指摘しています。人的資本開示が進む中では、単なるスコア提示ではなく「改善プロセス」をどう示すかが重要です。経済産業省『人材版伊藤レポート2.0』では、エンゲージメントを経営報酬や1on1施策と連動させる企業事例(ソニーグループ、SOMPO、丸井グループ等)が紹介され、測定から行動・開示へと一貫するサイクル設計が主流化しています。
施策トレンドの推移:制度中心から「対話・現場・従業員主体」へ
この10年で、施策の主軸は制度・環境整備偏重から、現場対話や従業員主体の関与へと変化しました。
2010年代の主流(制度・環境)
2010年代は、制度・処遇・働きやすさを整える取り組みが主流でした。評価制度の改定や両立支援制度の導入などが進み、「職場環境の整備」や「処遇見直し」がエンゲージメント向上策の中心にありました。しかし、制度変更だけでは現場マネジメントや日常の対話が変わらず、従業員の主体的関与にはつながらないという課題が顕在化します。結果、組織運営やマネジャー育成への注目が高まりました。制度面の整備が進んだ今、組織文化や関係性への介入が求められるフェーズに入っているのです。
直近の主流(1on1・EX・DX・従業員主体)
近年では、1on1やEX(Employee Experience)設計、DX活用などを通じた現場主導型のアプローチが広がっています。サーベイ結果をリアルタイムで可視化し、部署単位で改善施策を考える企業が増加。矢野経済研究所も「サーベイを可視化から運用・自走へ発展させる潮流」を強調しています。経産省の事例では、ソニーグループが経営報酬にエンゲージメント指標を組み込み、SOMPOが定期1on1でパーパスを共有、丸井グループが“手挙げ文化”を育成。これらは共通して「従業員主体」を前提としたモデルであり、エンゲージメントを“共創型の経営資源”として再定義しています。
「従業員主体の取り組み」を支えるミドルマネジャー層の課題と改善策
現場主導でのエンゲージメント推進が広がるなかで、最も負荷が集中しているのがミドルマネジャー層です。現場を支える要としての役割と、そこに潜むリスク・改善策を整理します。
ミドル層に負担が集中する実態
従業員起点の取り組みを推進しようとすると、チーム単位での対話・改善活動を支える役割が自然とミドルマネジャー層(課長・グループリーダーなど)に集中します。Gallupの「State of the Global Workplace 2025 Report」では、世界的にマネジャーの燃え尽きが深刻化していると指摘しており、日本企業でも同様の傾向が見られます。従業員主体化の裏で、ミドルマネジャー層が「組織の代弁者」と「現場支援者」という二重負担を抱えており、支援体制がなければ疲弊を招くリスクがあります。
負担を軽減し“支援型マネジメント”へ移行する方法
改善の鍵は、「監督型」から「支援型マネジメント」への転換です。サーベイ結果の分析や改善計画をチーム全員で分担し、マネジャー一人に依存しない体制を設けます。さらに、マネジャー向けには1on1スキル・心理的安全性・チーム対話設計などの研修を組み合わせ、支援者としての役割を強化することが重要です。経産省『人材版伊藤レポート2.0』のSOMPO事例でも、マネジャーを「従業員の成長支援者」と位置づける設計が紹介されています。組織全体で「マネジャーが担う負荷」を減らし、チーム全員で改善を回す文化づくりが求められます。
担い手を「従業員」に広げるメリット3点
エンゲージメント向上の担い手を会社だけでなく従業員にも広げると、組織の自律性と継続力が高まります。
自律・即応性の向上
従業員が担い手となると、組織は変化に即応できるようになります。サーベイ結果を踏まえ、現場単位で改善策を試行・検証する短サイクルが可能となり、トップダウン施策に比べ柔軟な対応が生まれます。こうした自律的な行動は自己効力感を高め、さらに新たな行動を誘発します。経産省事例でも、SOMPOの1on1導入やソニーグループの経営報酬連動が自律性を促進したと報告されています。
4.2 ボトムアップの活性化
従業員起点のアプローチでは、現場の声や知恵を施策に反映しやすくなります。丸井グループが実践する「手挙げ文化」やSOMPOの公募制度のように、従業員の意思を起点に動く仕組みは、心理的安全性を高め、参加率を上げます。チーム単位でのサーベイ共有やコメント分析を通じて、自分たちの課題を自分たちで選び改善する体験が「自分ごと化」を促します。これが組織全体に広がると、ボトムアップの文化が定着し、エンゲージメントの持続的向上が実現します。
▶表1:従業員主体で回す現場改善サイクル
ステップ | 内容 | 成果 |
|---|---|---|
1 | 結果共有・課題抽出 | 現場課題の明確化 |
2 | 改善案の選定・実行 | 迅速な実験・学習 |
3 | 成果共有・横展開 | 学習と再設計の循環 |
従業員担い手モデルの注意点・リスク
従業員主体にはメリットがある一方で、設計を誤ると形骸化や過負荷を招く恐れがあります。特に「主体性」と「責任」の境界をあいまいにしたまま進めると、現場に過剰な負担が集中し、全社課題が放置されるリスクが高まります。ここでは、注意すべきポイントを2つに整理します。
役割あいまい・丸投げのリスク
従業員主体=「現場任せ」ではありません。会社が資源提供を怠り、改善を現場に丸投げすると、モチベーションはむしろ低下します。経営・人事・現場の間で「誰がどこまで担うか」を明確に線引きすることが重要です。
特に、個人やチームでは対応しきれない全社的・構造的課題(例:評価制度・情報共有の仕組み・部門間連携など)は、経営や人事が主導して解決すべき領域です。
社員の自律を促すことと、組織課題を経営が引き受けることは矛盾しません。むしろ両者が並行して進むことで、エンゲージメントの「信頼の土台」が形成されます。
基盤不足・制度非連動の罠
従業員主体を機能させるには、データ・時間・制度連動の3要素が不可欠です。まずは、サーベイ結果をチーム単位で見える化すること。企業によっては、サーベイ結果の詳細を社内に開示することにより、「あの組織はいい組織だ」「この組織は悪い組織だ」という安易な評価や評判を広げ、結果的に職場の雰囲気や人間関係に悪影響を及ぼすことを恐れ、サーベイ結果の詳細を開示することに慎重になっているケースも見かけます。しかしながら、結果の開示無くして、改善活動を進めることは容易ではありません。少なくとも自チームの結果はメンバーに開示し、単にスコアだけを見せるのではなく、チームリーダーから背景や解釈、改善の取り組みの方向性をセットで伝えることで誤解や不安を減らすことができるでしょう。また、改善活動を進めるにあたっては、改善活動の時間を就業内に確保しなければ持続しません。加え、活動成果が評価やキャリアに反映されない場合、善意任せで終わる危険もあります。
実装チェックリストと先行ステップ
従業員主体への転換を実現するための設計・運用の要点の整理と、施策を実装する前の先行ステップについて解説します。
実装チェックリスト
項目 | チェック | 解説 |
|---|---|---|
目的定義 | 開示と改善を両立しているか | スコア向上と説明責任の両立が鍵 |
役割分担 | 経営・人事・現場の役割分担は明確か | それぞれが果たすべき範囲を定義する |
データ | チーム単位で共有できるか | 可視化粒度を部署別まで下げる |
時間 | 改善時間を公認しているか | 善意任せでは持続しない |
連動 | 評価・キャリアと結びつくか | 成果が報われる構造設計が必要 |
スキル | マネジャーの対話力を育成 | チーム運営の要となる能力 |
先行ステップ
施策を実装する前に最も重要なのは、現場が動ける基盤を会社側が整えておくことです。
まず、経営層が「エンゲージメント向上を経営課題として位置づける」明確な方針を示し、人事部門と一体で推進体制を構築します。これが“形だけの導入”を防ぐ第一歩となります。
次に、人事はデータ活用ルールや分析ツールの整備、管理職への説明・教育を行い、現場が安心して行動できる環境を整えます。
そのうえで、施策を評価・育成・報酬といった既存の人事制度と連動させ、エンゲージメント向上の取り組みが「一時的なキャンペーン」で終わらないようにします。
さらに、初回サイクルに向けて「結果共有→分析→アクション→レビュー」の流れを明文化し、誰が・いつ・どの範囲で動くのかを明確にします。
最後に、経営メッセージを伴うキックオフを実施し、経営が本気でこの取り組みにコミットしていることを社内に示すことが重要です。
これらの先行準備と制度連動が整ってはじめて、従業員主体の運用サイクルが機能します。
まとめ
日本企業では、エンゲージメント・サーベイの実施率が約5割に達し、「測る」から「活かす」への転換が進んでいます。かつては制度整備中心でしたが、近年は従業員主体の改善サイクルを重視する流れが主流です。
一方で、現場のミドルマネジャー層に負担が集中しやすく、これを支える支援型マネジメントと経営の関与が欠かせません。
エンゲージメント向上は、現場任せでも、経営主導の一方通行でもなく、「社員が動き、経営が支える」二者の協働で成立します。
会社は環境・制度・方向性を整え、社員は対話と行動で変化を生み出す――その循環が、持続的なエンゲージメント経営の核となります。人的資本開示が求められる今こそ、この「協働の設計」を見直す好機です。
FAQ
Q1:従業員主体の取り組みを始める際の最初の課題は?
A1:多くの企業で、最初に直面するのはマネジャー層への負担集中です。チームで結果共有・改善策を協議し、リーダー一人に依存しない体制を設けることが鍵です。
Q2:エンゲージメント向上において会社や経営陣が担うべき役割は何か?
A2:会社や経営陣は、社員の主体性を支える「環境と資源の提供者」であることが基本です。つまりは、上司支援・裁量・成長機会などの仕事の資源を増やす役割を担っています。加えて、チームレベルでは解決できない全社的・構造的課題(例:評価制度の硬直性、部署間連携の断絶、経営方針の不透明さなど)については、会社や経営陣が責任をもって取り組む必要があります。社員が主体的に動けるのは、経営がこうした根本課題を引き受けてこそです。
つまり、エンゲージメント向上は「現場の自走+経営の構造改革」の両輪で進めるべき取り組みなのです。
参照・出典
労務行政研究所(2025)『従業員エンゲージメントの向上施策に関するアンケート』-https://www.rosei.or.jp/data/labo/research/limited/2025engagement.pdf
経済産業省(2022)『人材版伊藤レポート2.0 実践事例集』-https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0_cases.pdf
Gallup(2025)『State of the Global Workplace 2025 Report』
Schaufeli, W. 他(2006)『UWES: The Measurement of Work Engagement』-https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/251.pdf
サイコム・ブレインズのソリューション
サイコム・ブレインズでは、エンゲージメント・サーベイの実施から、従業員主体の改善施策の立案・実践までを一貫して支援するサービスを展開しています。サーベイ結果をもとに、現場の声を活かしたアクションにつなげることで、組織の変革を着実に前へ進める――そんな「人と組織が動き出す仕組み」をご提供します。
●【まなラン】エンゲージメントを高めよう