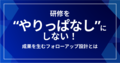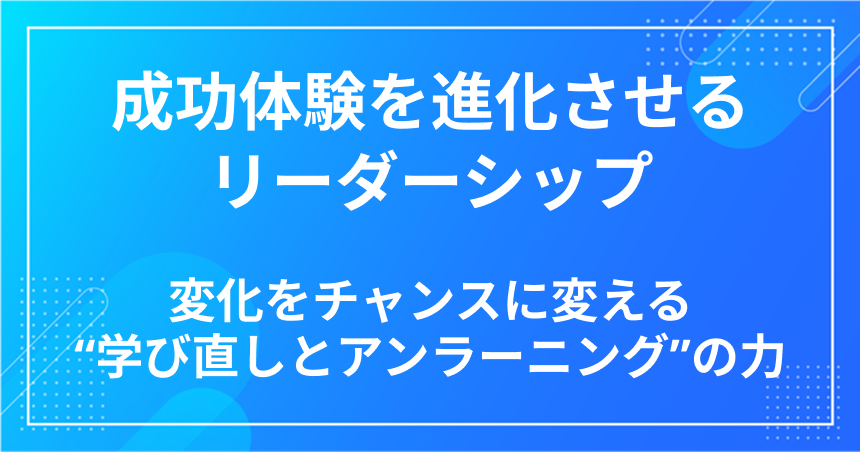
成功体験を進化させるリーダーシップ ―変化をチャンスに変える“学び直しとアンラーニング”の力―
気づかぬうちに、かつてのやり方を守り続けてしまう。そんな姿は、多くの企業の管理職層で見られます。本人に悪意があるわけではありません。長年の成功体験が「自分の型」となり、新しい挑戦を受け入れにくくしているのです。
いま、求められているのは過去を否定することではなく、「経験を問い直す力」です。
本稿では、成功体験を“手放す”のではなく“進化させる”という視点から、変化をチャンスに変えるリーダーシップを考えます。
目次[非表示]
成功体験が“進化の壁”になる理由
過去の成功はリーダーの誇りであり、自信の源でもあります。しかし環境が変わると、その成功の型が「行動の枠」になり、新たな挑戦を妨げることがあります。その背景には、人の心理に根差した“守りの傾向”が潜んでいます。
「失敗できない立場」が生む守りの行動
長く成果を上げてきた管理職ほど、「今さら失敗できない」という意識を強く持ちます。
評価や部下の目が気になる中で、「挑戦してもし結果が出なければ」と考えるほど、行動は慎重になります。人は、得る喜びよりも失う痛みに敏感に反応します。この心理的な傾向が、“変化より安定”を選びやすくしているのです。
組織の“安心の文化”が変化を支える
意欲を引き出すには、「挑戦しても大丈夫」という安心感が欠かせません。挑戦を評価する制度や、失敗を共有できる文化がある職場では、人はより自由に新しい試みを行えます。リーダー自身も「経験を活かして次のやり方を探す」姿勢を見せることで、成功体験を“進化の資源”へ変えられるのです。
▶図1:成功体験が心理的壁に変わるプロセス
図1:成功体験は自信を生む一方で、挑戦をためらう要因にもなる。
変化を避ける心理のメカニズム
変化を拒む行動の背景には、心理的な防衛が働いています。それは「変化を恐れる」よりも、「これまでの自分を守ろうとする」自然な反応です。
“これまでの自分”を手放す難しさ
長いキャリアで培った成功パターンは、自己像と結びついています。それを変えることは、自分の価値観を問い直す行為でもあります。ここで重要になるのが、”アンラーニング(Unlearning)”の発想です。
アンラーニングとは、過去のやり方を「忘れる」ことではなく、「今の環境に合うように再定義する」こと。たとえば、過去に有効だったリーダー像を見直し、“指示型”から“共創型”へ自分の行動軸を進化させる――これも立派なアンラーニングの実践です。
当社が提供するダイバーシティ・マネジメント研修でも、受講者が自身の「思い込み」や「成功体験の前提」を見つめ直し、多様な価値観を受け入れる柔軟性を養っています。これは、アンラーニングを実践的に体感する好例です。
「できるようになる」と信じる力
行動を変えるために必要なのは、“変わる勇気”よりも“変われる自信”です。心理学者キャロル・ドゥエックが提唱した「成長マインドセット」は、「能力は努力や経験で伸ばせる」と信じることが、挑戦を支える基盤になると示しています。この感覚を取り戻すことが、学び直しとアンラーニングの起点になります。
学び直しとアンラーニングが変化を促す理由
学び直し(Re-learning)は、新しい知識を身につけるだけでなく、既存の思考を再構成し、行動を再設計するプロセスです。そして、その前提にあるのが「アンラーニング」です。
越境と対話が内省を深める
学び直しは孤独な作業ではありません。他部署や他職種の人との意見交換、他企業リーダーとの対話を通じて、自分の考え方を相対化することができます。この“越境”が、経験の意味を再解釈し、行動変容を生む鍵になります。異業種交流が難しい場合でも、社内研修で他部署の参加者と事例共有を行うことでも十分に効果があります。異なる現場の価値観に触れることで、自分の判断軸を客観視でき、小さな気づきから大きな変化が始まります。
アセスメントで「気づき」を可視化する
学び直しを行動に変えるには、自己理解の可視化が欠かせません。当社のアセスメントでは、リーダーが自分の思考傾向や意思決定パターンを数値化し、「どんな場面で強みを発揮し、どんな状況で硬直しやすいのか」を客観的に把握します。これにより、漠然とした“課題意識”を具体的な行動テーマに変えることができます。
可視化は、アンラーニングを進めるうえでも有効です。なぜなら、人は“見えないもの”を手放せないからです。行動データを可視化することで、「自分の成功パターンの限界」を受け入れ、次の行動を設計する勇気が生まれます。
経験学習の循環で行動を変える
デイヴィッド・コルブの経験学習モデルは、「経験→内省→概念化→試行」の循環を重視します。越境・対話・アセスメントによる内省を通じて、学びが深化し、次の試行へと移行していきます。アンラーニングとリスキリングを両輪として回すことが、真の変化を生み出す条件です。
図2:越境・内省・可視化による経験学習サイクル
図2:越境・対話・アセスメント・アンラーニングが行動変容を支える。
学びを支える組織設計
個人が学びを始めても、組織がそれを支える仕組みがなければ変化は定着しません。ここでは、制度と文化の両面から「学びが続く組織」の条件を考えます。
制度面:挑戦を評価する仕組み
挑戦を“成功・失敗”で判断してしまうと、挑戦そのものが減ってしまいます。学びを促す制度では、「結果」よりも「試み」を評価対象にすることがポイントです。たとえば、上司評価の項目に「新しい手法への挑戦」「チームへの学びの還元」を加える。
このような行動指標があれば、メンバーは安心して動けます。
あるメーカーでは、「挑戦のプロセス」を表彰する社内制度を導入し、“成功例”より“試行例”を共有する文化をつくっています。失敗の共有が学習の土台になると、組織は着実に変化します。
また、当社の研修でも、受講者が策定したアクションプランの「結果」だけでなく、「プランそのもの」を共有することを重視しています。計画段階の意図や背景を語り合うことで、参加者は互いの考え方や行動設計を学び合い、「挑戦の過程を評価する」文化を体感します。このプロセスは、職場に戻った後の対話やフィードバックにもつながり、
学びを一過性で終わらせない仕組みとして機能しています。
文化面:心理的安全性とトップの語り
リーダーや経営層が自分の経験をオープンに話すと、組織全体の空気が変わります。「自分も変化に戸惑った」「学び直して理解が深まった」と語ることで、メンバーは「変わってもいい」「迷ってもいい」と感じられるようになります。この“語り”こそ、心理的安全性を高める最も実践的な行為です。心理的安全性は単なる“やさしい雰囲気”ではありません。率直な意見が交わせる、信頼に基づいた緊張感のある関係です。
リーダーがこの場を意識的に設計することで、組織は“学ぶ文化”へと変わっていきます。
▶図3:学びを支える組織構造
図3:制度と文化の両輪で学びを定着させる。
リーダーが変化を体現する4つの行動
変化を起こすリーダーは、「新しい行動を試すこと」そのものをリーダーシップと捉えています。彼らの共通点は、“変化を恐れず挑戦を続ける姿”をメンバーに見せることです。
行動 | 内容 | 実務ポイント |
|---|---|---|
共感する | メンバーの不安に寄り添う | 「どう感じた?」と尋ねる |
意図を語る | 変化の背景を伝える | “なぜ変えるのか”を自分の言葉で語る |
自ら学ぶ | 先頭に立つ | 部下より先に試して見せる |
小さく試す | 成功体験を更新する | 1週間単位で行動を検証する |
リーダー自身が“学び続ける姿”を見せることは、チームに対して「変化は怖くない」というメッセージになります。その過程で、リーダー自身もアンラーニングを体験しています。「リーダーとはこうあるべき」という固定観念を解きほぐし、新しいスタイルを試す姿が、部下の挑戦を後押しするのです。
小さな成功を共有し、次の挑戦へ
行動科学では、「Small Wins(小さな成功)」が行動変化を定着させるといわれます。
大きな改革を待たずに、まずは小さな挑戦から始める。たとえば「1on1で質問を変える」「打ち合わせで意見を1つ増やす」といった行動で十分です。その成果や気づきをチームで共有することで、挑戦が連鎖し、学びの文化が広がります。
図4:行動変化のスパイラル
図4:共感と共有が挑戦を循環させる。
成功体験を進化させる組織への展望
学び直しとアンラーニングは、個人の変化にとどまりません。それは、組織が「挑戦を称え、学びを循環させる文化」を育てる営みでもあります。本稿で見てきたように、変化に強い組織には次の3つの要素が共通しています。
- 挑戦を評価する制度設計 ― 行動の意図や試行を正当に評価する仕組み。
- 越境と対話を促す場づくり ― 他者との関わりから新しい視点を得る機会。
- 経営層が変化を語るリーダーシップ ― 学び続ける姿勢を自ら示すこと。
これらが循環すると、個人の経験が組織の知へと変わり、「学びが組織文化として根づく」状態が生まれます。
当社では、こうした仕組みを支援する複数のプログラムを開発しています。たとえば、越境型リーダー育成研修では異文化環境でのビジネス体験を、次世代リーダー育成研修では個人の内省を深める学びの設計を重視しています。これらは、「成功体験を進化させるリーダー」を育てるための一つの実践例にすぎません。
本質は、“過去を否定せず、未来の行動へと再構成する”こと。その姿勢を持つリーダーが一人でも増えれば、組織全体が変化を前向きに受け止め、
挑戦が自然に生まれるカルチャーが育っていくのです。
FAQ
Q1:ベテラン管理職にも“学び直し”は必要でしょうか?
はい。経験と成功体験があるからこそ、変化する時代に合わせて「自分のやり方」を問い直す機会が必要です。学び直しは、経験を否定するのではなく、次の価値へ転換するプロセスです。
Q2:「越境や対話」の場とは具体的にどのようなものですか?
たとえば他部署・異業種交流、他企業リーダーとの座談会などです。
異業種交流が難しい場合でも、社内研修で他部署や他職種の参加者と意見交換や事例共有を行うことでも十分に効果があります。異なる業務背景に触れることで、自分の考え方を客観的に見直せます。
Q3:「挑戦を評価する制度」とはどうデザインすればよいですか?
結果だけでなく「試み」を評価します。たとえば“新しい手法を試したか”“他部署と連携したか”といった行動指標を設定することで、挑戦しやすい風土が生まれます。
Q4:「アンラーニング」はどうすれば実践できますか?
自分の「正解の前提」を疑うことから始めます。
部下との1on1で意識的に“聞く時間”を増やすなど、日常行動で試すのが効果的です。
Q5:学び直しを継続するために有効な仕組みは?
アセスメントによる可視化や、研修内でのアクションプラン共有が効果的です。
学びの意図を言語化・共有することで、職場でも行動が続きやすくなります。