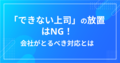次世代リーダー育成を成功に導く「学習体験デザイン」──アクションラーニングを核にした設計と運用
事業を任せられる「自走型リーダー」が育たない——多くの上場企業の人材責任者が抱える共通課題です。人手不足や業務の分業化、リモートワークの定着などにより、現場での挑戦的な任務(タフアサインメント)を与えにくくなり、従来の座学中心研修は越境学習や戦略思考の定着に届きません。
本稿は、アクションラーニングを核に、経験学習・学習転移・心理的安全性を統合した「学習体験デザイン(LXD)」の設計と運用を体系化。研修前・中・後の設計指針、擬似現場の作り方、効果測定の要点まで、明日から使える具体策を提示します。
目次[非表示]
なぜ今「学習体験デザイン」か:環境変化と70-20-10の再解釈
人手不足・高齢化・働き方の変化で、現場に任せるだけの育成は機能しづらい。研究知見とマクロ環境を起点に、70-20-10を“設計可能な学習体験”に翻訳します。
人手不足・高齢化・働き方変化が学習の前提を変える
日本では人口減・高齢化が進み、企業は構造的な人手不足に直面しています(例:Reuters「Japan firms face serious labour crunch…」2025年1月)。また、厚生労働省「Age of the 100-Year Life」(2023)でも、人口減少と高齢化が示され、リモートワークや多様な働き方が定着しています。OJTやタフアサイン(新規事業の立ち上げや赤字部門の再建、未経験領域への挑戦的な人事異動など)だけに依存した育成は機会不足に陥りがちで、意図的に設計された学習体験により、経験機会を補完・加速させる発想が不可欠です。
70-20-10を“設計”に落とす:現場×他者×研修の編成
リーダー育成の世界では、「仕事からの経験70%」「他者との関わりからの学び20%」「教育・研修からの学び10%」の比率で成長が構成される――という「70-20-10の法則」が知られています。
これは「多くの学びは日常業務の中で生まれる」という実態を示す経験則ですが、同時に、放っておけば自然に形成されるものではない点が誤解されがちです。
Center for Creative Leadership(CCL)の研究によれば、優れたリーダーは「実地経験」「他者からの学び」「体系的教育」の三要素を相互に結びつけながら成長しており、どの要素も設計によって効果が高まります。
したがって、現場課題を核に、社外や他部門などの異なる視点(顧客・メンター・他社)と、短時間の教育インプットを組み合わせ、循環的に実践→振り返り→改善を回す仕組みが必要です。
70-20-10は比率を守るルールではなく、学習機会をどう配置・接続するかを考える設計指針と捉えるのが本質です。
▶表1:70-20-10を学習体験に翻訳するチェック項目
要素 | 設計の問い | 実施例 | 一言解説 |
|---|---|---|---|
70:仕事 | 本業課題に直結しているか | 既存事業の粗利改善スプリント | 成果責任が学習を駆動 |
20:他者 | フィードバックとメンタリングの設計 | 上司1on1、外部メンター | 他者視点で盲点が開く |
10:教育 | 行動に直結する最小インプットか | 90分マイクロ講義+演習 | 学びを即実践へ接続 |
実務への落とし込み:70・20・10の要素を“学習機会マップ”として構造化し、現場・他者・教育の機会を整理・可視化して偏りを防ぐ。
アクションラーニングの本質と誤解を解き明かす
アクションラーニングとは、現実の課題に取り組みながら学ぶ、実践的な学習プロセスです。一方で、その定義や形式は幅広く、誤解も少なくありません。一般的に、コーチの質問を通じて内省とリーダーシップを育むセッション型プログラムを指すことがありますが、本稿で扱うのはそれよりも広義のアクションラーニングです。
ここで言うアクションラーニングとは、チームで実際の経営・事業課題や新規事業テーマに取り組み、半年程度のプロジェクト期間を通じて「仮説立案→フィールド検証→振り返り→再設計」を繰り返す、実践探究型の学習プロセスを指します。各サイクルではワークショップ形式で講師やファシリテーターがフィードバックを行い、次のフィールドワークに反映する流れを設計しています。
このプロセスは、単なる課題解決の手段ではなく、「経験を通じて思考と行動を磨く学習のデザイン」です。プロジェクトを推進する過程で、受講者は戦略思考力・協働推進力・リーダーシップなどを総合的に高めていきます。実務と学びを循環させる仕組みこそがアクションラーニングの本質であり、その設計精度が次世代リーダー育成の成果を大きく左右します。
定義と原理:L = P + Q(知識+問い)から始まる
アクションラーニングは、英国の経営学者レグ・レバンス(Reg Revans)が提唱した理論を起点としています。
彼は学習の本質を、次の有名な方程式で表しました。
L = P + Q
(Learning = Programmed Knowledge+ Questioning Insight)
つまり、学習(L)とは「既存の知識(P)」に「探求的な問い(Q)」が加わることで生まれるという考え方です。レバンスは、学びを成立させる鍵は行動(Action)を通じて問い(Questioning)を立て、考え、試すことにあると説き、この「行動と問いの往復」こそがアクションラーニングの原点であるとしました。
参加者は、組織の実課題を題材に「問いを起点に行動し、行動を通して問いを磨く」循環を繰り返します。
このとき重要なのは、正解を探すことではなく、行動を通じて新しい理解を生むこと。
アクションラーニングは、単なる研修手法ではなく、組織に学びを埋め込むデザインアプローチです。
当社のプログラム設計でも、プロジェクト型演習や越境共創にこの原理を適用し、「学びながら事業を創る」構造を取り入れています。
レバンスの原則:行動(Action)と問い(Questioning)の循環
レバンスが示した原則は、行動(Action)と問い(Questioning)の往復によって、思考が深まり成果が生まれるというものです。
アクションラーニングの場では、実際の組織課題を扱うチーム(セット)が、自律的に問いを立て、仮説を現場で検証し、結果を持ち寄って振り返ります。
ここで重要なのは、講師が答えを教えるのではなく、メンバー同士が「なぜそう考えるのか」を問うプロセスを通して自己省察を促すこと。
その過程で、行動と内省が連続し、リーダーとしての判断力・他者理解・戦略的思考が磨かれていきます。
心理的安全性が成果を左右する
エイミー・エドモンドソン(Amy Edmondson)は、心理的安全性がチーム学習行動を促進することを示しました。役職を外すルール、観察者によるプロセス振り返り、失敗からの学びを称える文化が、挑戦的な実践を可能にします。心理的安全性は“優しさ”ではなく、学習のための規律ある土台です。
▶図1:A(行動)×Q(問い)×R(成果責任)の循環モデル
実務への落とし込み:初回に“対話のルール”と観察者役を決め、各回で2項目の行動基準(対話・実践の質を高めるために定める観察・振り返りの基準)を設定し、振り返る。
学習体験デザインの設計原則:経験学習×転移×心理的安全性
コルブ(David Kolb)の経験学習サイクル、ボールドウィン&フォード(Baldwin & Ford)の学習転移、エイミー・エドモンドソンの心理的安全性。リーダー育成を成功させるには、この3つの理論を“研修設計の型”として具体化することが欠かせません。
コルブのサイクルで「手触り感のある学び」を作る
コルブは、人が深く学ぶためには「経験→内省→概念化→実践」のサイクルを回すことが重要だと示しました。研修設計でも、講義(概念化)だけでなく、演習や現場実践(経験・実践)と、丁寧な振り返り(内省)を1スプリント内で繰り返します。たとえば、90分のインプット→1週間の現場実践→ピアレビュー→次の実践という短い周期を設けることで、受講者が「自分の仕事の中で手を動かした実感」を得られ、知識が“使える形”へと変わっていきます。
学習転移の三要素:受講者×設計×職場環境
ボールドウィン&フォードの研究では、研修の成果が職場で発揮されるかどうかは、受講者の特性(自己効力感など)・研修設計(練習・フィードバック・職場への近接性)・職場環境(上司支援・機会提供)の3要素が相互に作用することが示されています。したがって、受講者の要件(志望動機・基礎スキル)や設計(反復練習・業務に近いケース)に加え、上司支援(実践機会の提供・評価との連動)を“必須要件”として織り込む必要があります。研修単体での効果を期待するのは危険で、環境設計も成果の半分を占めると捉えましょう。
以下の表2では、コルブの「経験学習サイクル」と、ボールドウィン&フォードが示した「学習転移モデル(Transfer Model)」を掛け合わせ、研修設計時に確認すべき観点を整理しています。
▶表2:経験学習×転移モデルのチェック
経験学習モデルのフェーズ | 設計チェック項目 | 転移モデル対応要素 |
|---|---|---|
経験 | 受講者が自分の業務課題を題材に実践・体験できる設計になっているか | 職場近接性(業務に即した内容) |
内省 | 振り返りの時間が十分にあり、学びや気づきを言語化・共有しているか | 受講者特性(内省力・自己効力感) |
概念化 | 理論やフレームワークを共有し、体験から得た気づきを整理・理解しているか | 研修設計(理論との接続) |
実践 | 学びをもとに次の行動を計画し、職場で再実践する機会が設けられているか | 職場環境(上司支援・実践機会) |
<支援・フィードバック> | 上司や講師が定期的に進捗を確認し、具体的なフィードバックを行っているか | 職場環境(支援・評価連動) |
※「支援・フィードバック」は、学習サイクルそのものには含まれませんが、職場で学びを活かすための重要な支援要素です。
実務への落とし込み:各回で「経験→内省→概念化→再実践」を完結。上司の確認欄を運用。
研修前・中・後のLXD設計と運用
研修の成否は“前後”で決まります。カークパトリック(Kirkpatrick)の4段階評価に連動させ、研修前の目的・環境設計から、研修後の行動・成果回収までを一貫して設計します。
事前:目的・業務課題・上司関与の三点留め
カークパトリックは、研修効果を「反応(Reaction)→学習(Learning)→行動(Behavior)→成果(Results)」の4段階で評価する枠組みを提案しました。ここで特に重要なのは、成果から逆算して行動を定義することです。
まず、経営・事業のKPI(例:粗利率、解約率など)に直結する行動定義を作成します。次に、各受講者に自分の業務課題を事前に提出してもらい、それを評価指標と連結します。最後に、上司の関与を明確に取り決めます(1on1の回数、実践機会の提供、評価への反映など)。
この三点を研修前に固めておくことで、研修は単なる“知識提供の場”ではなく、行動変化を起こすための仕掛けとして機能するようになります。
研修~実践:スモールステップで現場課題へつなぐ
研修中は、学びをスモールステップに分解し、翌週の業務で即試す流れを作ります。
たとえば「営業打合せで仮説検証の質問テンプレートを1回使う→録音して振り返る→次週に改善案を適用する」といった形です。
研修後は、チームのOKRや部門KPIに接続し、行動ログ(実践回数、適用案件、成果の差分)を継続的に収集します。月次ではカークパトリックの第3層(行動変化)を確認し、四半期では第4層(業績成果)への反映を確認します。
さらに、行動や成果のデータを見える化し、現場と人事部が共通の情報をもとに進捗を確認・支援できる仕組みを整えます。この仕組みによって、受講者の行動変化をリアルタイムに把握し、上司や人事がタイミングよくサポートできるようになります。
この一連の流れを、カークパトリックの4段階評価と対応づけて整理すると、図2のようになります。
▶図2:Kirkpatrick連動の運用フロー
実務への落とし込み:受講前に業務課題を提出させ、上司確認・合意のプロセスを設計に組み込む。
タフアサイン代替/補完としての「擬似現場」設計
現場で大規模な権限委譲を行うことは、今の環境では簡単ではありません。人手不足やリモート化により現場の余白が減り、上司もリスクを取りづらくなっているためです。しかし、設計次第で“現実に近い摩擦”を安全に再現することは可能です。ここでは、擬似現場と越境学習を活用して戦略思考を鍛える方法を紹介します。
事業創造シミュレーション/越境共創の型
「擬似現場」は、事業創造シミュレーション(市場データの分析、P/L制約、意思決定会議の再現)と、越境共創(他社や他部門と協働し、実際の課題に挑むプロジェクト)を組み合わせて設計します。
評価の軸は、成果そのものよりも「意思決定の質」です。たとえば、仮説の明確さ、代替案の検討、学習ログの深さなどを重視します。ポイントは、収益への影響は小さく、学習上の摩擦は大きく設計すること。社外の視点や顧客の声を取り入れながら、“痛みを伴う意思決定”を安全に体験できる場をつくります。
当社ではこれに加え、LMS(学習管理システム)や動画教材を組み込み、知識のインプット→実践→レビューを短いサイクルで回す仕組みを取り入れています。これにより、学びと実践の往復速度を高めています。
制約条件の設計で戦略思考を鍛える
戦略の質は、「限られた資源の中で、何を捨て、何に集中するか」の判断に現れます。擬似現場では、資金・人員・時間・データなどの制約条件を意図的に設定し、その中で優先順位をつけるプロセスを体験させます。意思決定会議の“冷や汗をかくような瞬間”を再現することで、戦略的対話やチームの意思統一の力が磨かれます。
また、心理的安全性を守るために、役職記号の解除(役職を外した対話)や観察者による質問権の設定などのルールを併用します。これにより、挑戦的な仮説提案が生まれやすくなり、実務に戻った際にも“迷わず打ち手を出せる”状態をつくります。
擬似現場を設計する際は、どの要素をどの程度「現実に寄せるか」を慎重に決めることが重要です。以下の表では、設計時に検討すべき主要な要素を整理しています。
▶表3:擬似現場設計の主要な設計要素
設計要素 | チェック観点 | 設計例 |
|---|---|---|
目的設定 | 学習の焦点を明確にしているか(思考/意思決定/実行など) | 戦略思考・リーダーシップ強化 |
対象・期間 | 対象層と実施期間を適切に設定しているか | 次世代リーダー層・6か月プロジェクト型 |
フィールド | どの現場・テーマを模擬するかを定義しているか | 他部門連携・社外越境型 |
制約条件 | 資源制約を意図的に設定し、トレードオフを可視化しているか | 資金上限・人員・時間・データ制約 |
実務への落とし込み:役員レビュー会を模擬実施。決裁資料は実フォーマットで提出。
効果測定とスケール:データで磨く育成ポートフォリオ
単発の“良い研修”を量産しても、組織能力は上がりません。データで回し、学習施策を資産化する運用と、スケールのコツを述べます。
4段階評価×行動データ:小さく回して深く学ぶ
カークパトリックの第1〜4層(反応・学習・行動・成果)は、受講直後のアンケートやテストだけで終わらせず、行動データと成果指標に結びつけて運用します。
たとえば、
行動ログ: 実践回数、適用案件、上司コメント
成果指標: KPIの改善度、提案件数など
これらを個人・チーム・組織全体といった複数レベルで確認できる仕組みを作り、「どの層で学びが定着しているか」を見える化します。
仮に複数部門から選抜されたメンバーによる横断型プログラムとして設計する場合、
1回の実施(=1期・1バッチ)をひとつの検証単位とし、6〜8週間の短期スプリントで運用します。この期間中に、上司の関与度や実践機会の有無が成果にどの程度影響するかをデータで確認し、効果が確認できた仕組みだけを標準化して、次期以降の選抜研修に反映します。このように、小さく試して深く検証しながら広げていくことが、最終的に最速の全社スケールにつながります。
自社事例の学習資産化:ナレッジ運用のコツ
成功・失敗事例は“教材”に再編集し、5分動画×テンプレでLMSに格納。検索しやすいタグ(課題領域・業界・指標)を付け、毎月のアクションラーニングに再利用します。当社の導入事例でも、短尺動画+ワークシート運用により、自律学習の回転数が上がり、研修の“前後”で学びが接続されました。ナレッジの再利用率をKPIに据え、動画視聴→現場実践の連動を計測します。事例が蓄積されるほど、育成コストは下がり、品質は上がる――学習資産は増やすほど強くなる設計にしましょう。
実務への落とし込み:成功/失敗を5分動画化し、テンプレとセットで翌月の題材に。
まとめ
- 70-20-10の考え方は「配置と接続」の設計課題。現場の経験・他者との学び・教育機会を一つの流れとしてつなぐことが重要です。
- アクションラーニングは「問い・行動・安心」の循環。チームの対話の質が、学びの深さとスピードを決めます。
- 学びを職場で生かす鍵は環境。設計だけでなく、上司の関与や実践の場を制度として組み込みましょう。
- カークパトリックの視点では「成果から逆算」。行動を定義し、記録とKPIの変化で効果を確かめます。
- タフアサインの代わりに「擬似現場」を設計する。制約と他者の視点を組み合わせ、戦略的に考える力を鍛えます。
この5つの視点を押さえ、6〜8週単位で小さく試しながら検証を重ねましょう。
効果が確認できた設計要素を標準化していくことが、最速の全社スケールにつながります。
FAQ
·
· Q1. アクションラーニングとPBL(課題解決型学習)の違いは?
A. PBLは解の探索寄り、アクションラーニングは現場実践と問いの往復で能力を鍛える点が核。成果責任を伴う実課題を扱い、心理的安全性や観察者によるプロセス振り返りを組み込むのが基本です。
· Q2. リモート下でも効果は出せますか?
A. はい。会話の質を担保するルールと、短い実践サイクルの設計が鍵。上司1on1やピアレビューをオンラインで定例化し、行動ログとKPIをダッシュボードで共有すれば、距離は大きな障害になりません。
· Q3. どの層から始めるべき?若手でも早すぎませんか?
A. 人手不足・高齢化下では早期選抜の加速が合理的。6~8週の短周期で“安全な摩擦”を経験させ、上司の伴走を条件化することで、若手でも戦略思考の土台を築けます。
· Q4. 研修効果が曖昧になりがち。何を測れば良い?
A. 行動定義→行動ログ→KPI差分の三段測定が基本。カークパトリックの第3層(行動)と第4層(成果)を月次/四半期で確認し、効いた施策だけ標準化します。
· Q5. タフアサインが減った現場での代替策は?
A. 擬似現場+越境共創を設計。制約強度を高め、他部門や社外の視点を入れて意思決定の質を鍛えます。実データの使用率や仮説更新回数で学習を測りましょう。
· Q6. 自社の導入事例を教材化するコツは?
A. 5分動画+テンプレで再利用可能性を高め、タグ(課題・業界・指標)で検索性を担保。LMSに蓄積し、アクションラーニングの題材として回し続けると、学習コストが逓減します。
参照・出典
· Center for Creative Leadership(2024)「The 70-20-10 Rule for Leadership Development」https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/70-20-10-rule/
· Ministry of Health, Labour and Welfare(2023)「Age of the 100-Year Life – Current State of Employment…」PDF https://www.mhlw.go.jp/content/10500000/001086776.pdf
· Reuters(2025)「Japan firms face serious labour crunch from aging population, survey shows」https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/japan-firms-face-serious-labour-crunch-aging-population-survey-shows-2025-01-15/
· Reg Revans(2017)『ABC of Action Learning』Taylor & Francis
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315263533/abc-action-learning-reg-revans
· David A. Kolb(1984)『Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development』(書誌情報)
http://search.library.wisc.edu
· Baldwin, T. & Ford, J.(1988)「Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research」PDF https://gwern.net/doc/psychology/1988-baldwin.pdf
· Edmondson, A.(1999)「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」PDF
https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Group_Performance/Edmondson%20Psychological%20safety.pdf
· Kirkpatrick, J. & Kirkpatrick, W.(2006)『Kirkpatrick’s Four Levels of Training Evaluation』(書誌情報)https://archive.org/details/kirkpatricksfour0000kirk archive.org
· 経済産業省(2025)「White Paper / METI」
https://www.meti.go.jp/english/report/index_whitepaper.html
· サイコム・ブレインズ(2025)「導入事例|ビジネスマスターズ」
https://bm.cicombrains.com/case