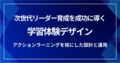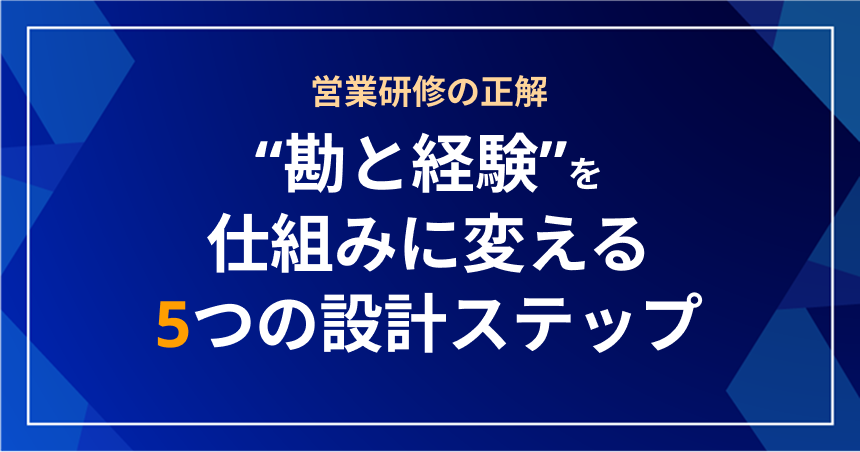
営業研修の正解|“勘と経験”を仕組みに変える5つの設計ステップ
「営業研修=ロールプレイばかりで現場に効かない」「先輩の暗黙知を言語化できない」「中途入社社員が自社の営業プロセスに馴染むまで時間がかかり即戦力化しない」。顧客の情報武装と意思決定の多層化が進むいま、個人の勘と経験だけに依存した育成は限界を迎えています。本稿では、MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部のオリジナルフレームワークHPC®(Hearing/Proposing/Closing)を核に、研修→定着→評価を一気通貫で結び、若手が“営業って楽しい”と感じるマインドセットまで含めて成果に変える設計を解説。明日から設計に使える手順を提示します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、“営業研修”が必要なのか
- 1.1.環境変化と営業スキルの再定義
- 1.2.属人化・暗黙知が育成を止める構造
- 2.研修だけでは不十分──定着・制度まで設計する
- 2.1.設計→実施→定着の“三位一体”
- 2.2.DX時代の育成は“データで回す”
- 3.HPC®で成功パターンを言語化し、共通言語にする
- 3.1.商談成功のための三原則HPC®
- 3.2.HPC®を“組織のOS”にする利点
- 4.若手・中途・マネジャーの“階層別”トレーニング
- 4.1.若手・中途の早期戦力化
- 4.2.マネジャー・OJT担当の“教える力”強化
- 5.「営業はつらい」を変える──マインドと成長実感の設計
- 5.1.「つらさ」の源泉を設計で断つ
- 5.2.演習・評価の“手触り”を高める
- 6.スキルの可視化・等級化で、育成と評価を連動
- 7.まとめ
- 8.MBK Wellnessの研修プログラム
- 9.FAQ
- 10.参照・出典
なぜ今、“営業研修”が必要なのか
営業現場はいま、オンライン商談が増え、社内調整が複雑になり、情報があふれる時代です。こうした環境では、営業は“話術”ではなく、顧客の意思決定を前に進める設計力が問われます。研修の存在意義は、まさにその設計力を再現可能なスキルとして育むことにあります。
環境変化と営業スキルの再定義
BtoB営業の現場では、顧客側の情報量が増え、ベンダー比較は高度化しています。単なる製品説明では差がつかず、顧客が「本当の課題」に気づいていない段階から、仮説を提示して考え方を揺さぶり、新しい視点で合意をつくる力が求められます。いわば、顧客の“前提”を問い直し、「気づきを生む営業」へと進化することが必要なのです。
また、オンライン商談やメール・チャットでの意思決定も増え、質問設計・論点構造化・合意形成が不可欠に。つまり、営業研修は「うまく話す」ではなく、H(聴く)→P(提案)→C(取り決める)のプロセス設計能力を体得させる場へ進化させる必要があります。
属人化・暗黙知が育成を止める構造
「先輩の背中を見て育つ」風土では、何を学べば即戦力化するかが曖昧になり、若手・中途の立ち上がりが遅れます。指導者不足・時間不足は日本の人材育成の代表的課題でもあり、プロセスの標準化と共通言語化が解決の第一歩です。HPC®は商談をH/P/Cに分解し、暗黙知を測れて教えられるスキルへ変換。OJT・会議・SFA・評価を同じ言語で運用できるため、属人化を抜け出しやすくなります。
▶図1:営業研修導入の流れ
実務への落とし込み
直近の勝ち商談3件をH/P/Cで分解し、再現条件を仮説化して共有開始。
研修だけでは不十分──定着・制度まで設計する
研修=イベントに終わらせず、定着運用=仕組みにする。これが投資対効果を変えます。
設計→実施→定着の“三位一体”
- 設計:対象別(若手/中途/管理職)に行動KPI(例:深掘り質問率、価値訴求の論点数、次回設定率)と成果KPI(受注率・客単価)を連結。
- 実施:自社案件を素材にHPC®ロールプレイ→翌日やる行動を個別に宣言。
- 定着:商談報告・会議・SFAの入力項目をH/P/Cで統一し、上司レビューとフォロー研修を設計段階から組み込む。
この“面をそろえる”設計が、研修と現場の断絶を埋め、成果の再現性を高めます。
DX時代の育成は“データで回す”
経産省はDXを経営課題として位置づけ、進め方・成功ポイントを公表しています。営業育成も同様に、プロセス指標をデジタルで可視化し、学習—実践—改善のサイクルを加速させるべきです。具体的には、H(質問深度)/P(ベネフィット提示率)/C(次回設定率)をSFAで収集・可視化し、会議でボトルネックの特定→打ち手の順に議論する運用へ。データで語る会議が、育成を“仕組み”に変えます。
▶図2:研修→定着→成果のロードマップ
実務への落とし込み
研修の最後に行動宣言+上司レビュー日を確約し、SFA項目と紐づける。
HPC®で成功パターンを言語化し、共通言語にする
HPC®は“商談成功の三原則”。誰がやっても同じ観点でレビューできるため、育成・会議・評価のOSになります。
商談成功のための三原則HPC®
- H:Hearing(聴く)──顧客の課題やニーズを理解するために、 適切な質問をして、 顧客になるべく多くのことを話してもらう。
- P:Proposing(提案する)──顧客のニーズを満たすために商品やサービスを提案する。それが顧客にもたらすベネフィットを伝える。
- C:Closing(取り決める)──購買の意思を確認する。 次回面談の目的や日時を細かく取り決めて面談を締めくくる。
HPC®を“組織のOS”にする利点
HPC®を組織内の共通言語にすると、①OJTの指導観点が揃う(「今日はHが弱い」など具体指摘)、②会議の生産性が上がる(案件停滞の箇所をH/P/Cで即共有)、③育成と評価が連動(スキル基準が明確)、④人が入れ替わっても教育の質がぶれない。明日から使える“共通のものさし”を作ることが、属人化脱却の近道です。
▶図3:HPC®ナレッジ展開構造
実務への落とし込み
直近の勝ち商談3件をH/P/Cで分解し、型の仮説をつくる。
若手・中途・マネジャーの“階層別”トレーニング
“誰に・何を・どこまで”を明確化。階層別にゴールとKPIを置くと、立ち上がり速度と教える品質が同時に上がります。
若手・中途の早期戦力化
· 0–3か月:基礎…HPC®の用語とスキル(質問・要約・次回設定)を日次チェック。
· 3–6か月:課題仮説提示…顧客の課題を仮説スライドで提示→検証。
· 6–12か月:合意形成力…Cの品質(合意の明確さ)をテンプレ化し、案件を前進。
併せてメンター同行→短サイクルでの振り返り、SFAのH/P/C項目入力で行動を可視化。小さな成功体験を連続させ、自信と再現性を育てます。
マネジャー・OJT担当の“教える力”強化
- フィードバック観点統一:HPC®観点のチェックリストでフィードバックを標準化。
- 暗黙知の言語化:自分の勝ち筋を問い(なぜ勝てた?)→行動(何をした?)→再現条件を明文化。
- 部下育成KPI:部下のH/P/C指標改善を評価に組み込む。
“自分で売れる人”から“育てられる人”に役割を転換し、組織の再現性を高めます。
▶表1:階層別トレーニングマトリクス
対象 | 主要ゴール | 代表KPI | 解説 |
|---|---|---|---|
若手0–3か月 | Hの基礎定着 | 質問数/面談 | 質問→要約→同意の型を日次で反復 |
若手3–6か月 | 課題提起P | 価値訴求率 | 提案の“論点—証拠—合意”を型化 |
中途 | 自社型適応 | 次回設定率 | 自社の稟議プロセスに沿って合意形成 |
マネジャー | 育成可視化 | チームHPC®指標 | 会議・評価・OJTを同言語で運用 |
実務への落とし込み
各層に90日ロードマップ+H/P/C KPIをセット。週次でレビュー・是正。
「営業はつらい」を変える──マインドと成長実感の設計
若手の離職要因は「やっても成果に結びついた実感がない」。成功体験の設計で“楽しい”に変えます。
「つらさ」の源泉を設計で断つ
行動と成果が結びつかないと人の心は折れます。HPC®の行動単位KPI(質問の深さ/価値訴求の明確さ/次回合意率など)を可視化し、小さな成功体験を意図的に作ることで、「できた→次もやれる」のループを回します。役割の意味付け(顧客の意思決定を前進させるパートナー)を研修冒頭で共有し、自己効力感を高める設計が有効です。
演習・評価の“手触り”を高める
- 自社ケース×HPC®総合ロープレ:実案件に近い素材で練習し、翌日適用点を明記。
- 定量+定性の相互評価:質問の種類、論点の明確度、合意文の品質を数値化。
- フォロー会:30日後に録音・議事メモを持ち寄り、前後比較で成長実感。
- 称賛の仕組み:会議で“今週のH/P/Cベスト”を称える。
こうした“手触りのある”しかけで、楽しさ=上達の自覚を確立します。
▶図4:モチベーション循環
実務への落とし込み
「今週のH/P/Cベスト」を週次会議に常設。称賛を制度化し、継続の燃料に。
スキルの可視化・等級化で、育成と評価を連動
学んだ→やった→伸びたを証拠で示す。可視化と等級化が、育成を経営資本に変えます。
H/P/Cを“測れる言葉”にする指標設計
- H:深掘り質問率、要約頻度、顧客視点の発話比率。
- P:価値訴求の数、証拠提示率、反論対処成功率。
- C:次回アポ設定率、合意の明確度(5W1H)、期日遵守率。
SFAダッシュボードで個人/チーム/商材の粒度で可視化し、会議でボトルネック→打ち手を議論。DXが強調するデータ駆動の改善を、営業育成にも適用します。
等級・ロードマップ・評価への落とし込み
- 等級例:Lv1=H基礎(深掘り質問率80%)、Lv2=P提案力(価値訴求2論点/提案)、Lv3=C合意形成(次回設定率90%)、Lv4=チーム育成(部下HPC®指標の改善)。
- ロードマップ:各等級に研修・OJT・KPIを割付し、昇格要件を行動×成果で明文化。
- 評価連動:成果KPI×プロセスKPIの二軸で評価し、納得度と再現性を担保。
学習がキャリアに直結する設計が、定着と自走を促します。
▶図5:等級化モデル例
人事×営業でHPC®等級表(ドラフト)を共同設計。次期評価で試験運用。
まとめ
“勘と経験”に依存した属人化は、オンライン商談や社内調整が増える中で限界に。研修は型の共有と制度運用の出発点です。
HPC®(H/P/C)で成功パターンを言語化し、研修—OJT—会議—SFA—評価を同じ言語で回すと再現性が生まれます。
若手・中途・マネジャーの階層別ロードマップと、小さな成功→可視化→称賛の設計で“営業の楽しさ”を醸成。
指標設計と等級化により、育成を経営とつなぎ、投資対効果を継続的に説明可能に。今期はまず、勝ち商談のH/P/C分解→指標定義→レビュー運用から着手し、90日で“回る仕組み”を立ち上げましょう。
MBK Wellnessの研修プログラム
FAQ
Q1. ロールプレイは形式的になりませんか?
自社ケース×HPC®観点で設計し、翌日から実践する行動を個別に言語化して終えるのがコツ。商談報告・SFA・会議と同一用語(H/P/C)で運用すれば、練習と実務が直結し“やりっぱなし”を防げます。
Q2. 中途の即戦力化、最初の90日で何を?
Hの基礎(質問→要約→同意)→Pの提案力→Cの合意形成を順に標準化。メンター同行+短サイクルでの振り返り+SFA入力を3点セットで回し、次回アポ設定率などのKPIでトラッキングします。
Q3. 先輩の暗黙知をどう言語化する?
自分の勝ち筋を問い(なぜ勝てた?)→行動(何をした?)→再現条件を明文化し、H/P/C欄に配置。部下育成KPIにH/P/C改善を入れて定着させます。
Q4. 若手の“営業はつらい”を変える方法は?
小さな成功→指標で可視化→称賛の循環を制度化。会議冒頭の「今週のH/P/Cベスト」と30日フォロー会(録音・議事の前後比較)が、上達の手触りを生み、楽しさにつながります。
Q5. データ化までやる必要はありますか?
あります。DXの要諦は可視化→改善。H/P/CをSFAで数値化し、会議で停滞フェーズ→打ち手を議論することで、研修投資の説明責任と改善速度が上がります。
Q6. HPC®は自社の特殊な商材にも合いますか?
HPC®はフェーズ定義(H/P/C)という“器”なので、商材・業界を問いません。質問・価値訴求・合意の品質を自社版KPIに落とし、教材と会議・評価を同言語化すれば、カスタム適用が可能です。
参照・出典
- 経済産業省「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き(2025)」PDF
- Penguin/Portfolio『The Challenger Sale』(2011)出版社ページ(仮説提示型営業に関する一次情報)